どんな本?
『大阪・関西万博 「失敗」の本質』は、2025年に開催予定の大阪・関西万博に関するノンフィクション作品である。本書は、政治、建築、メディア、経済、都市の5つの視点から、万博の問題点や課題を多角的に分析し、その本質に迫る内容となっている。
著者プロフィール
• 松本 創:編著者。1970年大阪府生まれ。神戸新聞記者を経てフリーライターとして活動。主な著書に『誰が「橋下徹」をつくったか―大阪都構想とメディアの迷走』、『軌道―福知山線脱線事故JR西日本を変えた闘い』などがある。
書籍の特徴
本書は、以下の専門家による各章で構成されている:
• 第1章:木下功氏が「万博と政治」について、維新政治のリスクを分析。
• 第2章:森山高至氏が「万博と建築」について、会場となる夢洲の地盤問題を指摘。
• 第3章:西岡研介氏が「万博とメディア」について、電通や吉本興業の関与とその影響を検証。
• 第4章:吉弘憲介氏が「万博と経済」について、経済効果の実態と問題点を解説。
• 第5章:松本創氏が「万博と都市」について、大阪の歴史的文脈から万博を考察。
これらの視点から、万博の抱える課題を多角的に浮き彫りにし、読者に深い洞察を提供する。
出版情報
• 出版社:筑摩書房
• 発売日:2024年8月8日
• ISBN:978-4-480-07641-0
• ページ数:256ページ
読んだ本のタイトル
大阪・関西万博「失敗」の本質
著者:松本創 氏
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
誤算を認めないニッポンの縮図
理念がない、仕切り屋もいない、工事も進まない。なぜこんな事態のまま進んでしまったのか? 政治・建築・メディア・財政・歴史の観点から専門家が迫る。
感想
カジノ誘致という裏テーマの存在
表向きは「未来社会のデザイン」を掲げながら、実態はカジノ建設のためのインフラ整備であったという構図に驚きを禁じ得なかった。地盤の脆弱性や莫大な予算の存在は、万博ではなくIR(統合型リゾート)に向けた準備であったと気づいたとき、納税者としての無力感が深まった。公金で整えた基盤を民間が利用し、イベント後にはすぐ解体される構造に、虚しさばかりが残る。
維新と財界による利得の構造
本書を通じて明らかになったのは、維新の政治勢力と関西財界が「成果」として万博を利用し、成功のイメージだけを残して去る構図であった。残された府民と国民は負担のみを押し付けられ、イベント終了後に「いったいあれは何だったのか」と疑問を抱く姿が目に浮かんだ。税金を使い、恩恵を受けた者は誰かという問いがずっとつきまとった。
メディア・広報の不在と情報の不透明さ
東京五輪で問題視された電通が今回は関与を避け、吉本興業までもが途中で撤退したことにより、広報戦略は混乱を極めた。情報発信の不在により、国民の関心は高まらず、公式キャラクター「ミャクミャク」すら不気味だと評された。そもそも、誰に向けて何を発信しているのかが不明であった。結果、信頼の欠如と無関心が同時に進行した。
仕切る人間が不在という構造的問題
事業の中心を担うはずの万博協会には、プロジェクト全体を統括するリーダーが見当たらなかった。財務責任者不在、トップの常駐なし、ピラミッド型組織の弊害により、現場は混乱と疲弊に包まれていた。各国パビリオンの建設も遅れが目立ち、最終的に間に合わない可能性さえ語られていた。
都市政策としての限界と過去への執着
夢洲という地が繰り返し失敗を経験してきた土地であるにもかかわらず、また同じように万博とIRで再活用されようとしている。湾岸開発の幻想にすがり、1970年の万博という過去の成功体験に縋る姿勢が、未来志向とはほど遠い。時代錯誤の政策が、今また繰り返されようとしていた。
市民不在のイベントがもたらす未来
市民の関心が低く、支持も得られないまま進行する万博は、本来の理念を失ったまま漂っているように見えた。チケットの売れ行きや収支状況も不安視されており、終わってから「やはり失敗だった」と総括される未来が予見される。誰のための、何のためのイベントなのか。その答えが見つからないまま、開催の日が近づいている。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
備忘録
はじめに
迷走する万博と高まらぬ関心
大阪・関西万博は、会場建設費が当初の2倍に膨らみ、海外パビリオンの建設遅延や撤退国の出現、さらにはガス爆発事故などの問題に直面していた。災害リスクも指摘されたが、防災計画は依然として不十分であった。2024年4月時点の世論調査では、万博に関心を示す国民はわずか3割にとどまり、関心がないと答えた割合は倍以上に達していた。
会場とコンセプトの説明不十分
会期は2025年4月13日から10月13日までの184日間、会場は大阪湾の人工島「夢洲」であった。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」とされ、SDGsの達成に資する内容が掲げられたが、実際に何が展示されるのか、体験できるのかは明示されていなかった。公式キャラクター「ミャクミャク」も謎に包まれた存在であり、企画全体の不透明さが関心の低さを助長していた。
迷走の原因と複合的な要因
万博準備が混乱した要因としては、ドバイ万博の延期、ウクライナ戦争による物価高騰、建設業界の人手不足といった外的要素に加え、万博自体の計画と体制に内在する問題が挙げられた。本書ではこれらの点を多角的に検証し、開幕前にその本質を明らかにすることを目的としていた。
「失敗」と断ずる意義と批判への備え
開催前に「失敗」と言及することは批判を招く行為であるが、メガイベントでは事前の懸念が軽視され、終了後は「成功だった」と総括されやすい傾向がある。本書はそのような空気に抗い、「成功」の恣意的な定義に流されず、開幕前に冷静な検証を行う意義を強調していた。
五つの検証テーマと書き手の人選
本書では、「万博と政治」「万博と建築」「万博とメディア」「万博と経済」「万博と都市」の5つを検証テーマとし、編著者が信頼する記者や研究者に執筆を依頼した。それぞれが独立して寄稿したにもかかわらず、共通する「失敗」の本質が浮かび上がる構成となっていた。
個人的背景と万博への思い
編著者である松本創氏は、1970年の大阪万博開幕直前に会場近くで生まれた。自身の原風景には万博記念公園が深く刻まれており、過去に40周年の機に取材を行った経験もあった。今回はその延長として、信頼できる編集者の声かけを得て、万博を再考する機会を得たことに感謝の念を示していた。
第 1章
維新「政官一体」体制が覆い隠すリスク──万博と政治
木下 功 氏
歓喜の決定とその後の混迷
2018年11月24日、パリでのBIE総会にて2025年万博の大阪開催が決定された。大阪では府・市、経済界関係者が歓喜に沸き、万博誘致が成功裏に終わったかに見えた。しかし、年月の経過とともに、会場建設の遅延、海外パビリオン設計の停滞、建設費の膨張、爆発事故など深刻な問題が次々に表面化した。
夢洲という土地選定の不透明性
会場となる夢洲は人工島であり、軟弱地盤とアクセス不足という構造的欠点を抱えていた。もともと廃棄物処分場や港湾物流拠点として活用されていた土地であり、イベント会場としての適性に疑問があった。にもかかわらず、府・市首長や一部有識者の主導により、夢洲への開催地決定が既定路線化された。
万博とIR誘致の並行的進行
夢洲はIR(統合型リゾート)誘致計画の候補地でもあり、万博とIRのインフラ整備が重なる形で進められていた。IR計画の前提としてのインフラ投資が万博という名目で先行実施されていた可能性が指摘され、市民の反発を招いた。住民投票条例案が府議会に提出されたが、維新と公明党の反対多数で否決された。
夢洲への誘導と有識者会議の形骸化
2016年からの基本構想検討会では、既に夢洲を想定した試案が提出されていた。有識者による候補地選定は形式的に行われ、府主導による夢洲誘致の既成事実化が進められた。議論の場では夢洲以外の候補地を否定する声が上がり、IRとUSJの集客力を理由に夢洲開催が支持されていった。
維新と政権の協調による誘致推進
維新の府市政と安倍政権は、万博誘致を共同で進めた。安倍首相・菅官房長官の国会答弁や記者会見は、消極的だった関西財界に大きな影響を与えた。2016年以降、府・市・経済界・国が連携し、夢洲開催を軸とした計画が急速に進展した。
吉村市長の政治的アピールと責任の曖昧さ
誘致成功を「府市一体の成果」と位置付けた吉村市長は、万博を政権の成果としてアピールした。2023年の知事選でも「誘致に関わった責任」を理由に再選を目指したが、同時に会場建設費の増額、工期遅れ、安全対策の遅延といった課題に対する説明責任を十分に果たしていなかった。
協会の見通しの甘さと増額の正当化
会場建設費は2度にわたり増額され、最終的に当初の1.9倍の2350億円に達した。協会側は物価高や円安を理由に挙げたが、いずれも事前に予測可能な事象であり、見通しの甘さが露呈した。増額の内訳や経緯も曖昧なままで、協会のガバナンス不足が浮き彫りとなった。
防災計画の曖昧さと孤立リスク
夢洲には避難施設が設置されておらず、橋やトンネルが地震で使用不能になった場合、来場者15万人が島内に孤立するリスクが現実化した。協会の防災基本計画は抽象的で、避難経路や備蓄体制に具体性が欠如していた。市や府の責任者も、詳細な避難計画の必要性を認識しつつ、未策定のままであった。
液状化リスクと想定の誤り
夢洲では過去に液状化の可能性が指摘されていたが、防災基本計画では液状化しないとの前提で策定されていた。実際にはIR工事で液状化対策のために公金が投入されており、避難経路として想定される舞洲・咲洲も液状化の高リスク地帯であることが判明していた。
爆発事故と情報公開の不備
2024年3月、夢洲会場でメタンガス爆発事故が発生した。協会の情報公開は遅れに遅れ、追加被害も後日判明した。大阪市議会では協会の説明不足が問題視され、市長も安全対策強化を表明したが、協会の消極的な姿勢は変わらなかった。
検証機能の欠如と組織的問題
万博協会は公益社団法人として情報公開請求の対象外であり、議事録の未公開や検証体制の欠如が組織的問題として残った。東京五輪の組織委と同様、解散型組織であるため、不正や失策の検証が困難な構造的課題を抱えていた。
議事録の削除と情報統制の懸念
2024年5月、大阪府のホームページから万博関連の議事録が削除されたことが確認され、情報統制の疑念が高まった。市民や議会からの疑問の声に対しても、協会や行政側の対応は不十分であり、透明性の確保が課題として残された。
第 2章
都市の孤島「夢洲」という悪夢の選択──万博と建築
森山高至
海外パビリオンの建設危機
大阪・関西万博では、多くの海外パビリオンが完成しない可能性が高まり、一部の国々は建設そのものを断念した。これはパビリオンだけでなく、インフラ整備の遅延によるもので、建設業者の確保も困難な状況にあった。協会は各国の事情と主張したが、建設を担う日本側の都合が根本原因であったと推察された。
夢洲の土地特性と不適切な開催地選定
夢洲は産業廃棄物処理場として機能してきた埋立地であり、開催地としての整備には急速な造成が必要であった。地盤は不安定で沈下が続いており、地下には有害物質が存在する恐れがあった。にもかかわらず、短期間での埋め立てによって会場が整備され、土地としての安定が不十分なまま建設計画が進行した。
杭打ちと掘削に関する厳しい制約
パビリオン建設においては、杭を深く打つ必要があるにもかかわらず、撤去を義務づける制約があり、コストと工期の面で大きな負担となった。また、地下2.5メートル以上の掘削が禁止され、地下室の設置が困難となり、多くのパビリオンの設計変更を余儀なくされた。これらの制約は構造設計に深刻な影響を及ぼした。
ガス爆発と今後の安全懸念
2024年3月にはメタンガス爆発事故が発生し、夢洲の埋設物がもたらす安全上の問題が顕在化した。浚渫土などに含まれる有機物から発生する可燃性ガスは、施工中および開催中も継続的なモニタリングを必要とする。協会の「安全宣言」は根拠を欠き、再発防止策の徹底が求められた。
交通インフラの欠如と「都市の孤島」問題
夢洲は大阪市中心部から孤立した位置にあり、アクセスは限定された道路に頼っていた。地下鉄延伸は未完成であり、工事車両や作業員の移動にも大きな制限があった。駐車場や電源設備も不十分で、作業効率が著しく低下していた。これにより、工事全体の進行に重大な支障が生じていた。
残業規制と工期遅延の現実
2024年からの労働時間規制強化により、建設業界では従来の残業ベースの工程管理が不可能となった。二交代制による対策は費用増を招き、人件費や資材費の高騰と相まって、工期とコスト両面で厳しい状況に追い込まれた。この影響で、工事進捗率の著しい低下が見込まれた。
資材高騰と為替リスクの影響
世界的な資材不足や紛争の影響、円安進行によって建設費は大幅に上昇した。建材価格の上昇により、総工費は当初の見積もりから40%以上の上振れが予想され、今後も追加費用の発表が続くと見込まれた。これらの背景には、無理な費用設定と不適切な開催地選定があった。
タイプXと協会の不透明な方針
夢洲の会場建設には地盤・労働・資材・立地・気候といった厳しい条件が重なっており、通常の建設でも困難な中で各国が個別にパビリオンを建てるという前提そのものに無理があった。にもかかわらず、万博協会は華やかで個性ある展示空間を前提とせず、雑居ビル型の簡易建築「タイプX」を導入しようとした。これはプレハブに薄板や緑化シートをかぶせた簡素なものであり、参加国の希望に反して事前発注されたが、撤回によりキャンセル料も発生した。
建築制度と言語対応の不備
万博協会の提供した資料は英語・仏語に限定され、国連公用語での対応がなく、多くの国で建築法規の理解が進まなかった。結果、参加国は独自設計を国内で進めた後、日本の法規に準拠させる「翻案設計」の段階で対応に苦慮した。特に日本との人的ネットワークが希薄な国々では、適切な設計事務所や工事業者が見つからず、設計自体が停滞する例が相次いだ。
契約形態とリスクの過多
タイプA方式は参加国自身が発注主体となり、契約書や保証対応を含む複雑な手続きを日本側企業と個別に交わす必要があった。しかし、日本国内の建設会社は海外発注に不慣れで、支払いの遅延リスクや通貨・言語の壁を懸念して受注を避けた。結果として、受注可能な業者は大手・準大手ゼネコンに限られ、中小企業は契約形態の複雑さと資金リスクから撤退せざるを得なかった。
電通の不在とプロジェクトマネジメントの欠如
東京五輪で役割を担っていた電通が大阪万博では機能せず、契約仲介・支払い代行・信用保証など裏方機能が不在となった。1970年の大阪万博では竹中工務店が全体統括を担い、施工の指揮と分配を一元化していたが、今回はそのような中核ゼネコンが存在せず、現場は分散され、工事進行は非効率に陥った。特に木造リングの工事では、安全性の議論も統一されず、杭打ちの可否すら現場ごとに判断が分かれた。
木造リングの視覚的誤認と実務上の障害
万博協会は木造リングの建設進行を成果として強調したが、それはパビリオン建設の遅れを覆い隠す視覚的トリックとなった。リングは来場者に会場の完成を錯覚させ、関係者の危機感を麻痺させる効果を持っていた。さらに、先行配置されたリングにより建材搬入ルートが制限され、大型機材の通行が困難となるなど、建設進捗に実質的な障害を与えていた。
根本的な議論の欠如と理想論の暴走
問題の根底には、本質を見据えない机上の理想論があった。かつての高度経済成長期とは異なり、現代日本は少子高齢化による労働力不足が深刻であり、大規模再開発や国際イベントを支える人材が著しく不足していた。にもかかわらず、計画の立案者たちは現場実情に無理解なまま進行し、持続可能性を無視した構想を理想論で正当化していた。
人手不足と受注忌避の現実
現場では高齢の作業員すら不足しており、パビリオン建設の多くはゼネコンに断られる状態が続いていた。本来ならば、受注可能な企業や人材を早期に確保し、現場を一元的に統括すべきだったが、そのための人事や予算措置も行われなかった。結果として各国は設計すら完成できず、着工が不可能なまま判断の先送りを余儀なくされていた。
開催意義の見失いと延期の必要性
大阪万博の計画は、そもそも世界的課題に対応する「人類的連帯」の視座を欠いたものであり、IR誘致という政治的目標に利用された側面も否定できなかった。地盤問題や土地整備の見通しの甘さが重なり、延期以外に現実的な選択肢は存在しなかった。最低でも半年、可能なら1年の延期を行い、構造的課題を抜本的に見直す必要があるという結論に至った。
第 3章
「電通・吉本」依存が招いた混乱と迷走──万博とメディア
西岡研介
東京五輪談合事件の影響
2021年の東京オリンピックに関する贈収賄事件が発覚し、広告代理店である電通を含む複数社が捜査対象となった。これにより電通は指名停止処分を受け、大阪・関西万博への関与が大幅に制限された。広報やPRを担うべき広告代理店が軒並み関与できなくなったことは、万博の機運醸成に深刻な影響を与えた。
広告代理店と博覧会の歴史的関係
1970年の大阪万博以降、日本の博覧会では広告代理店がPRや運営を一括して担う構造が定着していた。電通は過去の博覧会において、海外博の調査から企画・演出・運営に至るまで中心的な役割を果たしてきた。特に「つくば万博」「愛知万博」では、パビリオンの設計段階から電通のプロデュースが加わっていた。
大阪万博と維新との関係
今回の大阪万博において、広告代理店の主導権は維新と関係の深い大広に渡った。電通は自民党との関係を重視し、維新主導の大阪府・市との連携を回避していた。誘致段階からプロモーション映像の制作が大広に委託された経緯があり、その映像は後に政府の不満を招き、電通が修正する事態となった。
万博協会と東京・大阪間の不和
協会事務所の設置も政治的な駆け引きの影響を受けた。本来は東京に置かれるべき事務所が大阪に設置され、東京の電通社員は大阪への出張・通勤を強いられた。こうした体制の不備と、電通社員の撤退は、運営面でも混乱を生じさせた。
電通の姿勢と不参加の理由
万博の中核事業である「未来の都市」事業のプロポーザルに、電通は応募すら行わなかった。オリンピック談合事件を契機に、電通はコンプライアンスと企業評価リスクへの対応を強化し、官公庁案件への直接的営業活動を制限する方針へと転じていた。そのため、出向者の派遣や事前調整を避ける姿勢が定着した。
形式的な参加と開会式事業の受託
一方、2024年5月には、開会式運営を担う事業者として電通を含む共同企業体が選定された。ただし、実質的な業務主体はNHK関連会社であり、電通は裏方としての業務を担当するにとどまった。表向きの発表では電通が主導するかのように見えたが、実態は形式的参加であった。
将来視点と横浜花博への注力
電通は大阪万博をすでに消化試合と見なし、2027年に開催される横浜国際園芸博覧会(花博)に注力していた。花博は自民党主導であり、国交省と農水省が所管するため、電通にとっても関与しやすく、予算規模や収益性の面でも魅力が高かった。
吉本興業の台頭と地方創生戦略
電通の不在下で、大阪万博のPRを主導したのは吉本興業であった。同社は早期から地方創生事業に注力し、行政と包括連携協定を締結。大阪市とも連携し、「チーム関西」を組織して企業・メディアを巻き込んだPR活動を展開した。特に、ダウンタウンのアンバサダー就任やイベント開催を通じて、機運醸成に貢献した。
報道の中立性と読売テレビの離脱
在阪民放局のうち、読売テレビは「報道機関としての中立性」を理由に「チーム関西」への参加を見送った。特にIR事業への関与に慎重な姿勢を示し、必要に応じて万博への批判報道も辞さない立場を取った。この決定は、報道と広報が混同されるリスクを警戒するものであった。
読売グループによるIR拒否と万博不参加の姿勢
読売テレビは万博推進組織「チーム関西」から距離を置いており、その背景には読売グループ全体のカジノに対する否定的な姿勢があった。読売新聞はIR整備に批判的な社説を発表し、グループ内の広告会社も大阪IR関連業務を辞退した。これは過去の野球賭博問題による強い反省と、ギャンブルへの嫌悪感に基づくものであった。
吉本興業のIR連動戦略と万博への関与
吉本興業は、大阪IRの開業を視野に万博への関与を積極化させた。劇場・エンタメ施設での利害関係がIRに直結するため、万博をIR支援の一環として捉えた。吉本は大阪マラソンや文化芸術祭事業を受託し、さらに幹部社員を万博協会に出向させてイベント企画を主導した。
吉本体制への風当たりとスキャンダルの影響
万博における吉本主導体制は、大崎洋前会長の影響力が背景にあったが、その存在が「利益誘導」と批判されるようになった。松本人志の性加害疑惑が報道されると、吉本は当初否定したが、社外取締役の指摘により態度を軟化させた。この騒動を受けて、吉本は万博関連の公的事業から撤退を決定した。
吉本の完全撤退と企業戦略の転換
吉本興業は企業パビリオンの出展以外すべての万博関連事業から撤退することを取締役会で正式決定した。さらに、大阪府・市、国の公共事業からも距離を取る方針を明確にし、劇場中心の原点回帰へと舵を切った。背景には「税金を食い物にしている」との批判と、それによるレピュテーションリスクを回避したいという経営判断があった。
広報と催事のプロ不在による影響
電通と吉本という広報・催事の中核がいなくなったことで、万博の機運醸成は著しく停滞した。中小広告代理店ではノウハウが乏しく、実績不足により行政側も発注をためらった。協会が発表した116の催事の多くは政府や自治体主催であり、観客の興味を引くようなイベントに乏しかった。
協会内部の組織と人事の問題
万博協会の事務総長・石毛博行氏の指導力不足が組織の停滞を招いた。大阪に常駐せず、現場任せの姿勢により迅速な意思決定が行われなかった。過去には前田泰宏氏が副事務総長として活躍したが、わずか1年で退任しており、協会は長期にわたり実務を担える人材を欠いていた。
財務管理の欠如と予算増加の原因
万博協会は開催決定から5年以上、CFO(最高財務責任者)を置いていなかった。各部署が予算を独立的に使う構造の中、財務の俯瞰がなされず、支出は膨張した。大屋根「リング」の建設費は当初180億円から350億円に跳ね上がり、最終的に会場建設費は1250億円から2350億円に倍増した。
遅すぎた組織改革と不十分な対応
開幕約300日前の2024年6月、協会はピラミッド型組織を廃止し、横並びの12局体制に移行する方針を打ち出した。しかし、多くの企業関係者は「遅すぎる」「実務には影響しない」と評価し、問題の本質は協会と行政の不和にあると指摘された。
哲学なき万博の本質的欠陥
イベントプロデューサーは、大阪・関西万博の最大の問題点を「哲学の欠如」と断じた。1970年や2005年の万博は明確な理念と社会的ビジョンを持ち、長期間の準備と知識人の議論を経てコンセプトを練り上げた。それに対し、大阪万博はIR誘致が先行し、開催意義や基本理念が不明確であった。
経験の継承と運営プロの不在
過去の博覧会で得られたノウハウは広告代理店や専門企業に蓄積されていたが、東京五輪の不祥事によりこれらが排除された。博覧会の全体統括を担うスーパーゼネコンのような存在が不在となり、万博協会の現場対応能力は著しく低下した。
開幕後の可能性と不測の事態
過去の万博では事故や事件が報道を通じて注目を集め、来場者数の増加に繋がった例がある。ベテランプロデューサーは、今回の万博も始まってから評価すべきと述べたが、現時点では「哲学の欠如」「広報の失敗」「組織の不全」が揃い、懸念は深まるばかりであった。
第 4章
検証「経済効果 3兆円」の実態と問題点──万博と経済
吉弘憲介
万博経済効果の政治的強調
2023年12月、吉村洋文府知事はテレビ番組で万博の経済効果を2兆4000億円〜2兆8000億円と述べ、費用膨張への反論として経済効果の価値を強調した。2024年1月にはAPIRが拡張万博の効果額を最大3兆3667億円と発表し、大阪維新の会の市議も議会で経済効果を擁護する発言を行った。こうした政治的な主張は、費用対効果の議論をすり替えるものであった。
経済波及効果と外部性の基本概念
経済効果は短期の波及効果と中長期の外部性に大別される。短期では建設・運営による支出や雇用、長期では教育や交通整備といった持続的影響が該当する。1970年の万博や1964年の五輪ではインフラ整備による外部性が評価されたが、それらの成果も事後的にしか把握されず、計画段階での予測は困難であった。
短期的経済効果の構造と限界
短期の経済波及効果は、投入された資金がどのように産業に流れ、消費や雇用に影響を及ぼすかを産業連関分析により試算される。ただし、この手法は投入額が確実に供給されることを前提としており、労働力や資材が不足すれば想定通りの波及は得られない。また、同額の支出であれば別の事業でも同様の効果が出るため、万博の正当性を保証する根拠にはなり得なかった。
中長期の外部性とレガシー効果の評価困難性
教育やインフラ投資による外部性は社会に持続的影響を与えるが、事前に数値化するのは難しく、計画の恣意性を招く懸念があった。特に維新の会のような特定政党が成果を政治的に利用する構図は、正当な外部性評価の障害となっていた。
直接効果と試算根拠の恣意性
産業連関表を用いた計算では、最初の直接効果の見積もりが試算全体の信頼性を左右する。需要の見積もりが現実と乖離していれば、最終的な波及効果も過大評価となる。また、供給制約や資源競合が反映されないため、過大な試算が政策判断の誤りを招く危険性があった。
経済効果試算の変遷とその背景
2017年の試算では経済効果は1兆9000億円とされていたが、その後、建設費や来場者数の見積もりが増加し、試算額も上昇した。APIR、りそな総研、日本総研などが行った複数の試算では、直接効果の設定によって大きく結果が異なっており、恣意性の問題が浮き彫りとなった。
来場者数と消費単価の乖離
APIRの報告では2820万人の来場者を想定し、消費単価も観光庁の統計と乖離していた。特に宿泊単価や日帰り単価に関する根拠が曖昧で、2023年確報値との整合性がなかった。このような前提数値の不透明さは、全体の波及効果の蓋然性を損なっていた。
供給制約と労働力不足の見落とし
2024年問題や災害対応などにより、建設・運営に必要な労働力の確保が困難な状況が続いていた。労働供給が不足すれば事業全体の遂行に支障をきたし、結果的に期待された経済効果も実現されない可能性が高まっていた。
価格と需要の関係の無視
万博の入場料は7500円と過去の万博と比較して高額であり、需要の抑制要因となる可能性があった。しかし、経済効果の試算には価格弾力性が考慮されておらず、需要見積もりの現実性が乏しかった。こうした価格設計の問題も、試算の信頼性を低下させていた。
来場者数過大見積もりの危険性
万博協会は来場者2820万人を前提に試算していたが、過去の万博実績から見てこの数値は異常に高かった。ハノーヴァー万博の失敗例に見られるように、過大な来場者想定は赤字の原因となりうる。また、価格設定との整合性も取れておらず、蓋然性を欠いたまま数値が独り歩きしていた。
経済波及効果が政策正当性を保証しない理由
最終的に、経済波及効果は支出に応じて機械的に算出される数値に過ぎず、その事業の政策的正当性を保証するものではなかった。将来的に生じるマイナスの影響や経済循環上の副作用が無視されたまま、経済効果という数字だけが独り歩きすることの危険性が指摘された。
万博の事業会計において、入場料収入は建設費を賄うに足らず、運営費も物価高騰で当初より増加したため、収支は常に赤字前提で進められていた。このような事業に対する税金投入の正当性は、事業が社会にもたらす公益性によって判断されるべきであった。公共財としての性質を持つイベントであれば、税金投入の合理性が確保されるが、恩恵が特定の層に限定されるならば、その費用は受益者が負担すべきであるという論点が提示された。
短期的な損失と長期的利益のバランス
東京五輪では最終的に2兆円超の赤字が発生したが、民主的合意のもとで支出されたのであれば、政治的正当性を持ち得るとされた。短期的な経済効果は政治的合意を得るための便宜的な数値であり、実際にどれだけの長期的利益が社会に還元されるかが重要であった。公共投資の評価には、単なる経済効果だけでなく、社会的便益の持続的価値が問われた。
公共事業評価のための手法と限界
長期的な費用対効果の評価には、代替法やトラベル・コスト法、ヘドニックアプローチなど多様な手法が存在する。しかし、これらの手法は視覚化可能な利益や評価者の選好に依存しており、外部効果をどう捉えるかによって結論が左右される不確実性を残していた。公共支出の水準も各国・各時代の価値観に左右されてきたため、最適な支出水準は一義的に決められなかった。
大阪府民の評価と万博支持の乏しさ
2024年5月の調査によると、大阪府民は万博誘致を肯定的には捉えておらず、平均評価はマイナス0.34であった。一方で、評価が高かったのは二重行政の解消であり、これは維新の政策の中でも個人に直接利益が及ぶものに限られていた。IR誘致に関しても同様に低い評価が下され、個人にとってわかりやすい利益がない政策には支持が集まりにくい傾向が明らかになった。
維新の政策スタイルと万博との齟齬
大阪維新の会は、既得権益の解体と再分配による「身を切る改革」を進め、個人に明確な利益をもたらす政策によって高い支持を得てきた。都構想の住民投票では敗北したものの、合理的な個人判断によって票が動くという前提の下、維新は教育費無償化などの政策で一定の評価を得ていた。
公共財としての万博と支持の乖離
万博のような公共財は、全体への利益を前提とし、個人への配分が難しい性質を持つ。税金投入によって全体利益を得るという理念と、個別の利益を重視する維新のスタイルとの間には根本的な矛盾が存在した。維新が政治的に成功した要因である「コスパ重視」の視点が、万博のような長期的外部性を評価すべき事業に対しては適用困難であった。
価値の共有と万博の将来
万博の成否は、インフラ整備や地域経済連携、多様性の実現といった正の外部性をいかに可視化し、社会に共有させるかにかかっていた。維新が掲げる効率性とコストパフォーマンスの価値観を超えた議論ができるか否かが、長期的に残る「遺産」としての万博の価値を左右する最大の要素となった。
第 5章
大阪の「成功体験」と「失敗の記憶」──万博と都市
松本 創
博覧会と都市開発の歴史的文脈
明治期の博覧会と大阪の都市整備
大阪は1903年の第五回内国勧業博覧会を契機に博覧会都市としての歩みを始めた。京都との誘致合戦に勝利し、天王寺と堺に大規模な会場を設置した同博覧会は、外国産品の展示や遊戯施設の導入などで530万人超の来場者を集め、日本初の国際博覧会とされた。イベント後、会場跡地は天王寺公園や新世界に転用され、都市整備と娯楽の拠点として機能した。
大大阪時代と戦後の博覧会による街づくり
1925年の「大大阪記念博覧会」は、市域拡張と人口増加を祝うもので、博覧会は市民の祭りとしての側面も強かった。戦後も1970年の大阪万博と1990年の花博が開催され、千里丘陵や鶴見緑地の都市開発に直結した。これらの博覧会は都市の郊外化とインフラ整備を推進し、大阪の都市構造を大きく変化させた。
堺屋太一と万博再誘致の構想
維新のブレーンであった堺屋太一は、1970年の万博を成功体験として再評価し、再誘致を提案した中心人物であった。彼はイベントが社会や政治を活性化させると信じ、橋下徹や松井一郎との会食の席で2025年万博の構想を提案した。これが府市一体の都市改革と大阪万博の出発点となり、東京五輪との「セット効果」を主張する論理が維新の政治戦略に組み込まれた。
堺屋の思想と空疎な理念
堺屋は万博を「知価社会」や「好老社会」といった未来像の表現機会と捉えていたが、記者会見では理念の曖昧さと成功体験への過信が目立った。70年万博の収益や著名人の起用を誇示しつつ、現在の社会状況への対応には説得力を欠いた。大阪万博の構想はこのような空疎な夢想と政治的思惑の融合により現実化した。
博覧会の排除と差別の歴史
博覧会には植民地主義や差別の歴史も存在した。1903年の第五回博覧会では琉球・アイヌ・朝鮮・台湾の先住民族が「土人」として展示され、博覧会が国家権力と差別の装置である側面を露呈した。また、労働者の居住地「長町」は会場建設のために強制移転させられ、これが釜ヶ崎の起源となった。70年万博やその後のイベントでも日雇い労働者の排除が繰り返され、都市開発と排除の構図が顕在化した。
天王寺博覧会とジェントリフィケーション
1987年の天王寺博覧会は、花博に先駆けた都市整備の一環として開催されたが、終了後には天王寺公園が有料化され、労働者や野宿者が排除された。この一連の流れは「ジェントリフィケーション」として定義され、都市の再開発が貧困層の締め出しを伴う過程であることが指摘された。現代でも商業施設「てんしば」により同様の現象が続いていた。
湾岸開発構想とテクノポートの失敗
1980年代の大阪市は湾岸部の咲洲・舞洲・夢洲を再開発しようと「テクノポート大阪計画」を策定したが、バブル崩壊によって企業誘致が失敗し、計画は破綻した。情報通信や国際交易などの中核施設は機能せず、インフラ整備も効果を生まなかった。事業は第3セクター方式で進められ、経営破綻と過大融資が問題視された。
大阪五輪招致活動の挫折
大阪市は2008年五輪の招致を試み、湾岸エリアをメイン会場として活用しようとしたが、国際的評価は低く、最下位で落選した。市内からのアクセスの悪さや財政難が原因とされ、招致活動は失敗に終わった。それでも計画は止められず、湾岸開発の失敗と一体化して再び夢洲の利用計画は暗礁に乗り上げた。
成長幻想と湾岸開発の挫折
府庁移転とWTCビル取得の顛末
2009年、橋下徹知事は老朽化した府庁舎を咲洲のWTCビルに移転する構想を打ち出した。防災拠点や経済特区の中心地としての活用を意図し、府議会に庁舎移転条例案と買収案を提出したが、条例案は否決され、買収案のみが可決された。WTCはその後「咲洲庁舎」として一部利用されたが、東日本大震災時の長周期地震動で脆弱性が露呈し、防災拠点としての計画は断念された。
維新結党の原点と二重行政批判
この庁舎移転問題は、維新誕生の契機となった。橋下の構想に賛同した松井一郎らが、自民党内の若手グループとして分派し、2009年に「自由民主党・維新の会」を結成。翌年には「大阪維新の会」として正式に発足した。維新はWTCとりんくうゲートタワービルを税金の無駄の象徴として批判し、都構想と府市統合を掲げて政治的勢力を拡大していった。
夢洲選定の政治的経緯と不透明さ
堺屋太一は当初、1970年万博の遺産地である万博記念公園を会場に提案していたが、府は広域候補地の検討を経て、2016年に夢洲を会場とする構想をまとめた。有識者会議ではインフラやアクセスの利点を強調したが、軟弱地盤や液状化などのリスクについては十分に検討されなかった。技術系幹部らによる検討会も政治的判断に追従したとの指摘があった。
IR構想とカジノ推進の流れ
カジノ構想は橋下が初めて表明したものではなく、前任の太田房江知事時代から萌芽があった。橋下はIRを都市振興の鍵と位置づけ、民間団体や経済同友会と連携して推進した。2016年には国会でIR推進法が成立し、大阪市は夢洲でのIR構想を明確化。2021年にはMGM・オリックス連合が事業者に選定され、2023年に区域整備計画が国に認定された。
市民の無関心と支持の乏しさ
統一地方選で反維新候補はIRの危うさを訴えたが、市民の反応は鈍く、「夢洲は遠い」「生活に関係がない」との声が多かった。IRも万博と同様に、少数の推進派によって進められ、大多数の市民は無関心のまま進行していった。
混乱の原因とスケジュールの逆転
橋爪紳也教授は、混乱の原因をIRと万博の工事スケジュールの逆転に求めた。当初、IRを先に建設し、そのインフラを活用して万博を行う計画であったが、IRの遅延とコロナ禍により順序が逆転。未整備のまま万博が先行開催される事態となった。さらに、IR事業者に有利な条件が設けられ、地盤改良費への公金投入や安価な賃料契約が問題視された。
レガシーの喪失と都市像の不在
橋爪は、万博やIRが大阪の将来像を示すための布石であるべきとしながらも、現実には開催そのものが目的化してしまったと懸念を示した。1970年の万博以降、湾岸エリアの事業は未達成のままであり、今こそエンターテインメント都市としての位置づけを再考すべきとした。
成長幻想とイベント型政策の限界
大阪では「成長の起爆剤」としての万博やIRに過大な期待が寄せられてきたが、都心回帰が進む現代において、遠隔地での新都市構想は現実性を欠いていた。湾岸部に人為的に人の流れを誘導する政策は、過去と同じ失敗の繰り返しと見なされた。イベント偏重の政策による都市整備は限界を迎えていた。
維新政治と無責任構造の本質
大阪における維新の政治支配下では、政治と行政の線引きが曖昧になり、失敗の責任を誰も負わない構造ができ上がっていた。過去の成功体験に固執し、不都合を無視した万博の強行開催が進む状況こそが、大阪・関西万博「失敗」の本質であった。
その他フィクション

Share this content:
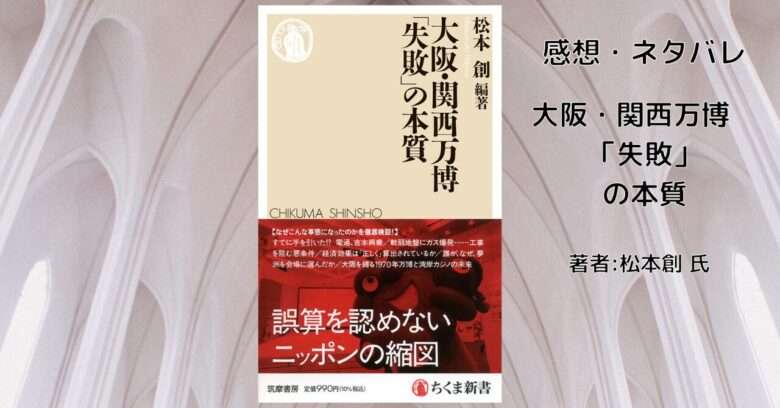

コメントを残す