どんな本?
「訂正する力」は東 浩紀氏著の書籍で、2023年10月13日に朝日新聞出版から出版された。
この本は、人間が誤ったことを訂正しながら生きていくという視点から、現代日本で「誤る」こと、「訂正」することの意味を問い、この国の自画像をアップデートするという内容。
本書は、哲学の魅力を支える「時事」「理論」「実存」の三つの視点から、保守とリベラルの対話、成熟した国のあり方や老いの肯定、さらにはビジネスにおける組織論、日本の思想や歴史理解にも役立つ、隠れた力を解き明かす。
また、本書は「訂正する力」を取り戻すことを提唱。
それは過去との一貫性を主張しながら、実際には過去の解釈を変え、現実に合わせて変化する力――過去と現在をつなげる力。
これは持続する力であり、聞く力であり、記憶する力であり、読み替える力であり、「正しさ」を変えていく力でもある。
東浩紀氏は、卓越した哲学者であり、小説家であり、そして経営者でもある多才な人物。
彼の本領は、若者顔負けの情熱で、白ワインを片手に深夜、何時間でも白熱した議論を繰り広げられる熱量と好奇心のもと、深い哲学の知識と広い視野から現代社会の先行きを見通し、時代を前に進めるコンセプトを創出し、発信する力にあると評されている。
読んだ本のタイトル
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
ひとは誤ったことを訂正しながら生きていく。
訂正する力
哲学の魅力を支える「時事」「理論」「実存」の三つの視点から、
現代日本で「誤る」こと、「訂正」することの意味を問い、
この国の自画像をアップデートする。
デビュー30周年を飾る集大成『訂正可能性の哲学』を実践する決定版!
聞き手・構成/辻田真佐憲 帯イラスト/ヨシタケシンスケ
保守とリベラルの対話、成熟した国のありかたや
老いの肯定、さらにはビジネスにおける組織論、
日本の思想や歴史理解にも役立つ、隠れた力を解き明かす。
それは過去との一貫性を主張しながら、実際には過去の解釈を変え、
現実に合わせて変化する力――過去と現在をつなげる力です。
持続する力であり、聞く力であり、記憶する力であり、
読み替える力であり、「正しさ」を変えていく力でもあります。
そして、分断とAIの時代にこそ、
ひとが固有の「生」を肯定的に生きるために必要な力でもあるのです。
感想
本書は、現代日本が直面するさまざまな問題に対して、「訂正する力」の重要性を説く一冊である。
著者は、過去を正しく再解釈し、現在の状況に合わせて柔軟に対応することの大切さを力説している。
これは、個人のレベルだけでなく、社会全体においても同様で、硬直した思考を改め、常に更新し続けることが求められている。
まず日本が停滞している現状を詳しく解説し、その原因として、過去の間違いを認めて訂正することに対する抵抗感があると指摘する。
そのためには、過去を適切に理解し、現在に生かすための「訂正する力」を身につけることが不可欠であると説く。
保守とリベラルの対話を通じて、多様な意見を取り入れながら社会を成熟させる方法を探る。
さらに、ビジネスの世界における組織論や、老いを肯定的に捉える視点も提供し、日本の文化や歴史理解に新たな光を当てる。
特に、現代社会において分断が進む中で、「訂正する力」が如何にして個人の生活や社会全体に役立つのかを、具体的な例を挙げて説明する。
例えば、古い価値観に基づく政策や慣習を見直し、現実に即したものに更新することが、よりよい社会を作るための一歩とされる。
また、AIやデジタル技術の進化がもたらす変化に対応するためにも、「訂正する力」は重要である。
テクノロジーがもたらす速やかな変化に、人間がどう適応し、それをどう社会に反映させるかが、今後の大きな課題とされる。
書籍の結末では、個々人が「訂正する力」を身につけることが、より良い未来への鍵であると結論づける。
それによって、人々は過去の過ちを乗り越え、より柔軟で、開かれた社会を構築できるとされる。
この力を持つことで、私たちは困難な時代においても、確固たる希望を持ち続けることができるのである。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
その他ノンフィクション

備忘録
はじめに
日本はさまざまな分野で停滞しており、大胆な改革が求められているが、実際には進展が見られない。
この状況を打開するためには、大規模なリセットではなく、個々人が現状を少しずつ変える地道な努力が必要である。
また、過去を再解釈し現在に生かす柔軟な思想も重要である。
日本人は過去の間違いを認め、訂正することに抵抗があるが、これを改め、訂正する力を取り戻すことが求められている。
本書では、そのための具体的な指針を提供し、過ちを正しながら成熟していくプロセスを解説している。
第 1章 なぜ「訂正する力」は必要か
ヨーロッパの人々は状況に応じてルールや政策を頻繁に変更することに長けており、これが彼らの「訂正する力」の表れである。
これに対し、日本も外来文化を受け入れつつ本質的な部分は変わらず、保守的でありながら表面上は開かれているかのように振る舞う。
しかし、現代の日本社会では「訂正する力」が失われ、固定された「空気」によって新しい意見や変化が阻害されている。
この問題を解決するためには、相手の意見に耳を傾け、訂正や議論を通じて意見を変えることが重要であり、その土壌を育てることが日本に求められている。
権力批判側にも「訂正しない勢力」が存在し、特に左派リベラル勢力が柔軟な対応を示していないことが指摘されている。
例えば、日本共産党は「ぶれない政党」と自称するが、現代の変化する社会環境においては、そのような姿勢が問題とされる。
また、憲法の第9条についての議論は、専門家による神学的な議論が国民には理解しづらく、憲法の精神を守るためには条文を現実の変化に応じて修正すべきとされる。
しかし、左派は条文の変更を許容せず、憲法を固守することによって事態を膠着させている。
このため、訂正する力が発揮されず、社会の進展が阻害されていると論じられている。
保守派も訂正する力が欠如していると批判されている。
保守派は日本を守るという名のもとに、移民や外国人労働者の問題などに対して冷淡であり、人権侵害が発生しても適切な対応を取らない例がある。
日本の「技能実習制度」の問題や、外国籍の人々が長期間日本で生活しても住民自治に参加できない現状など、日本社会の実情に合わせた政策の変更が求められている。
また、日本文化の伝統を継承しつつ、必要な変更を受け入れる柔軟性が保守派には必要であるとされる。
このように、保守派もリベラル派と同様に訂正する力を発揮し、時代の変化に適応する必要があると主張されている。
ポリティカル・コレクトネスと訂正する力について述べている。
ポリティカル・コレクトネスは、過去の価値観が現在では適切でない場合にそれを訂正しようとする反省の精神を意味する。
現在の正しさが将来間違いになる可能性があるため、常に距離を持って考えることが重要である。
訂正する力は、過去を記憶し、必要に応じて謝罪する力であり、単なる過去の修正ではない。
小山田圭吾さんの騒動が例として挙げられており、この騒動は日本社会の問題点を見逃してしまった例である。
訂正する力は記憶する力でもあると強調されている。
また、訂正する力は聞く力、持続する力、老いる力、記憶する力として定義され、これらの力が現代日本で阻まれていることが課題とされている。
訂正する力は、対象となるコンテンツの背景や文脈を含む「外部」の存在が必要であると述べている。
この外部は、歴史や身体性、付加情報として現れることがあり、コンテンツ自体はその外部とともに理解されるべきである。
現代社会では、この外部がしばしば見過ごされがちであり、文化的な遺産や豊かなコンテンツを適切に利用できないことが指摘されている。
特にインターネットは情報を時間や文脈から切り離し、読みが単純化することが問題視されている。
現代はコストパフォーマンスや効率を重視する時代であり、人間関係やコンテンツ消費においても最低限の情報で満足する傾向が強まっている。
しかし、その結果、コンテンツ本来の力を発揮することができず、訂正する力が弱まっている。
音楽や読書などの体験は単なるデータ提供に留まらず、それに付随する豊かな体験が重要であると強調されている。
訂正する力には過去との一貫性を主張しながらも現実に合わせて適応する能力が含まれ、それには聞く力や記憶する力、読み替える力が必要。
日本は訂正する力を活用しきれていないとし、その原因としてリベラル派と保守派の双方に存在する「訂正しない勢力」が議論の硬直化や社会の停滞を招いていると分析している。
しかし、新しい伝達手段の登場が訂正する力を強める可能性を秘めているとも述べられている。
第 2章 「じつは……だった」のダイナミズム
訂正は日常生活において自然に行われている行為であり、意識的な活動へとその価値を活かすことが提案される。
訂正の本質は「メタ意識」にあり、意図せず行った行動に対して疑問を感じたり、距離を感じたりしたときに生じる。
無意識の行動がうまくいかなくなったときに、意識的な思考が始まり、行動の訂正が必要とされる。
訂正する力は生きることの基本であり、人間はその能力を発達させたため意識を持つようになったとされている。
また、訂正する力は試行錯誤の重要性を含み、環境の変化に合わせて行動を調整することが重要である。
この力は、すべての対話の基本であり、ロシアの文学理論家ミハイル・バフチンによれば、対話は絶えず反論が可能である状況を指すとされています。
言語哲学者ソール・クリプキの議論は、どんなルールを設定してもそれに対する異議申し立てが可能であるという考え方を示しています。
これは、人間のコミュニケーションが本質的に開放的であり、社会において変わった行動やルールの解釈をする人間が必ず存在するという性質を持つことを示しています。
訂正する力は、民主主義の本質的な部分と密接に関連しており、社会の存続と発展のためには、ルールが破られたときに柔軟に対処する能力が求められる。
民主主義はルールを共に作るプロセスであり、そのプロセスにおいて訂正する力が不可欠であるとされている。
2022年7月の安倍元首相銃撃事件に関する考察が展開されている。
事件に対して同情や共感を持つことは否定され、そのようなテロ行為を許容してはならないとされている。
ただし、テロが発生した後の社会の変化には対応する必要があり、訂正する力が必要であると主張されている。
社会にはルールの変更や運用の訂正を含む適切な対応が求められる。
この点で、日本の世論は極端な反応が目立ち、リベラル派と保守派双方が単純化された見解を示していると批判されている。
また、ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論に言及し、社会的な事象やアイデンティティの理解において、ルールが変わる現象を説明している。
この理論は、固有名についても適用されており、新たな発見や変化に対応するための訂正する力の重要性が強調されている。
人間と人間社会を理解する上で「じつは……だった」という発見の重要性を説いている。
これは、予期せぬ発見によって過去の経験の意味が大きく変わる現象を指す。
特に人工知能(AI)に関連したチューリングテストの議論を通じて、人間とAIの区別が曖昧になる状況で、人間独自の「じつは……だった」の感覚がどう影響するかが問われている。
例えば、AIとの対話が人間と変わらないと感じた場合でも、その相手がAIだったと後で知った時のショックや裏切り感は、AIが人間として完全に機能するかどうかの評価に影響する。
これは、人間が過去の認識を再評価し、それに基づいて意味や感情を修正する能力を持っていることを示している。
この能力は、生きるうえでの訂正する力として非常に重要である。
また、文系学問の重要性についても触れており、文系は「じつは……だった」という論理を基にして進むことが多いと説明している。
文系の知識は、過去の理論や概念を現代の文脈に再解釈し、新たな視角から理解を深めることに重点を置いている。
これに対して、理系はより具体的な外部の世界との一致を求めることが多い。
このように、文系的なアプローチは過去の再解釈や言葉の修正を通じて、新しい知識や理解を生み出す手段となっている。
この再解釈のプロセスは、社会全体にとっても有益であり、過去と現在を繋ぐために不可欠である。
本文は、自然科学と人文学の間に存在する反証可能性と訂正可能性の違いについて説明している。
反証可能性は、理論が間違っていることを証明できる可能性があり、その理論が暫定的に正しいとされるカール・ポパーの概念である。
これに対して、人文学では理論が過去に棄てられたとしても、再評価される可能性があり、学問としての訂正が可能である。
文系と理系の学問の違いをさらに深める「サンクコスト」の概念が紹介されており、経済的な合理性からはサンクコストは無視すべきだが、人文学では過去の知識や理論も未来を豊かにするために重要とされる。
これは、図書館が現在必要な本だけでなく、幅広い過去の書籍を保存していることからも示される。
最後に、シンギュラリティという概念とその影響についても触れられている。
技術的な発展により、人工知能が人間の知能を超える可能性はあるが、それが人間の本質的な生き方や社会の根本を変えることはないとされる。人間の問題は技術が進歩しても変わらず残ると結論づけられている。
この点で、人文学の訂正する力は、未来においても重要な役割を果たし続けるとされている。
人工知能が進化し、高品質なコンテンツを生み出す社会において、「人間とは何か」という問いが重要になると述べられている。
特に、作品を生成するAI技術が進んでも、人間がどう感じるかが重要であり、作品の「作家性」が大きな価値を持つと指摘されている。
子供の絵を例に、作品そのものの技術的価値ではなく、誰が作ったかという「作家性」に価値が見出される場面があり、これは人間がコンテンツを消費する際に、内容だけでなく作品背後の情報も重視するためである。
AIが良質なコンテンツを生成しても、それが誰によって作られたかが不明である限り、市場での価値は限定される可能性がある。
これに対して、人間が生成したコンテンツは「作家性」という付加価値があり、これがコンテンツの市場価値を形成する要因となる。
この文脈で、人間の「訂正する力」が重要な役割を果たす。
訂正する力は、新しい情報によって過去の定義や認識を更新する力であり、人文学においてはこの力が中核を成す。
自然科学が反証可能性に基づく一方で、人文学は訂正可能性に重きを置いている。
この力は、人間の感じ方や価値観を形成する基盤であり、AIがどれだけ進化しても、人間独自のこの力をAIは持ち得ないため、人文学や作家性の理解は今後も重要であると結論づけられている。
第 3章 親密な公共圏をつくる
文書では、「時事」と「理論」と「実存」という哲学の三つの要素について議論されており、これらがバランス良く組み合わさっている場合、思想が強力な力を持つとされている。
しかし、現代ではこれらを完全に兼ね備えた言葉は少なく、時事と理論、時事と実存、理論と実存の組み合わせは存在するものの、三つ全てが重なる例はほとんど見られないと指摘されている。
また、筆者は「ゲンロン」という会社を経営しており、会社運営を通じて「訂正する力」の重要性を学んだと述べている。
訂正する力とは、変化に適応し続ける力のことで、会社の運営だけでなく、個人の生き方やアイデンティティにも関わる概念である。
特に、社長交代や新しい事業モデルの導入など、大きな変更を経験することで、その重要性を実感したとされる。
訂正する力は、過去に対する新たな視点を提供し、過去の行動や成果を再評価する機会を提供する。これにより、個人や組織は成長し続けることができる。
また、この力は日常生活での「余剰の情報」を通じて他者との関係性においても有効であると説明されている。
専門家としての自身のイメージを訂正し続けたいという筆者の願望が述べられている。
専門家がマスコミに出演する際、一般的にはその専門性だけが求められ、「余剰の情報」には興味が持たれないため、彼はそれを退屈だと感じている。
さらに、訂正される可能性を失ってしまうことをリスクとして捉えており、その結果、社会状況の変化に対応できなくなると指摘している。
彼は訂正する力の重要性を説き、この力を持つことで「交換不可能な存在」になると説明している。
例えば、特定の専門家が親ロシアとして批判されたが、彼の信頼性が高いために活動を続けているという。
この信頼は、専門家が単に専門的な知識だけでなく、その人物自身に関する「余剰の情報」を提供することで築かれる。
また、筆者は訂正する人々を集めることの重要性についても語っている。
人々は経年により変化するが、その変化に対応し、自分を再発見するためには訂正する力が不可欠であると主張している。
これにより、人々は役割に縛られずに生きることができ、人間関係が持続可能になる。
訂正する力は、個人が社会的な役割やイデオロギーに縛られることなく、柔軟に自己を再定義し続けることを可能にする。
文書では、ルソーがジュネーブの伝統的な「セルクル」と呼ばれる小さなコミュニティを保護するために、演劇の導入に反対したことが説明されている。
彼は、演劇が人々を虚飾に染め、既存の地域コミュニティを破壊すると懸念していた。
これは現代のインターネットやソーシャルメディアが地元の親密な公共空間を侵食している現象と同じであると筆者は指摘している。
さらに、筆者は、ある集団が閉鎖的か開放的かという二分法に対して批判的であり、人々が固有名で互いを認識し、訂正の力が働くかどうかがより重要であると主張している。
この訂正の力とは、人々が互いの本質を理解し、予想外の行動や発言を受け入れる力である。
この視点から、筆者は組織の重要性と、その組織がどのように機能すべきかについても言及している。
組織は、単に人々がお互いを理解する場ではなく、恒常的に「おまえはおれを理解していない」という討論を交わし続ける場であるべきだと強調している。
このような対話の空間を通じて、民主主義社会は多様な意見が飛び交う「うるさい」社会として機能することが示されている。
組織やコミュニティ内での祭りの役割に焦点を当てている。
日本の伝統的な祭りが個人とコミュニティを結びつけるアイデンティティの確認の手段として発展してきたとされている。
この点は、訂正する力が発揮される場としての祭りを通じて、共同体の集団的記憶を再発見し訂正する過程が行われることにつながる。
また、例として挙げられた『名探偵コナン』の劇場版は、年間行事としての機能を果たしており、観客が映画を見る行為が祭りに参加する行為に等しいとされている。
さらに、IT業界におけるエンジニアの働き方が議論されている。
彼らは遊びと仕事の区別なく活動し、その柔軟な態度が新しい技術やサービスの創出につながっている。
この動きは、ウィトゲンシュタインの言語ゲーム理論に照らして考えられ、遊びが仕事に変わるダイナミズムが強調されている。
全体として、この文書は、祭りや集まりが個人や集団にとってどのように意義深いものであるか、そしてそれがどのようにして社会的、文化的アイデンティティを形成し維持するかについての考察を示している。
第 4章 「喧騒のある国」を取り戻す
訂正する力を用いて日本思想の批判的な継承を模索している。
丸山眞男が提案した「つぎつぎになりゆくいきほひ」という概念を中心に、日本特有の思想的流れを説明している。
日本の思想や政治において、物事がなんとなく自然に生まれてつながっていく流れが存在するとされている。
この考え方は、ヨーロッパ哲学、特にマルティン・ハイデガーの思想との類似性を通じて説明されており、京都学派の哲学者たちが日本的な要素を見出し、日本が主体的に思想を形成すべきだと主張したことが触れられている。
しかし、このようなアプローチが国家主義と結びつくリスクを孕んでいるとも指摘されている。
また、文書は過去を保守するという行為が必ずしも過去を守ることにつながらず、実際には伝統を変えることにもなり得ると論じている。
この「訂正する」という概念を用いることで、伝統的な自己肯定や過去の全否定を超えた新しいアプローチが可能になると提案されている。
さらに、日本の哲学が外国からの哲学の批判として機能する一方で、日本内部での自己肯定には問題があるとされ、伝統と現代のバランスを取る必要性が強調されている。
その中で、異なる文化的要素を組み合わせることによって「新しい日本」を創出しようとする試みが、ポストモダン的なアプローチとして評価されている。
日本の保守思想をリベラル的な視点から再解釈し、日本の近世思想をヨーロッパの思想展開と類似させることに焦点を当てている。
丸山眞男の『日本政治思想史研究』を例に挙げ、その内容がヨーロッパ哲学に影響を受けたと述べている。
また、この本が近世と近代の日本思想をつなぐ重要な作品であると評価している。
さらに、訂正する力という概念を用いて、過去の解釈を変えることで新たな物語を創造することが可能であると論じている。
これにより、現実逃避ではなく、深刻な現実に直面するための必要な幻想を創出することができるとしている。
この文書は、日本の伝統に普遍的な価値を見出し、リベラルと保守の語彙を組み合わせることで豊かな思想が生まれる可能性を示唆している。
また、保守的な思想をリベラル的に再解釈することの有効性を強調し、それが現代の議論にも重要な意義を持つと主張している。
日本の民主主義に関する誤解とその歴史的背景、そして現代の政治的な議論について述べている。
著者は、日本に古来から民主主義が存在していたとする保守派の主張を批判している。
五箇条の御誓文や大正デモクラシーなど、過去の政治的文脈を民主主義と結びつける試みは、民主主義の本質的な意味とは一致しないと指摘している。
民主主義とは、人民が国を統治することであり、この概念は戦後の改革を通じて日本で広がったものである。
また、著者は日本人が民主主義の怖さに直面していないとも主張している。
民主主義がポピュリズムや全体主義に直結する可能性を指摘し、ナチスドイツの法学者カール・シュミットの例を引用している。
さらに、日本がフランス革命やロシア革命のような大規模な社会変革を経験していないため、民主主義の理解が不十分であると論じている。
このような背景から、日本の政治的議論が非常に抽象的であると批判しており、平和主義や護憲運動が硬直化していると指摘している。
著者は、戦後日本の平和主義を「訂正」すること、つまり内実を変えつつ受け継いでいくことが必要だと主張している。
日本の平和主義の新たな解釈として、文化と観光戦略を結びつける提案がなされている。
日本の文化的豊かさを平和の概念に結びつけ、新しい物語を構築することで、平和主義を再定義しようとしている。
また、アメリカの民主主義と喧騒の関連性を例に挙げ、日本における平和が政治から離れた活動によって実現されると論じている。
この視点は、平和を単なる戦争の欠如ではなく、政治的な対立が減少した状態として理解することを示唆している。
さらに、平和を文化的な多様性と独自の生活様式と関連付け、戦後日本の平和が政治の外側で豊かな文化的活動によって支えられていたと指摘している。
これを「訂正する力」と呼び、過去を変えながらも変えたと感じさせない、見えない政治による平和の実現を目指している。
このような日本の平和主義の再解釈は、政治と文化の新たな関係性を模索するものである。
ルソーが日本でなぜ人気があるのかを解析している。
ルソーの思想が日本で受け入れられた理由の一つは、自然と社会の対立を止揚する彼のアプローチにあるとされている。
彼は自然な状態での人間の生活を理想と見なし、しかし社会的な契約が必要であるとも説いた。
このような矛盾を抱えつつも、ルソーは「訂正する力」の重要性を追求した哲学者であり、日本の「作為を自然に見せる」という美学と共鳴している。
また、ルソーの「社会契約論」と恋愛小説「新エロイーズ」を同時に読むべきだと提案されている。
この両作品は、人間の行動を自然に見せつつも背後で作為が行われているというルソーの思想を体現している。
この複雑な関係性は、日本の文化的ダイナミズムと対応しており、ルソーの哲学が日本の近代に積極的に受け入れられた理由の一端を示していると論じられている。
あとがき
本書は、田真佐憲という近現代史研究家との対話によって構成されており、東浩紀に新たな視点から自己を語らせることに成功している。
本書は、東浩紀の過去の著作と異なり、新たな側面を描出しており、本人も自己が「訂正」されたと感じている。
対話形式による再構成により、田の構成案に基づいて、東が自らの言葉で全文を再話している。
本書は多様な話題を扱い、特に「訂正する力」を主題としているが、そのような本は現在の市場では一般的ではなく、読者が見えないと東は述べている。
しかし、東はこのような考えることの重要性を伝えるために書かれたと強調している。
本書の発表は、同じ価値観を共有する人々とのつながりを生み出す可能性を持っており、東はこの本が創造的な人々にとって響くことを期待している。
Share this content:
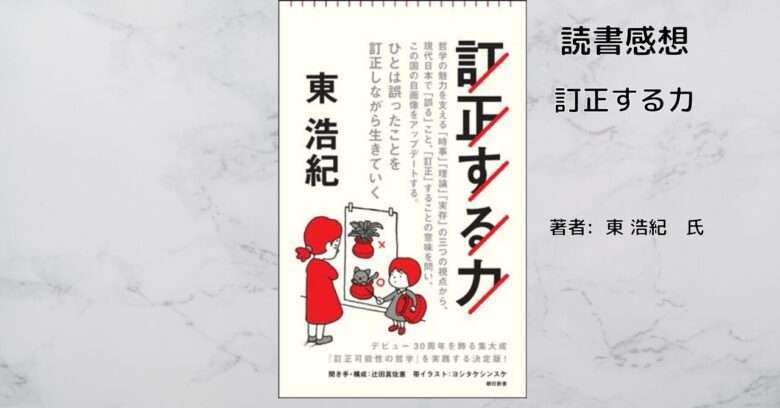

コメントを残す