- どんな本?
- 読んだ本のタイトル
- あらすじ・内容
- 感想
- 備忘録
- まえがき
本が読めなかったから、会社をやめました - 序章
労働と読書は両立しない? - 第一章
労働を煽る自己啓発書の誕生
明治時代 - 第二章
「教養」が隔てたサラリーマン階級と労働者階級
大正時代 - 第三章
戦前サラリーマンはなぜ「円本」を買ったのか?
昭和戦前・戦中 - 第四章
「ビジネスマン」に読まれたベストセラー
1950 ~ 60年代 - 第五章
司馬 太郎の文庫本を読むサラリーマン
1970年代 - 第六章
女たちのカルチャーセンターとミリオンセラ
1980年代 - 第七章
行動と経済の時代への転換点
1990年代 - 第八章
仕事がアイデンティティになる社会
2000年代 - 第九章
読書は人生の「ノイズ」なのか?
2010年代 - 最終章
「全身全霊」をやめませんか - あとがき
- まえがき
- 類似作品
- ノンフィクション
どんな本?
「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」は、書評家・批評家の三宅香帆 氏によって執筆された本。
この本は、明治時代から現代にかけての労働と読書の歴史を振り返り、日本人の読書観を明らかにしていた。
著者は自らも兼業での執筆活動を行っており、労働と読書のあり方の変遷を探求していた。
本書では、仕事と趣味が両立できないと感じる人々に向けて、日本の労働の問題点や読書のあり方について考察している。
本の内容は以下の章立てで構成されている:
1. まえがき: 本が読めなかったから、会社をやめました
2. 序章: 労働と読書は両立しない?
3. 第一章: 労働を煽る自己啓発書の誕生―明治時代
4. 第二章: 「教養」が隔てたサラリーマン階級と労働者階級―大正時代
5. 第三章: 戦前サラリーマンはなぜ「円本」を買ったのか?―昭和戦前・戦中
6. 第四章: 「ビジネスマン」に読まれたベストセラー―1950~60年代
7. 第五章: 司馬遼太郎の文庫本を読むサラリーマン―1970年代
8. 第六章: 女たちのカルチャーセンターとミリオンセラー―1980年代
9. 第七章: 行動と経済の時代への転換点―1990年代
10. 第八章: 仕事がアイデンティティになる社会―2000年代
11. 第九章: 読書は人生の「ノイズ」なのか?―2010年代
12. 最終章: 「全身全霊」をやめませんか
13. あとがき: 働きながら本を読むコツをお伝えします
三宅香帆は文芸評論家であり、多数の著作を持っている。
この本は、読書愛好者や労働者に向けた渾身の作品となっている。
なぜ働いていると本が読めなくなるのかについて、興味深い視点で探求されていた。
読んだ本のタイトル
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
【人類の永遠の悩みに挑む!】
なぜ働いていると本が読めなくなるのか
「大人になってから、読書を楽しめなくなった」「仕事に追われて、趣味が楽しめない」「疲れていると、スマホを見て時間をつぶしてしまう」……そのような悩みを抱えている人は少なくないのではないか。
「仕事と趣味が両立できない」という苦しみは、いかにして生まれたのか。
自らも兼業での執筆活動をおこなってきた著者が、労働と読書の歴史をひもとき、日本人の「仕事と読書」のあり方の変遷を辿る。
そこから明らかになる、日本の労働の問題点とは?
すべての本好き・趣味人に向けた渾身の作。
感想
本書は、現代の働く人々が読書を楽しむことの難しさをテーマにしたものである。
著者が社会人1年目の時、彼女は読書が大好きだったが、仕事の忙しさと疲れにより、ほとんど本を読む時間がなくなる。
キャッチーなフレーズにするためか、本を読まずにスマホを見てしまうと書いてあった。
でも、本筋は本が読めないといった状況に対する考察だった。
彼女はこの状況に疑問を感じ、会社を辞め、本を多く読み批評家としての道を歩む事となっていた。
そして、彼女の体験談がウェブサイトで連載され、多くの共感と反響を呼ぶ。
その過程で、労働と文化活動の両立の難しさを描きつつ、個人がどのようにバランスを取るべきか、社会がどのように支援すべきかについて問いかけていた。
本書では、明治時代から現代に至るまでの労働の歴史と、読書がどのように変わってきたかを掘り下げる。
読書は朗読(時代劇でやってた)が当たり前だとか、図書館が日露戦争以降とは知らなかった。
各時代の社会状況や文化的背景に基づいて、労働者がどのように読書と向き合ってきたかが詳細に分析されている。
円本、、
ウチのだと百科事典か?
アレは良い読み物だった。
俺はアレを読んでたな。
インターネットやスマートフォンが普及した現代においては、情報の取り方が大きく変わり、本を読む時間がさらに減少していると指摘する。
それがキャッチーなフレーズ「スマホでパズドラ」なんだな。
最終章では、「全身全霊をやめませんか」という問いかけを通じて、働き方やライフスタイルの見直しを提案。
著者は、半身(出力50%?)で仕事をし、もう半身で個人の生活や趣味を楽しむことが、より豊かな人生を送るための鍵であると説く。
分かるわ〜
自身も一生懸命働くのをやめて、読者をする時間を強引に取ってるもんな、、
仕事中でもスキあらば読むし。
読書をはじめとする文化活動が、個人の精神的な豊かさを育むために重要であるとし、それを実現するための社会的なサポートや制度改革の必要性を強調。
書籍は、働きながらでも読書を楽しむ具体的な方法を示し、忙しい現代人に向けた解決策を提案していた。
それにより、読者に自身のライフスタイルを見直すきっかけを提供し、個々の生活においてどのように時間を有効に使うかを考える機会を与える本であった。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
備忘録
まえがき
本が読めなかったから、会社をやめました
社会人1年目のある女性が自分が愛してやまない読書をほとんどできなくなった経験について述べたものである。
彼女は学生時代から本を愛読し、そのために就職もしたが、仕事の長時間と疲労により、読書の時間が極端に減少したことに気づく。
その結果、社会人としての生活に疑問を感じ、最終的に会社を辞めて批評家としての道を歩むようになる。
この変化は、彼女が書いたウェブサイトの連載記事が、多くの同じ悩みを持つ人々から反響を呼び、さまざまな声が集まったことを明らかにしている。
文書は、労働と文化活動との両立がいかに難しいかを問題提起し、労働と私生活のバランスをどう取るか、そしてそれがどのように社会に影響を与えるかについて考察している。
序章
労働と読書は両立しない?
社会人生活と読書の両立の難しさについて語った内容である。
主に、「花束みたいな恋をした」という映画を例に取り、労働が読書や他の文化的活動と相容れない現実を描写している。
映画は、恋人関係にある麦と絹のカップルが、麦の長時間労働により読書を含む共有の趣味が疎遠になる様子を通じて、労働とプライベートな趣味との間の矛盾を浮き彫りにする。
また、映画に対する反響が大きかったことから、多くの若者が同様の問題を抱えていることが示されている。
文書は、現代日本における労働と文化的生活のバランスを取る困難さを、映画の評価や人々の感想を通じて掘り下げている。
第一章
労働を煽る自己啓発書の誕生
明治時代
1
日本の労働が長時間化したのは明治時代からであり、この時期に「労働」という概念が広まった。
労働時間の増加は工業化の進展と密接に関連していた。同時に、この時代には読書のスタイルも大きく変わり、「黙読」という形式が生まれた。
活版印刷技術の導入により、個人が自由に読書を楽しむ文化が育った。また、明治時代には図書館文化が芽生え、特に学生層を中心に読書が普及した。
この文書では、それまでの集団での朗読が一般的だった読書が、個人が自分のペースで読むスタイルへと変化した点を強調している。
2
日本初の男性向け自己啓発書である『西国立志編』が注目されていた。
この書籍はイギリスのサミュエル・スマイルズの著作『Self-Help』を中村正直が翻訳したもので、明治初期に大ベストセラーとなり、労働者階級の青年たちに努力と自己助力を通じた成功を勧める内容であった。
また、歌「仰げば尊し」の背景として、明治時代の教育的価値観が反映されている点が触れられており、この歌が作られたのは「立身出世主義の時代」が始まった頃であるとされる。
この歌は学校を卒業した後の若者に立身出世を目指すよう促す内容であり、それが当時の社会の価値観として広く受け入れられていたことを示している。
3
明治時代に「修養」という概念が導入され、「自己啓発書」のジャンルが確立した。
特に『西国立志編』は、自助努力と修養を重視し、男性中心の社会での成功を描いた。この本は、勤勉や努力といった概念を「修養」と訳し、自己啓発の思想を広めた。
一方で、修養をテーマにした雑誌がブームとなり、『実業之日本』や『成功』といった雑誌が創刊された。
これらの雑誌は、労働者階級の男性を主な読者とし、成功の秘訣を広めた。
さらに、欧米の自己啓発書の翻訳が多数売れ、ニューソート思想に基づいたポジティブ思考が強調された。
この時代の文脈は、労働と階級格差の問題を背景にしており、成功を目指す労働者階級とインテリ層との間には明確な階級格差が存在した。
夏目漱石の『門』においても、自己啓発雑誌「成功」への言及があり、これがエリート層にとって遠い存在であったことが示されている。
このように、明治時代から自己啓発書は階級格差と密接に関連しており、その流れは現代に至るまで続いている。
第二章
「教養」が隔てたサラリーマン階級と労働者階級
大正時代
1
大正時代における社会不安と宗教、内省のブームについて述べられている。
この時代、効率重視の教養が問題視され、教養を提供する雑誌「中央公論」が流行していた。
インターネット時代以前から効率を求める教養の流れがあったが、大正時代にはこれが顕著だった。
また、日露戦争後の国力向上のために全国で図書館が増設され、読書人口が爆発的に増加した。
出版界では再販制度や委託制度が導入され、読書文化が大きく発展。特に大学生などの高等教育を受ける層の増加がこの傾向を強めた。
しかし、大正時代のベストセラーには社会不安への内省を反映した暗い内容の作品が多く見られた。
これは当時の社会情勢が影響しており、読者たちの間で「親鸞ブーム」などの宗教ブームや、社会主義関連の書籍が人気を博した背景には、深刻な社会不安があった。
この時代の出版物は、社会不安を背景に、救いを求めるための宗教や社会主義に関連するテーマが多く採り上げられていた。大正デモクラシーの流れと共に、政治や社会問題に関心を寄せる動きも見られ、社会主義への関心も高まっていた。
2
大正時代に「サラリーマン」という新中間層が誕生した。河合譲治のようなキャラクターが登場する谷崎潤一郎の『痴人の愛』では、サラリーマンとしての生活が描かれている。河合は月給百五十円の技師として働いており、質素だが自由な生活を送っていた。しかし、この時代のサラリーマンは社会的地位や給料の低さ、長時間労働などの問題に直面していた。
大正後期から昭和初期にかけて「サラリーマン」という言葉が広まり、新中間階級として社会に定着した。彼らは教育を受けたが、企業に勤めることで身分から解放され、新たな労働階級としてのアイデンティティを形成していった。
一方で、大正時代には物価高騰や不景気に苦しむサラリーマンが多く、彼らの生活は困難を極めた。サラリーマンの苦労を風刺した漫画が当時から人気を博し、サラリーマンが直面する問題が広く認識されるようになった。『痴人の愛』の主人公譲治は、この新しいサラリーマン像の典型であり、彼の日常と心理が当時のサラリーマンの現実を反映していた。
3
大正時代に「教養」と「修養」は、それぞれ異なる社会階層で異なる意味を持つようになった。労働者階級は自己鍛錬としての「修養」を追求し、一方でエリート階級は「教養」を身につけることで人格を磨くことを重要視した。この時代のエリートたちは、新渡戸稲造の影響を受け、「知識を身につける教養」を通じて人格を磨くことが重要だと考えるようになった。
明治時代の労働者階級は、教育を通じて自己を向上させるために「修養」を追求していたが、大正時代に入ると、都市部と農村部の両方で労働者階級にも「修養」が根付いた。都市部の工場労働者や農村部の青年団は、自己鍛錬を通じて社会の一員として認められることを目指した。
大正時代には「教養」がエリート文化として定着し、エリート学生や一部のサラリーマン層に広まった。この層は「中央公論」などの総合雑誌を読むことで、エリートとしてのアイデンティティを確立しようとした。当時のサラリーマン層は、教養を買うことによって自己の見栄えを良くし、社会的地位を高める手段として教養を利用した。
教養と修養の分離は、大正時代を通じて明確になり、戦後もこの分離は続いた。この過程で、教養はしばしば労働者階級との差別化の手段として用いられ、新中間層としてのサラリーマンは、教養を身につけることで自己の社会的地位を高める試みを行った。この時代の教養と修養の動向は、日本の近代化とともに発展し、それぞれの階層で異なる役割を果たしていた。
第三章
戦前サラリーマンはなぜ「円本」を買ったのか?
昭和戦前・戦中
1
大正末期から昭和初期にかけて、関東大震災と経済不況の影響を受けた日本の出版業界は苦境に立たされていた。その中で、「円本」という安価な書籍が登場し、日本の読書文化に革命をもたらした。改造社が発行した『現代日本文学全集』は、その価格が1冊1円という破格で、全巻予約必須の販売方式であった。この全集の予約者は最終的に40万~50万人に達し、大成功を収めた。
この成功は他の出版社にも影響を与え、さまざまな円本全集が刊行された。円本の成功の背後には、価格の安さだけでなく、書籍がインテリアとしての美観も提供していたことがある。特に新しい中流階級の家庭であるサラリーマン層は、読書を教養としてのステータスシンボルと見なし、円本全集を購入していた。
円本ブームは、教養を象徴する文化として、また安価で手に入れやすい全集として、当時のサラリーマンや新中間層に広く受け入れられた。その結果、多くの人々が教養を身につける手段として読書に興味を持ち、円本がその需要を満たす存在となったのである。
2
大正末期から昭和初期にかけて、円本は新中間層に大きな影響を与え、彼らにとってのある種のファッションアイテムとして機能した。これは出版社による支払い制度の工夫と広告戦略が功を奏していた結果である。関東大震災後の困難な状況の中、円本は「安くて買いやすい全集」として市場に出され、多くの人々に受け入れられた。
円本はその装幀の美しさもあって、インテリアとしても価値があるとされ、新中間層の書斎の一部となった。出版社は、この全集が「とにかくこれだけ集めればOK」という形で教養が身につくかのように消費者に提供した。円本は「教養に良さげな本を簡単に手に入れたい」という需要に応えたが、実際には積読されることも多かった。
しかし、農村部でも読まれていたとされ、多くの場合、古本として広がりを見せた。都市部のサラリーマン層によって購入された後、価格が下がった古本として農民層などに渡り、より広い層の人々が読書を楽しむ機会を得た。これにより、農村部で文学に触れる読者が増え、長期間にわたり多くの人々に読まれ続けた。
3
戦前の日本において、サラリーマンは映画や演劇などの受動的な娯楽にふけっていたが、読書は必ずしも広く受け入れられた趣味ではなかった。それは主に教養を必要とするエリート階層に限られていたとされる。しかし、大衆向け雑誌やエンターテイメント小説の普及により、読書は次第に広い層に受け入れられるようになり、特に大正時代末期から昭和初期にかけての大衆小説の登場が読書の風景を変えた。
戦前のサラリーマンは、週休の導入や郊外住宅地の発展により、休日や通勤時間に読書を楽しむ機会が増えた。特に電車の中や自宅での読書が一般的であった。また、新聞や雑誌に連載される小説は、エンタメとして受け入れられ、多くの人々に読まれることとなった。これにより、雑誌や新聞に掲載された小説が書籍化されるとベストセラーとなる流れが確立された。
しかし、戦時中になると、本を読む環境は大きく制限された。それでも初期には、海外文学の翻訳書などがベストセラーになるなど、読書への関心は完全には失われていなかった。戦時中は英語が禁じられるなど、出版環境が厳しくなる中でも、読書はある程度の層に支持されていた。戦後になると、戦前からの著名な作家たちによる活動が再び活発になり、日本の出版界は復興の道を歩み始めた。
第四章
「ビジネスマン」に読まれたベストセラー
1950 ~ 60年代
1
1950年代の日本では、戦後のサラリーマンや労働者階級が新たな娯楽に興じていた。特にギャンブルが広まり、パチンコや競輪などが流行した。戦前の囲碁などの伝統的な遊びは減少し、より身近な娯楽へと移行していった。この時代、労働者階級にも教養の概念が広がり始め、教養は階級上昇を目指す手段とされた。特に定時制高校に通う青年たちは、教養を求めていた。
また、雑誌が教養や人生訓を語る場となり、農村部の青年や女性が自身の内面を表現する手段として用いられた。出版社は紙の高騰に直面し、全集や文庫本の普及を図ることで対応した。これらの全集は新しい家庭のインテリアとしても人気を博し、多くの本が販売された。さらに、1950年代はエンターテインメントが多様化し、ラジオやテレビ放送の始まりとともに、余暇の過ごし方が大きく変化していった。
2
1950年代のサラリーマン向けエンターテインメントには、パチンコ、株、そして源氏鶏太の小説が含まれていた。当時、株は朝鮮戦争特需と新しい制度導入により、一般大衆にとって身近な存在となっていた。源氏鶏太は、サラリーマンやその家族を主人公に据えた小説を執筆し、彼の作品はサラリーマンにとって読みやすく人気を博していた。特に、彼の小説は雑誌で読み切り連載される形式が多く、前のあらすじを覚えていなくても楽しめる内容であったため、通勤電車内などで手軽に読むことができた。
また、当時のサラリーマンは非常に長い労働時間を有していたため、通勤電車内での読書が推奨されることが多かった。加藤周一は「通勤電車限定の読書」を提案し、通勤時間を利用して読書にあてるべきだと説いた。これは、当時のサラリーマンが抱える長時間労働と、余暇の少なさを背景に持つ。読書は教養を身につける手段として、また日々のストレスからの逃避手段としても機能していた。
3
1960年代、忙しいサラリーマンに本を買わせるためには、実用的で直接役立つ内容が求められた。この需要に応える形で『英語に強くなる本』や『記憶術』などの新しいジャンルの新書が登場した。これらは岩波新書などの伝統的な教養新書とは異なり、カッパ・ブックスレーベルなどから発行され、具体的なスキル向上や実務に役立つ情報を提供した。タイトルも直接的で理解しやすいものが選ばれ、広告戦略も具体的な利益を訴求するものであった。
これらの新書は、従来のインテリ層に加えて、新たな読者層を開拓し、労働者階級や時間がないサラリーマンにも読書が身近で役に立つものとして認識されるようになった。さらに、源氏鶏太のような作家がサラリーマン小説を提供することで、読書は大衆にとってアクセスしやすい娯楽となり、読書文化が階層を超えて広がるきっかけとなった。この流れは、ビジネスや自己啓発に関する書籍の需要が高まる背景を形成し、最終的には書籍が多様な職業や階級の人々にとって有用なリソースとなった。
第五章
司馬 太郎の文庫本を読むサラリーマン
1970年代
1
1970年代の日本のサラリーマンたちに『坂の上の雲』が読まれた理由は、その時代が明治時代の立身出世主義と相似していたためである。明治時代は自己啓発と立身出世の機会が広がった時期で、『坂の上の雲』はこの時代を背景にしている。本書は明治維新から日露戦争へと進む日本を描いており、3人の男性主人公が国のために努力し成功する物語が展開されている。
1970年代は、経済成長が急速に進む中で、サラリーマン層が増加し、彼らにとって読書が教養として、または娯楽としての価値を持ち始めた。司馬太郎の作品は、特にビジネスマン層に人気があり、その教養的価値が求められた。司馬の作品には、歴史を通じて人格を磨くというテーマが含まれており、読者は自己改善の手段としてこれを読んだ。
司馬太郎は教養小説の作家として知られ、その作品は歴史知識の提供だけでなく、当時の乱世を生き抜くヒーロー像に憧れる心理にも訴えた。『坂の上の雲』は8巻に及ぶ長大な作品であるが、その長さにもかかわらず、教養としての価値とともに、人々がその物語に引き込まれた理由である。
2
1970年代、テレビの普及により映画産業の存在感が減少し、テレビドラマが主要な娯楽となっていた。この時代には、『太陽にほえろ!』や『必殺仕掛人』などのドラマが人気を博し、松本清張や五木寛之の小説がドラマ化された。これにより、「テレセラー」という言葉が生まれ、「テレビによって売れる本」という現象が確立された。特に、大河ドラマの成功は歴史小説の販売を大きく促進し、例えば海音寺潮五郎の『天と地と』は、ドラマ放送中に廉価版が発売され、合計で150万部を売り上げるベストセラーとなった。しかし、この現象に対して著者自身は、「テレビが栄えて文学がおとろえる」と述べ、引退宣言をするほどであった。
また、1970年代のサラリーマンにとって、土曜日の夜は週休1日制の中で唯一の休日前夜であり、多くはテレビ視聴で過ごすのが一般的だった。この文化は現代においても続いており、新しいメディアの出現が文学の影響力を脅かす懸念は、昭和から令和に至るまで変わらずに存在している。それにもかかわらず、テレビの登場が小説の影響力を弱めると危惧されながらも、歴史小説やエンタメ小説のジャンルではベストセラーを生み出すことに成功している。
3
1970年代は、文庫創刊ラッシュの時代であり、オイルショックの影響による紙不足が深刻であったにも関わらず、多くの出版社が文庫の創刊に踏み切った。この時期、通勤電車での読書が一般的な風景となり、司馬遼太郎の作品も文庫化されて広く受け入れられた。司馬の主要な長編は1960年代に単行本で刊行され、1970年代に文庫化されると、「竜馬がゆく」や「坂の上の雲」などがベストセラーとなった。
この時代の日本では、企業内での自己啓発が重視され始めた。オイルショック以前は労働力不足が問題であったが、1974年以降の経済減速では人員過剰となり、昇進のための評価が重要になった。この文化の中で、司馬の作品は日本のサラリーマンにとってある種のノスタルジーを提供していた。それは、1960年代の高度経済成長期への郷愁とも言えるもので、司馬作品が提供する「立身出世」の物語が、当時の社会状況にマッチしていた。
また、司馬は自身の作品が朝礼の訓示に使われることに対して批判的であったが、作品が文庫という形態でより広範な受容を見たことで、70年代という時代を象徴するものとなった。その時代のサラリーマンたちは、長い通勤時間を利用してこれらの長大な小説を読むことに耐え、司馬作品を通じて失われた時代への憧憬を感じていた。
第六章
女たちのカルチャーセンターとミリオンセラ
1980年代
1
1980年代は、出版業界がバブル景気の中で売り上げを伸ばした時代であった。この時期、俵万智の『サラダ記念日』などの作品が大ベストセラーとなり、若者たちの心を摑んだ。この時代の特徴は、出版物の売り上げが右肩上がりで、70年代の1兆円から90年代初頭には2兆円を超えるほどであった。一方で、長時間労働が増加し、平日の余暇時間は減少していたが、それでも読書文化は花開いていた。この矛盾した現象に対し、バブル時代の印象と読書の地味なイメージがずれているように思える疑問が浮かぶ。
2
1980年代に、サラリーマン向けの雑誌「BIG tomorrow」が創刊され、特に若い層からの支持を得た。この雑誌は、教養主義的な要素を排し、職場での処世術や女性にモテる術を中心に、即実用的なハウツー情報を提供していた。その人気の背景には、学歴よりもコミュニケーション能力が重視されるようになった社会の変化があった。この時代のサラリーマンは、教養よりも「コミュ力」が必要とされ、それに応じた内容の雑誌が求められたのである。この傾向は、学歴に関わらず出世を望むことができる新しい職場環境とも相まっていた。
3
1980年代、カルチャーセンターが人気を博し、多くの女性が教養を求める場として利用していた。これらのカルチャーセンターは、料理や芸術など多様な講座を提供しており、参加すること自体がステータスシンボルとされていた。カルチャーセンターは、特に教養を身につけたいと願う女性にとって、学歴コンプレックスを埋める場となっていた。
この時代のカルチャーセンターに対する社会的な視線は複雑であり、特に男性や一部の女性からは、主婦やOLが暇つぶしで通う場所として軽蔑されることもあった。しかし、同時に多くの女性にとっては、自己表現や自己啓発の場として非常に重要な意味を持っていた。
カルチャーセンターでの学びや教養の追求は、女性たちにとって新たな自己表現の機会を提供し、それが文化的な階級格差を超えるための手段となることも示唆されている。その結果、1980年代の女性は、これまで男性が支配していた文化や批評の世界へと進出し、新たな文学や教養の流れを生み出していた。
第七章
行動と経済の時代への転換点
1990年代
1
1990年代は、さくらももこが文学界で著名になり、多くの作品がベストセラーとなった時代である。さくらももこは『ちびまる子ちゃん』の作者として知られ、その作品は国民的アニメとなった。彼女のエッセイ『そういうふうにできている』では、出産というテーマを取り上げつつ、誰もが共感できる内容で展開している。このエッセイでは、さくらももこ独特のユーモアとリアルな人間描写が特徴で、彼女の作品が男女問わず多くの人々に受け入れられたことを示している。
さらに、1990年代は日本全体で内面や心理に対する関心が高まった時代でもあり、さまざまなメディアで心理テストや自己探求のコンテンツが流行した。この傾向は、心理学が大学で人気の学問となり、心理学的なアプローチが一般の人々にも広く受け入れられるようになったことからも見て取れる。心理学的な視点から自己を見つめ直す動きは、自己啓発の流行とも重なっている。
2
1995年に発表された春山茂雄の『脳内革命』は、ポジティブ思考によって健康や老化防止に寄与すると述べる自己啓発書で、非常に大きな成功を収めた。この書籍の特徴は、抽象的な心理学ではなく、具体的なイメージトレーニングやポジティブ思考を実践する方法を提案していた点にある。このアプローチは新しく、その後の出版界に「脳」ブームを巻き起こし、多くの自己啓発書に影響を与えた。
1990年代は、自己啓発書が行動重視の方向にシフトした時期であり、『脳内革命』はその先駆けとなった。この時代、多くの自己啓発書が翻訳され、ベストセラーになる一方で、日本の労働環境も大きく変化していた。終身雇用の減少や非正規雇用の増加など、労働市場の不安定化が進み、自己責任によるキャリア形成が強調されるようになった。
この背景のもとで、『脳内革命』のような自己啓発書が求められ、ポジティブ思考や自己変革の重要性が広く認識された。この流れは、1990年代の経済と社会の変動によってもたらされた新自由主義の影響を反映している。90年代の変化は、経済活動の個人化と、個人の行動や思考を変えることによって社会や経済の課題に対処しようとする動きが強まったことを示している。
3
本書は「働くことによって読書ができなくなる理由」について議論している。特に、1990年代以降の読書離れと自己啓発書の市場の伸びが注目されている。一方で、書籍購入額は減少しているが、自己啓発書の市場は拡大しており、この状況は反比例しているように見える。
自己啓発書は、「ノイズを除去する」という姿勢で、読者の行動変革を促している。具体的には、個人の私的空間を整理し、人生を好転させるために「聖化」することを提案している。これは、社会が忌まわしいものとして認識され、個人の私的空間のみが重要視されていることを示している。本来、部屋と人生の間に存在すべき社会が無視されており、自己啓発書のロジックは、個人が社会から孤立して自己管理に専念することを推奨している。
この自己啓発書がヒットする背景には、1990年代以降の労働環境の変化がある。戦後の高度経済成長期やバブル経済の崩壊後、日本は長期的な経済停滞に入り、個人は市場に適応することを強いられている。これにより、コントロールできる行動に焦点を当て、自分の人生を変えることが求められるようになった。
読書は、この環境下でノイズとなりうる。知らない情報を取り入れることは、市場に適合しようとする努力においては無用な干渉となる。自己啓発書の成功は、社会的なノイズを排除し、個人が自分自身を管理し、環境に適応する能力を高めることに寄与していると言える。
第八章
仕事がアイデンティティになる社会
2000年代
1
2000年代以降の日本社会が「仕事を通じて自己実現すること」を称賛している状況を議論している。
自己実現の概念が主に職業に関連付けられるようになった背景には、教育政策とメディアの影響がある。
特に2002年に始まったゆとり教育は、個々人の「生きる力」を重視し、子どもたちが早い段階で自分の興味に基づいたキャリアを選ぶことを奨励した。
この傾向は、村上龍の『13歳のハローワーク』というベストセラーによって象徴されている。
この本は、子どもたちが好きなことを職業に結びつけることを提案している。
しかし、この自己実現の追求が労働者にどのような影響を与えたかという問題が存在する。
新自由主義の流れの中で、教育やメディアは「好きなことを仕事にする」ことを理想として推進してきたが、実際には多くの若者がこの理想を実現できずに苦悩している。
労働市場の変化と結びつき、多くの若者が非安定な雇用状況に置かれ、経済的なリスクを背負うこととなった。
1990年代後半からのキャリア教育は、高校生に「夢を追いかける」ことを勧めたが、実際には多くの若者が低就職率の分野を選んでしまった。
このような状況は、個々人が仕事を通じて自己実現を図るという社会的期待に反して、労働によって個人の生活が圧迫されるというパラドックスを生み出している。
阿部真大はこの問題を「自己実現系ワーカホリック」と名付け、仕事による自己実現がもたらす問題を批判している。
これにより、労働そのものが個人の自己探求の場となっているが、実際には多くの人々が仕事のプレッシャーに追われ、余暇を楽しむ時間や資源がない状況にある。
これが、2000年代の日本の労働と自己実現の複雑な関係性を示している。
2
2000年代に入ると、インターネットの普及によるIT革命が進み、情報の形態とアクセス方法が大きく変化した。
この変化は「読書離れ」を加速させる一因となり、インターネットが提供する情報が優位に立つようになった。
特に『電車男』のような作品が示すように、インターネット上の掲示板やコミュニティが新たな情報源として機能し、従来の社会的ヒエラルキーや情報へのアクセス方法を変えた。
この情報の「転覆性」は、インターネットが平等に情報を提供し、利用者が匿名性を利用して自由に交流できる場として機能することを強調している。
インターネット情報の持つ「フラット性」は、すべての人に等しく情報へのアクセス機会を提供し、その結果、社会的階級や権威を超えたコミュニケーションが可能となった。
このように、インターネットは情報の民主化を促進し、従来の知識や権威を問い直す役割を果たしてきた。一方で、この情報アクセスの容易さが、従来の読書とは異なる新しい知識の形態を生み出している。
インターネットは「ノイズのない情報」を提供することで、ユーザーが求める情報のみを効率的に得られるようになっており、それが多くの人々に受け入れられる理由となっている。
3
2000年代には、昭和時代の一億総中流社会が崩壊し、バブル崩壊やリーマンショックといった景気後退が続き、若者の貧困が広がった。
この時期、階級を超えた、いわゆる「ノイズのない」情報や自己啓発書が求められるようになった。
過去や歴史を重視する教養よりも、現状に直接役立つ情報が重宝されたのである。
伊藤昌亮は、ひろゆき的知性が陰謀論や差別的感性に近いと批判しているが、それは知識の受け取り方が、「今」ここに即したものに限定されているからである。
知識を求める際に必要なのは文化資本であり、それがなければ外部の情報を得ることは難しい。しかし、インターネット上の情報は、「今」の情報を迅速に得ることができるため、「情報強者」となる。
情報の増加と読書の減少は、インターネットによる情報の変化を示している。
読書がもたらす知識には偶然性が含まれるのに対し、インターネットの情報はユーザーが求めるものを直接提供する。
そのため、インターネットは望む情報以外の「ノイズ」を除外する傾向がある。
これが、働いている人々が本を読む時間が減少している一因であり、インターネットが情報源として好まれる理由である。
2010年代に入ると、労働環境はさらに変化し、働き方改革が進んだ。
これは労働に関する意識の変化を示しており、仕事とは遊びやアルバイトとは異なる「一生の労働」であることを、多くの人が理解し始めている。この変化は、2000年代には見られなかった新しい「夢」の形成を示している可能性がある。
第九章
読書は人生の「ノイズ」なのか?
2010年代
1
2000年代半ばから、労働小説が注目を集め、多くの作品が労働問題をテーマにした。
ビジネス書『人生の勝算』や『多動力』などでは、行動を重視する姿勢が強調されており、これらは新自由主義的な価値観を反映している。
新自由主義は、個人の自己決定と自己責任を重んじ、市場の競争原理を基盤としている。
こうした社会では、自分の行動をコントロールすることが求められ、組織や共同体よりも個人の独立が強調される。
また、この時代の流れは、2010年代に入るとさらに加速し、労働小説が文学賞を受賞するなど、社会的な認知が広がった。
津村記久子の『ポトスライムの舟』や池井戸潤の『下町ロケット』、村田沙耶香の『コンビニ人間』など、労働を通じて個人の実存を問う作品が人々の共感を呼んだ。
この背景には、2015年に発生した電通過労自殺事件などが影響しており、これが「働き方改革」という概念の普及につながった。
働き方改革関連法の施行により、長時間労働に対する規制が強化され、より多様な働き方が推進されるようになった。
労働をテーマにした小説やドラマが人気を博す一方で、ビジネス書でも「行動重視」の流れが続いており、これらの作品は、市場に適応しようとする個人の姿勢を象徴している。
この時代の変化は、個人が自己実現を目指す現代の風潮を反映していると言えるだろう。
2
2010年代にスマートフォンの普及と共にSNSの使用が急増し、多くの人々が日常的にSNSを利用するようになった。
この変化は、読書量に影響を与えた可能性があるが、読書量が減少した主な理由としては「仕事や家庭が忙しくなった」という回答が最も多かった。
この事実は、「働いていると本が読めない」という現象を示している。
一方で、読書が娯楽から情報処理スキルを向上させるための手段として捉えられるようになっており、速読やビジネスに役立つ読書法などが人気を博している。
映画鑑賞も同様に、芸術鑑賞から情報収集という形で消費されるように変わってきている。
これらは、情報を効率的に取り入れようとする現代人の傾向を反映している。
「教養」とは、自分から離れたところにある知識に触れることであり、それは他者の文脈に触れることでもある。
たとえば、過去のポップカルチャーに精通していることが、採用面接での評価につながる場面もある。
これは、教養がビジネスシーンで役立つ具体的な例として挙げられる。
しかし、教養を速く手軽に伝える「ファスト教養」という概念も出現しており、これは新自由主義的思想の影響を受けている。
結局のところ、私たちは他者の文脈に触れながら生きることが必要であり、ノイズを完全に除去した情報だけで生きることは難しいとされている。
これは、教養を深め、多様な知識を得ることの重要性を示唆している。
3
2010年代後半から2020年代にかけて、「オタク」や「推し」という言葉が広まり、特定のアイドルや芸能人を熱心に応援する文化が注目された。この流れは、「推し、燃ゆ」という小説にも反映されている。
この小説は、アイドルを熱心に応援する女性の生活と内面を描いており、彼女にとっての「推し」は単なる趣味ではなく、人生の核となっている。
この小説は、趣味を通じて自己実現を追求する「シリアスレジャー」という概念を体現している。シリアスレジャーとは、趣味が生きがいとなり、日常生活の一部としてではなく、人生の中核を成すものとして捉えられる現象である。
主人公のあかりは、他者とは異なる生活パターンを送りながら、自己の存在を「推し」によって確立しようとする。
しかし、物語の中であかりは、「推し」だけに依存する生き方に限界を感じ、他者との関わりを通じて自己を見つめ直す過程を経る。
これは、人間が社会的な存在であるため、他者との関係性の中でしか自己を完全に理解し成長することができないという事実を浮き彫りにする。
この小説から、私たちは自己を取り巻く様々な「文脈」を理解し、それによって人生が豊かになることを学ぶ。
たとえそれが仕事や社会的な役割と直接関連しなくても、それぞれの人生において意味を成す様々な体験や関係性が存在するのだと示されている。
最終章
「全身全霊」をやめませんか
1
労働と読書の関連性に焦点を当てて、日本の労働環境と読書の歴史を概観し、これからの理想的な社会像について考察されている。
具体的には、「働きながら本を読める社会」の実現が提案されている。
明治から大正時代にかけて、日本の近代化の中で教養が重要視され、立身出世の手段として自己啓発的な書籍が普及した。
戦前から戦後にかけて、サラリーマンという新中産階級の登場により、教養を提供する書籍が大衆向けにも普及した。
高度経済成長期には、読書が娯楽として広く受け入れられ、多くのベストセラーが生まれた。
バブル崩壊後、労働環境の変化と情報社会の到来により、自己啓発書の人気が高まった。
この時期、忙しさから自己にとって不必要な知識を摂取する余裕が減少していった。
近代から現代にかけての労働と読書の変遷を検証することで、自己啓発とは対照的に、自分に必要な情報を効率的に取り入れる能力が重視されるようになり、それが長時間労働につながる社会的背景が浮かび上がる。
効率の良い労働と情報処理が求められる現代において、働きながらでも読書を楽しむための社会構造の変革が必要であると結論づけている。
「トータル・ワーク」という概念が紹介されている。
これは、生活のすべての側面が仕事に変容する社会を意味する言葉で、ヨゼフ・ピーパーによって提唱された。
マレシックは自身のバーンアウト経験を通じて、この概念がいかに現代社会に根付いているかを語っている。
また、現代日本におけるワーク・ライフ・バランスの取り組みが、真のバランスを提供しているかどうか疑問を投げかけている。
政府は「ワーク・ライフ・バランス憲章」を通じて、個人の時間を効果的に仕事と生活に割り当て、地域社会への貢献につながることを目指しているが、実際には個人の自由時間が政策的に活用されている現状が指摘されている。
これにより、労働と余暇の境界が曖昧になり、個人が全てを自己管理する圧力が増加している。
「トータル・ワーク」の社会では、個人は仕事だけでなく、家事や育児、さらには余暇活動にも全身全霊を注ぐことが求められがちである。
このような社会では、個人のメンタルヘルスや生活の質が脅かされるため、半身でのコミットメントを可能にする新しい社会構造の提案が必要である。
著者は、「半身社会」を提案しており、これは個人が仕事と生活のバランスを取りながら、読書などの文化的活動にも積極的に参加できる社会を意味する。
このような社会では、個人は自分自身と他者をケアする余裕を持つことができ、仕事だけではなく多様な生活を楽しむことができる。
この提案は、個人が全身で仕事にコミットする現代の要求から脱却し、より人間的で持続可能な生活様式を実現するためのものである。
それにより、個人は仕事だけでなく、文化や社会とのつながりを深めることができるだろう。
あとがき
著者は、働きながら本を読むコツを共有している。
コロナ禍による時間の余裕を活かし、読書スタイルを変えることで読書量を増やした経験がある。
効果的な読書法として、読書アカウントのフォローやiPadの利用、カフェでの読書習慣化、書店訪問、新しいジャンルへの挑戦、そして無理をしないことが挙げられている。
また、自身の職業生活とコロナ禍での体験が、書籍作成の動機になったことが述べられている。
著者は全身全霊での働き方を美化することに疑問を呈し、半身で働く社会の実現を提唱している。
彼女は、働き方を変えることで、読書を含む充実した生活が可能になると考えている。最後に、本書の完成に協力してくれた人々に感謝の意を表している。
類似作品
「若者の読書離れ」というウソ」

ノンフィクション

Share this content:
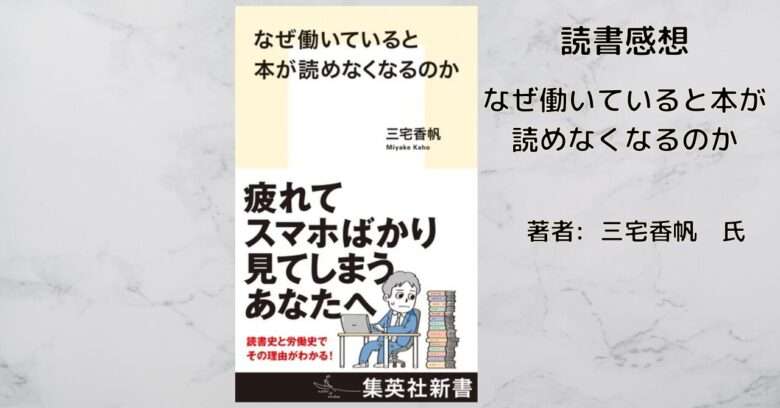

コメントを残す