どんな本?
『スポーツウォッシング なぜ<勇気と感動>は利用されるのか』は、スポーツの世界で行われている政治や企業の隠れた影響を明らかにする本である。
タイトルにある「スポーツウォッシング」とは、スポーツの良いイメージを使って、問題や矛盾を隠そうとする行為を指す。
2021年の東京オリンピックやその他の大きなスポーツイベントを例に、どのようにスポーツが政治的な道具として利用されているのかが語られる。
本書では、ナチスが1936年のベルリンオリンピックで行ったイメージ戦略や、カタールでのワールドカップ建設現場での労働問題など、歴史的な背景も含めて解説されている。
また、ジャーナリストや社会学者、アスリートのインタビューを通じて、スポーツがどのように社会的な洗濯行為の道具として使われているかが詳しく語られている。
この本は、スポーツファンだけでなく、現代社会におけるメディアや政治の影響に興味がある人にもたいへん有意義である。
スポーツの裏側を知り、より批判的な視点を持つことで、私たちが日常で接するスポーツの真実を理解する手助けとなるだろう。
読んだ本のタイトル
スポーツウォッシング なぜ<勇気と感動>は利用されるのか
著者:西村章 氏
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
「為政者に都合の悪い政治や社会の歪みをスポーツを利用して覆い隠す行為」として、2020東京オリンピックの頃から日本でも注目され始めたスポーツウォッシング。
スポーツはなぜ“悪事の洗濯”に利用されるのか。
その歴史やメカニズムをひもとき、識者への取材を通して考察したところ、スポーツに対する我々の認識が類型的で旧態依然としていることが原因の一端だと見えてきた。
洪水のように連日報じられるスポーツニュース。
我々は知らないうちに“洗濯”の渦の中に巻き込まれている!
「なぜスポーツに政治を持ち込むなと言われるのか」「なぜ日本のアスリートは声をあげないのか」「ナショナリズムとヘテロセクシャルを基本とした現代スポーツの旧さ」「スポーツと国家の関係」「スポーツと人権・差別・ジェンダー・平和の望ましいあり方」などを考える、日本初「スポーツウォッシング」をタイトルに冠した一冊。
はじめに
著者はスポーツウォッシングという現象に焦点を当て、その概念と社会的影響を解説した。日本ではこの問題が十分には理解されていなかったが、オリンピックの延期を契機に認知が進んだ。本書では、スポーツイベントがどのように政治的、経済的なイメージ戦略に利用されているかを掘り下げる。
第一章 身近に潜むスポーツウォッシング
スポーツウォッシングは、政治的、経済的なイメージの向上を図るためにスポーツが利用される現象である。この章では、特に2021年東京オリンピックと2022年北京冬季オリンピックが、国際的な問題から目を逸らすためにどのように利用されたかが語られる。
第二章 スポーツウォッシングの歴史
スポーツウォッシングの具体例として、1936年のベルリンオリンピックやモハメド・アリ対ジョージ・フォアマンのボクシングマッチが取り上げられる。これらのイベントがどのように政治的な目的に利用されたかが詳述される。
第三章 主催者・競技者・メディア・ファン
スポーツウォッシングのメカニズムとして、主催者、競技者、メディア、ファンの4つの要素がどのように連携して作用するかが分析される。具体的には、ナチス政権下の1936年ベルリンオリンピックの事例が詳しく語られる。
第四章 「社会にとってスポーツとは何か?」を問い直す必要がある
平尾剛氏へのインタビューを通じて、スポーツと社会の関係、特にアスリート・アクティビズムの重要性に焦点を当てる。スポーツが単なるエンターテインメントではなく、社会的な意味を持つことが強調される。
第五章 「国家によるスポーツの目的外使用」
二宮清純氏による解説で、オリンピックがどのように政治的な目的で利用されるかが議論される。特に北京オリンピックやソウルオリンピックの事例が取り上げられる。
第六章 サッカーワールドカップ・カタール大会とスポーツウォッシング
カタール大会を事例に、スポーツ大会がどのように政治的、経済的利益のために利用されるかが解説される。日本サッカー協会の対応も含めて、日本のスポーツ報道の問題点が指摘される。
第七章 テレビがスポーツウォッシングを絶対に報道しない理由
テレビがスポーツウォッシングの問題を報じない背景にある、スポンサーとの関係や広告代理店の影響が詳細に分析される。
第八章 植民地主義的オリンピックはすでに〈オワコン〉である
山本敦久氏による解説で、オリンピックがもたらす社会的、経済的負担とその時代遅れの性質が批判される。アスリートが社会的問題にどう関与すべきかが問われる。
第九章 スポーツをとりまく旧い考えを変えるべきときがきている
山口香氏との一問一答を通じて、スポーツがどのように政治的、商業的に利用されるか、そしてアスリートがどのように社会的な発言を行うべきかが語られる。
感想
本書は、スポーツウォッシングという現象を深く掘り下げている。
スポーツは最高の余暇である。
スポーツウォッシングとは、「為政者や企業にとって都合の悪い政治的・社会的な歪みや問題を、スポーツの感動的なイメージを用いて覆い隠す行為」である。
特に、2020(2021)東京オリンピックや2022北京冬季オリンピックが例として挙げられており、大規模なスポーツイベントがいかにして政治的なイメージ洗濯に利用されるかが明らかにされている。
本の内容は、スポーツウォッシングの歴史的背景やメカニズム、そしてそれに関わる各国の事例を紹介し、その社会的な影響を考察している。
ナチスの1936年ベルリンオリンピックから、カタールのサッカーワールドカップでの労働者問題、そして最近の東京オリンピックでの論争まで、多岐にわたる事例が網羅されている。
また、スポーツジャーナリストやアスリート、社会学者など、多様な分野の専門家たちが登場し、彼らのインタビューを通じて、スポーツがどのように社会的な洗濯行為の道具として用いられているのかが詳細に語られる。
結末部分では、スポーツウォッシングに対する具体的な対策と、スポーツを取り巻く環境を改善するための提言が提示される。
具体的には、メディアの責任を強調し、透明性を高めること、またファンや視聴者がより批判的な視点を持つことが重要であるとされる。
さらに、アスリート自身が社会的な問題に声を上げることの重要性が強調され、スポーツの真の価値を示すためのステップが示されて終わる。
この本は、ただスポーツイベントの裏側を暴露するだけでなく、スポーツと社会の関係を再考させ、より意識的なスポーツ消費を促すための知識と視点を提供している。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
その他ノンフィクション

類似本












備忘録
はじめに
読者が手にした本は、スポーツ観戦好き、またはスポーツウォッシングという現象に関心がある方々向けである。
2020年の春に日本でも認識され始めた「スポーツウォッシング」という用語は、スポーツの健全なイメージを利用し、社会の問題を隠蔽する行為を指す。
東京オリンピック・パラリンピックの延期が契機となり、その認知が進んだが、日本ではこの問題に関する議論は進んでいなかった。
このギャップに気付いた著者は、自らの取材を基に、スポーツウォッシングの実態とそのメカニズム、影響、是正策について深掘りを試みた。
その過程で、オリンピックをはじめとする大規模スポーツイベントが、いかにして社会的な洗濯行為のツールとして利用されているかが明らかにされた。また、日本のスポーツ報道の窮屈さも浮き彫りになった。
本書は、スポーツウォッシングを俯瞰的に捉え、スポーツファンがプロスポーツを成熟した形で楽しむための手助けとなることを目指している。
第一部 スポーツウォッシングとは何か
第一章 身近に潜むスポーツウォッシング
スポーツウォッシングを有名にした本
スポーツウォッシングという言葉が日本のメディアで目にされるようになったのは2020年頃であった。
この用語はまだ一般に広く認知されておらず、記事にはその意味の説明が必ず添えられていた。
この用語が注目され始めた背景には、2021年の東京オリンピックと2022年の北京冬季オリンピックがある。
特に東京オリンピックは新型コロナウイルス感染症の蔓延により1年延期され、その間に多くの問題が発生した。
また、北京冬季オリンピックでは人権問題に対する国際的な批判があり、ロシアのウクライナ侵攻に伴う選手団の出場禁止処分などがあった。
これらの大会をめぐる問題から目をそらせるために、スポーツウォッシングという行為が用いられていた。
スポーツウォッシングは、ゴルフや競馬、モータースポーツ、サッカー、オリンピックなど、さまざまなスポーツ大会で見られる現象であり、民主主義国でも同様に人々の注意を他にそらす手段として使われている。
なぜ 2000年代に入って中東諸国がスポーツ招致に力を入れ始めたのか?
二輪ロードレースのMotoGPがカタールで初開催されたのは2004年であり、この年には四輪レースのF1もバーレーンで開催されていた。
2004年は、中東地域においてモータースポーツの元年のような年であった。
この時代には、テニスのドバイオープンやアブダビコンバットなどの大きなスポーツイベントが中東で開催されていたが、これらの競技は熱心なファンの間でのみ知名度があり、一般的な地理的認知は限られていた。
中東地域がスポーツイベントの開催を通じて世界に自国のプレゼンスを向上させようとした背景には、政情の不安定さや厳しい戒律といったイメージを払拭する意図があったと考えられる。
特に、ドバイは贅を尽くした都市開発で経済ニュースに取り上げられることが多く、世界一高いビル、ブルジュ・ハリファの建設などが注目されていた。
カタールの首都ドーハも、毎年の訪問ごとに建設現場が増え、サッカースタジアムやショッピングモールが立ち並ぶようになり、街の美化が進んでいった。
2022年のサッカーワールドカップ開催の決定は2010年であり、それ以降は街の整備と巨大建設工事がさらに加速された。
現代の〝奴隷労働〟、中東の「カファラシステム」
建設工事はインド、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ネパールなどからカタールにやって来た移民労働者たちによって行われた。
湾岸諸国では、これらの労働者に対して「カファラシステム」という制度が適用されていた。
これは、労働者のパスポートを雇用主が預かり、労働者の移動や出国の自由を制限するもので、労働者は劣悪な条件の長時間労働を強いられていた。
この制度には国際的な批判が多く、近年では改善が図られているが、根本的な問題は解決されていない状態であった。
日本ではこの問題はほとんど報道されず、国際的なスポーツイベントが開催される際には、メディアや選手が問題を指摘することでわずかに取り上げられる程度であった。
FIFAは労働環境の改善が進んでいると発表していたが、人権監視団体からは依然として賃金遅延や未払いが多いとの報告が出されていた。
欧米メディアでは 2010年代終盤頃から報道され始めた
本人が重大な人権問題としてカファラシステムを認識したのは、カタールGP開催から10年以上経った2010年代半ばだった。
友人のイギリス人ジャーナリストがカファラシステムに抗議し、現地取材のボイコットを始めた。
その際、ジャーナリストは記事を示し、すでに多数の労働者が命を落としていると指摘した。
この事実に直面し、毎日目にしていた現場が実際には奴隷労働の現場だと認識した。
その後、スポーツウォッシングという言葉が広まり、スポーツイベントを政治的なイメージ浄化の手段として利用する問題が、2010年代後半から議論されるようになった。
アムネスティ・インターナショナルが2018年にスポーツウォッシングを批判し、それに関するメディアの報道が活発になった。
この言葉とその問題が日本でも理解され始めたのは2020年頃からである。
第二章 スポーツウォッシングの歴史
最も有名なスポーツウォッシング、 1936年ベルリンオリンピック
日本で大ベストセラーとなったSF小説『三体』の作者、劉慈欣が書いた短編「栄光と夢」では、経済封鎖を受けるシーア共和国がアメリカとスポーツを戦争の代替手段として利用する二国間オリンピックを開催する内容が描かれていた。この短編は2003年3月に脱稿された直後、アメリカがイラクに対して戦争を開始している。
約20年後の現実の世界では、2021年の東京オリンピックや2022年の北京冬季オリンピックが開催され、これらの大会の意義について議論がなされている。さらに、ロシアがウクライナに侵攻した状況は、小説の想像を超える残酷で脆弱な現実を示している。
スポーツはしばしば国際的な紛争の解決手段として、また国家のイメージを宣伝するためのツールとして利用されてきた。特にオリンピックはその熱狂を利用して開催地のイメージを良くするスポーツウォッシングの機会となり得る。スポーツの政治利用は新しい現象ではなく、1936年のベルリンオリンピックがその先駆けであると広く指摘されている。ナチス政権はこのオリンピックを利用して国際的な批判を和らげ、ドイツの好イメージを宣伝した。
アリ対フォアマンの「キンシャサの奇跡」もスポーツウォッシングだった?
モハメド・アリとジョージ・フォアマンの間で行われた伝説的なボクシングマッチは、1974年にザイールで開催された。フォアマンは当時無敵とされていたが、アリが勝利を収め、ヘビー級王座に返り咲いた。この試合は、その後も「20世紀の名勝負」として語り継がれている。
この試合には、総額1000万ドルのファイトマネーが支払われ、資金調達にはドン・キングが中心となって動いた。資金はザイール政府とリビアのカダフィ大佐が出資したとされる。この試合は、劇的なアリの勝利を通じて彼の名声を高めることに寄与したが、ザイール政府のイメージアップにはあまり貢献しなかったようだ。
この事件のドキュメンタリーや関連映画が多く制作され、アリの生涯や影響力が詳しく描かれている。彼はスポーツだけでなく、人間としての姿勢も多くの人々に影響を与えた存在である。アリの逸話は、彼が黒人としての自負と叛骨心を持って生きたことを象徴している。
女子サッカー選手たちがオリンピックで人種差別に抗議
スポーツイベントが観客に対して一定の印象を刻み込む手段として利用される「スポーツウォッシング」は、アスリート自身がその作為に対抗する強力な力を持っていることがわかる。特に、F1のような国際的なモータースポーツでは、中東地域での大会が増加しており、その中でルイス・ハミルトンやセバスチャン・ベッテルなどの選手が、人権支援や政治的問題に対して積極的に発言し、その活動がメディアを通じて世界中に伝えられることで、スポーツウォッシングに対する有効な対抗手段となっている。
また、2021年東京オリンピックでは、女子サッカーの選手たちが人種差別に対する抗議のために試合前に片膝をつく行動を取り、これがBLM運動と連携して大きな注目を集めた。しかし、日本ではスポーツ以外の問題に対してアスリートが発言することは一般的ではなく、スポーツ報道は依然として試合の興奮や感動に焦点を当てたままである。このような状況は、スポーツを通じてのイメージ操作に対して脆弱な態度を示していると言える。
第三章 主催者・競技者・メディア・ファン 四者の作用によるスポーツウォッシングのメカニズム
スポーツウォッシングを構成する4つの要素
第一章でスポーツウォッシングの概要を紹介した後、第二章ではその歴史を振り返った。第三章では、スポーツウォッシングがどのように作用するのか、そのメカニズムを考えている。スポーツイベントを4つの要素に分け、スポーツウォッシングを仕掛ける主体との関係を示した簡単なモデルを提案している。主催者・運営関係者、競技者・参加団体、メディア、消費者がその要素である。これらは特に理論に基づくものではなく、取材経験に基づいた体感的な分類だ。
具体例として1936年のベルリンオリンピックを取り上げ、ナチス政権がいかにスポーツウォッシングを行ったかを考察している。ナチス政権は、IOCからの支持を得て、正統性のある大会として世界に認識させることを目指した。その成功は、主催者からの保証やメディアの報道を通じて、人々のナチス政権に対する認識を変えた。同様に、1980年のモスクワオリンピックや1984年のロサンゼルスオリンピックも、政治的駆け引きに利用され、競技の公正性に疑問を投げかけられた。
メディアとスポーツウォッシングを行う主体の関係は、取材と宣伝の相互作用であり、ナチス政権の場合、熱狂的な報道が人権抑圧を覆い隠す効果をもたらした。一方で、消費者はスポーツ観賞を通じてその正当性を承認する役割を果たしている。この関係性が強まると、スポーツウォッシングはその目的を達成する。これが、スポーツの力として表現されることは皮肉なものであるが、東京オリンピックや北京冬季オリンピックでも同様の現象が観察された。また、ソチ冬季オリンピックや2018年のFIFAワールドカップ・ロシア大会では、スポーツウォッシングを行う主体に正当性を与えるために、主催者や競技者が毅然とした態度をとらなかったことも指摘されている。
フォーミュラ Eレースも事件のウォッシングに利用された?
フォーミュラEが2018年にサウジアラビアで初開催されたことは、国内で初めての国際モータースポーツ大会として注目された。このレースは、ジャマル・カショギ氏の暗殺から2ヶ月後に行われ、サウジアラビアの皇太子ムハンマド・ビン・サルマーンが大規模なイベントを通じて国際的なイメージを向上させようとした。多数のセレブや政財界人が招待され、エンリケ・イグレシアスがコンサートを行い、ウェイン・ルーニーやダウ・ケミカルの元CEOがイベントに出席した。この行動がカショギ氏の暗殺報道から世界の注目を逸らすためだったのかは断定できないが、少なくとも日本語の記事ではカショギ氏の事件には触れられていなかった。
さらに、このようなスポーツウォッシングの行為は、主催者や運営関係者、競技者、メディア、消費者というスポーツイベントの四要素全てに影響を与える。各構成要素は互いに影響し合いながら、大会の興行としての成功を目指すが、スポーツウォッシングによって真実が隠され、大会の正当性や正統性が損なわれる可能性がある。特に東京オリンピックの招致に関連した不正や談合汚職事件などがその事例として挙げられる。これらの問題は、スポーツイベントがどのように政治的、経済的に悪用され得るかを示している。
仕掛けられたウォッシングに対抗するには
スポーツウォッシングが明らかに存在しているとき、その対策として以下の方法が考えられた。主催者や運営関係者は、審査や監査を通じて大会の承認や否認を行う権限を持っている。しかし、このチェック機能はしばしば機能しないことが東京オリンピックの招致問題で示されている。競技者や参加団体は、ボイコットすることなく大会での積極的な意思表示や発言によって影響力を示すことができる。メディアは、スポーツウォッシングを試みる主体を監視し批判する役割を持っているが、その機能が正しく働いているかは疑問である。消費者は、スポーツイベントを単なる娯楽として消費するだけでなく、その背後にある意図を識別し、適切な反応を示す責任がある。スポーツウォッシングが社会にどのように作用しているかを理解し、その対策を考えることが重要である。
第二部 スポーツウォッシングについて考える
第四章 「社会にとってスポーツとは何か?」を問い直す必要がある ――平尾剛氏に訊く
2021年の東京オリンピックとパラリンピックは、そのレガシーについて多くが疑問視された。大会終了から1年後の2022年夏に、多くの報告がされたが、その内容は具体性に欠けるものであった。大会施設の公共財への転用や、社会の向上への貢献についての明確な効果は示されず、逆に大会関係者の贈収賄や談合容疑での逮捕が唯一の「レガシー」となったようだ。一方で、平尾剛氏はスポーツウォッシングを批判し、アスリート・アクティビズムを提唱している。平尾氏はラグビー元日本代表であり、現在は大学でスポーツ教育学を教えており、アスリートが社会的出来事に声を上げることの重要性を説いている。
オリンピックは成功だったと言い張る東京都
平尾剛氏は、東京オリンピックが公的には成功したとされているものの、その実態について真摯に捉えている人も多いと指摘した。この大会は、新型コロナウイルスの流行中に開催され、多くの醜聞に見舞われた。平尾氏は、メディアを通じて開催意義に疑問を投げかけ、オリンピックに対する反対意見を積極的に表明していた。彼は、反対意見を表明することの無力感を感じながらも、それがオリンピックの裏側を明らかにする一助になったかもしれないと今は思っている。NHKの報告によれば、このオリンピックは異例ずくめであり、公式の「安全・安心に成し遂げることができました」という発言とは対照的な実態があった。
学会でも反対するなという同調圧力
東京オリンピックに関して、平尾氏は、開催が多くの議論を呼び起こし、終了後にはしばしば「成功した」とされているが、その実態については疑問が多いと指摘した。彼は、オリンピックが社会的弱者を犠牲にして開催されがちであると述べ、東京大会でも同様の問題があったと説明した。特に再開発によるジェントリフィケーションや、災害復興よりも大会準備にリソースが割かれたことを例に挙げた。さらに、オリンピックに対するスポーツウォッシングの問題を指摘し、大会の問題点を社会に提起し続ける重要性について語った。平尾氏は、スポーツ界内の同調圧力やスポーツウォッシングによる問題を批判的に捉え、これらの問題に対して社会的な議論を呼びかけることの重要性を強調した。
アスリートにはもっと声を上げてほしい
平尾氏は、日本のスポーツ界においてアスリート・アクティビズムの重要性を訴えた。彼は、アスリートが社会に積極的に関わり、自己の声を上げることがスポーツウォッシングからの脱却に不可欠であると主張した。また、平尾氏は、アスリートが競技のトップクラスを経験しているにもかかわらず、社会的な同調圧力に抗する者が少ないことに疑問を投げかけ、この状況を変えるためにもアスリート自身が社会的な発言を強化する必要があると述べた。彼は、スポーツが社会的な影響力を持つ一方で、スポンサーや主催者に利用されがちであるため、アスリートが自身の立場を活用して社会問題に声を上げるべきだと強調した。その上で、日本のアスリートが社会的な発言を控える傾向について、教育や文化的な背景が影響していると指摘し、アスリート自身が意見を持ち、それを表現することの重要性を説いた。
競技スポーツと生涯スポーツ
平尾氏は、スポーツがしばしば便利な〈洗剤〉として利用される現状に疑問を呈し、この状況は私たちのスポーツに対する未熟な関わり方に起因していると考えられると述べた。スポーツは単なるゲームでありながら、社会的な競争を映し出しているとも指摘される。スポーツは、競争による勝敗の感情を通じて、その折り合いをつける方法を学ぶ場であるとされる。また、スポーツは身体の可能性を示し、トップアスリートの活動を通じて、我々自身が持つ未知の身体能力を理解する手助けをしていると説明される。さらに、競技スポーツと生涯スポーツの違いが説明され、生涯スポーツの重要性をもっと認識し、勝利至上主義から距離を置くことが提案される。特に、教育の場であるべき学校のスポーツ活動において、勝利を最優先する風潮に反対し、生涯スポーツの楽しみを重視するべきだと強調される。全日本柔道連盟の決定など、競争の過熱を避ける動きが進められていることも紹介される。
20世紀的マーケティング思考から変わり始めたスポンサーたち
平尾氏は、スポーツが社会にとってどういう存在であるかという問いに対し、職場や家族とは異なる社会的つながりを提供する手段であると説明した。スポーツを通じて、人々は地縁や血縁を超えたコミュニティと関わることができ、それが新たな社会的な見方や理解を深める助けになるとされる。さらに、スポーツは人間の身体が持つ可能性を示し、それを体験することで、個人が社会の一部としての自己を再発見するきっかけになるとも述べられる。
また、スポーツを支える企業の役割についても触れられ、これからの企業は、単なるマーケティングの手段としてではなく、ESG(環境、社会、ガバナンス)に真摯に取り組む姿勢が求められるようになると指摘される。スポーツウォッシングの問題を超えて、スポーツが本来持つ価値を高め、社会に貢献するための意識改革が必要だと平尾氏は訴えている。
第五章 「国家によるスポーツの目的外使用」その最たるオリンピックのあり方を考える時期 ――二宮清純氏に訊く
オリンピックは、4年に一度開催される世界最大のスポーツイベントである。その規模は、参加する選手団や関係者の人数、報道量、ビジネス活動、経済効果など、他のどのスポーツイベントよりも大きい。しかし、それに伴い、利権を巡る汚職やドーピングなどの不正行為が絶えない問題も抱えている。スポーツジャーナリストの二宮清純氏は、1988年のソウルオリンピックから現在に至るまでのオリンピックを取材してきた。彼はスポーツウォッシングを「国家によるスポーツの目的外使用」と定義し、その現場での体験や見聞をもとに、これからのスポーツと社会との関係性について話を展開した。
国威発揚としてのオリンピック
オリンピックは世界最大のスポーツイベントであり、4年に一度、世界中から多数の選手団や関係者が集まる。二宮清純氏は、1988年のソウルオリンピック以来、長年にわたりオリンピックを取材してきた。彼は、スポーツウォッシングを「国家や企業によるスポーツの目的外使用」と定義し、オリンピックが国威発揚や政権浮揚の手段として利用されている実例を見てきたと述べている。特に2008年の北京オリンピックでは、中国が経済発展の象徴としてオリンピックを利用し、報道されるべきでない地域を隠していたと感じたという。また、ソウルオリンピックでは、ドーピング問題が顕著になり、東西の陣営がドーピングを異なる目的で行っていたことも指摘している。西側は金銭的利益のため、東側は国威発揚のためにドーピングを行っていた。オリンピックが商業主義を進め、さまざまな企業がスポンサーとして参入している現状も、二宮氏は詳細に語った。
メディアが〈勇気と感動のドラマ〉を流し続けることの罪
オリンピックが商業主義に傾斜していく中で、利権を狙った汚職が発生していた。ソルトレークシティ冬季オリンピックやリオ・デ・ジャネイロオリンピックなどでは、招致段階での汚職が明らかにされ、世界的なスキャンダルになった。一方、2021年に開催された東京オリンピックは、ロゴの盗作疑惑や組織委員長の辞任など、さまざまな問題が浮上し、大きな批判を浴びた。新型コロナウイルスの影響で1年延期されたが、開催は賛否が分かれ、激しい議論を呼んだ。大会が始まると、日本のスポーツメディアは、ジャーナリスティックな役割を放棄し、週刊誌がその機能を果たした。ニホンミヤ氏は、スポーツメディアが政治や経済においても非常に不完全であると指摘し、報道の自由度で日本は世界71位であることを述べた。東京オリンピックに関しては、日本の新聞社がスポンサーになったことが問題だとして、監視機能が鈍る恐れがあると警鐘を鳴らした。
スポーツに対する「固定観念」を外さなければならない
二宮氏によれば、日本のスポーツ界では「する」「見る」「支える」という役割が固定化しているために、スポーツと人々の関わり方が限定されてしまっている。役割の流動性を増すことで、スポーツへの関わりが多様化し、豊かになる可能性があると述べた。例として、ソルトレークシティオリンピックで元オリンピアンがボランティアとして活動していたことを挙げ、日本では見られないこのような役割の流動性が重要だと強調した。また、障害者スポーツの取り扱いについても触れ、パラリンピックが市民権を得たのに対して、デフリンピックはまだそうではないというメディアの慣習的な対応に問題があると指摘した。スポーツに対する硬直した考え方を改め、より自主的にスポーツの多様性を受け入れる必要があると述べた。また、スポーツを支える企業の考え方も、単なるスポンサーシップから、共にスポーツを育むパートナーシップへの移行が必要だと述べている。
第六章 サッカーワールドカップ・カタール大会とスポーツウォッシング
議論を呼んだサッカーワールドカップ・カタール大会
二宮氏によれば、日本のスポーツ界では「する」「見る」「支える」という役割が固定化されているため、スポーツと人々の関わり方が限定されてしまっている。役割の流動性を増すことで、スポーツへの関わりが多様化し、豊かになる可能性があると述べた。例として、ソルトレークシティオリンピックで元オリンピアンがボランティアとして活動していたことを挙げ、日本では見られないこのような役割の流動性が重要だと強調した。また、障害者スポーツの取り扱いについても触れ、パラリンピックが市民権を得たのに対して、デフリンピックはまだそうではないというメディアの慣習的な対応に問題があると指摘した。スポーツに対する硬直した考え方を改め、より自主的にスポーツの多様性を受け入れる必要があると述べた。また、スポーツを支える企業の考え方も、単なるスポンサーシップから、共にスポーツを育むパートナーシップへの移行が必要だと述べている。
日本サッカー協会からの回答
情報にアクセスしやすい現代においても、日本のメディアはカタールで開催されたサッカーワールドカップに関連する重要な問題点を大きく報じていなかった。特に、スポーツニュースでは、日本代表の活躍に関する情報が主であり、多様性の支持や差別反対といったグローバルな議論についての報道は見られなかった。後に、日本サッカー協会会長がメディアの質問に対し、「サッカーに集中する時」と述べたことが報じられ、日本代表の立場が明らかにされたが、初秋の時点では、これらの問題に対する具体的な情報は不明確であった。
そこで、日本サッカー協会に直接取材を申し込み、国際サッカー連盟(FIFA)の規約に従うという内容の一般的な回答を受け取った。この回答は、具体的な問題には触れず、一般論に終始しており、具体的な行動計画には言及がなかった。全体として、回答は具体性を避け、FIFAの方針に従う姿勢を示すものであった。このような事務的な回答は、日本サッカー協会が政治的な問題に対して積極的な姿勢を取ることを避け、スポーツに集中する方針を強調するものであった。
一部のメディアは取り上げたものの……
スポーツの舞台での人権啓発が政治的な行動とされるべきかどうかについて、日本サッカー協会(JFA)からの回答は、具体的な内容が欠けており、議論から距離を置いた態度が示された。この姿勢は、日本のスポーツメディア全般にも見られる傾向だった。日本のサッカー界が人種や民族差別に反対する活動を行っている一方で、JFAの発言や行動からは、アスリート・アクティビズムへの前向きな姿勢は感じられなかった。しかし、カタールワールドカップの期間中、新聞やオンラインメディアはスポーツウォッシングに言及する記事をいくつか掲載し、議論を呼んだ。一方で、地上波テレビはこの問題を避け、報道しない姿勢を続けた。次章では、テレビメディアがなぜこの問題から距離を置くのかについて考察する。
第七章 テレビがスポーツウォッシングを絶対に報道しない理由 ――本間龍氏に訊く
2021年の東京オリンピックに関連して、日本でもスポーツウォッシングという語が議論され始めた。2022年のサッカーワールドカップ・カタール大会においては、この用語がさらに注目を集めた。しかし、活字メディアではこの用語が使われ始めたのに対して、テレビでは依然として使われていなかった。放送メディアがスポーツウォッシングに対して沈黙を守り続ける理由について、広告代理店博報堂出身の著述家、本間龍氏に尋ねた。
なぜテレビはスポーツウォッシングを報じないのか
2022年のサッカーワールドカップ・カタール大会以降、「スポーツウォッシング」という用語が活字メディアで頻繁に見られるようになった。この言葉は、Googleなどで検索すれば多数のオンライン記事がヒットするが、新聞でも様々な記事が掲載されている。しかし、これは活字情報に限った現象であり、テレビなどの映像情報ではスポーツウォッシングについてほとんど取り上げられていない。東京オリンピックやサッカーワールドカップの中継や関連ニュースで、この問題に言及した番組はほとんどなかったとされる。また、2022年の北京冬季オリンピックの時期には時事トピックを扱う番組で「スポーツウォッシング」という言葉が使用されていたが、オリンピックや競技の中継では聞かれなかった。ホスト国カタールの国営放送局・アルジャジーラが大会に対する批判を取り上げていた一方で、日本のスポーツニュースではそのような議論はほとんどなく、テレビのスポーツ番組はスポーツウォッシングについて触れず、問題に対して見て見ぬふりをしている。
テレビはスポンサーの機嫌を損ねることは絶対にしない
スポーツイベントはテレビにとって視聴率を保証する重要なコンテンツであり、安定したスポンサーがつくため、スポーツウォッシングという問題をテレビが取り上げることはほとんどなかった。元博報堂社員で著述家の本間龍氏によれば、これはスポンサーの影響力が大きいからである。テレビのスポンサーが多くスポーツ大会や選手たちを支援しているため、スポーツウォッシングについて言及することはテレビ局にとってタブーである。また、広告代理店はスポンサーの顔色をうかがい、テレビ局に問題あるコンテンツの取り扱いを控えるように言う。日本では、スポーツウォッシングを取り上げることがスポンサーを批判する行為につながりかねないとされ、それを避けるために積極的にこの問題に手を出さない傾向が強い。この日本的な事なかれ主義は、スポンサーとテレビ局の間で特に顕著である。
大坂なおみの行動に対する NIKEと日清食品の姿勢の差
2020年の全米オープンテニスで、大坂なおみ選手はBLM運動を支持し、警官の暴行で亡くなったアフリカ系アメリカ人の名を記したマスクを着用した。この行動は世界的に注目され、NIKEは彼女の行動を即座に支持し評価された。一方、日清は大坂選手の行動に言及せず、彼女の「かわいい」イメージを前面に出す応援メッセージをSNSに投稿し、これが批判を招いた。日清は以前にも大坂選手の肌の色を白く演出したアニメ広告で批判された経験がある。これらの出来事は、NIKEと日清の企業としての社会的責任に対する姿勢の違いを浮き彫りにした。本間氏は、日本の企業が社会的な問題に対して取り組むことを避ける傾向があると指摘し、これが広告代理店やテレビ局にも影響を及ぼしていると説明した。特にテレビは、スポンサーの機嫌を損ねることを避け、社会的なメッセージを含む提案を採用しない姿勢を取っているとされる。
電通抜きではオリンピック開催は無理。贈収賄・談合はまた起こる
東京オリンピックに関して、巨大イベントが作り出した陰の部分は次々と明るみに出された。電通元専務やKADOKAWA会長など、複数の関係者が逮捕され、電通グループなど6社が起訴された。大会の予算は当初の計画から膨れ上がり、最終的には談合汚職事件として処理された。このことは予想されていたが、それにしても不十分な結末であった。大会組織委員会元次長が逮捕された翌日には、車椅子テニスの国枝慎吾氏が引退会見を行い、東京パラリンピックでの優勝を最大の思い出と語ったが、彼の活躍と利権や私欲の温床として利用された事実はむなしさを感じさせる。
本間氏は、フジテレビの子会社の専務も逮捕されたが、フジテレビはこの事実をほとんど報じなかった。そのため、フジテレビを見る視聴者は逮捕の事実を知らない可能性があると指摘し、大きな問題についても報道できないテレビ局の実態を批判した。これは、捜査と裁判を通じて問題が根本から洗い出される契機になるのか、日本の贈収賄と談合の体質が改められるのか、楽観的な見方をする人は少ないだろう。今後も同様の問題が繰り返される可能性が高い。
第八章 植民地主義的オリンピックはすでに〈オワコン〉である ――山本敦久氏に訊く
BLM運動の高まり以降、人種差別反対や性的マイノリティの権利支持を積極的に表明するアスリートたちが目立つようになった。一方で、彼らの行動や発言を「政治的発言」として忌避する声も多い。では、「政治」と「人権」の境界はどこにあるのだろうか。その区別は本当に可能なのか。また、なぜ人々はスポーツの舞台を「無菌室」と見なし、アスリートの沈黙を容認するのか。これらの問題について、成城大学の山本敦久教授に訊いた。
F1ドライバーも MotoGPライダーも声を上げた
「スポーツに政治を持ち込むな」という言葉は、昔からアスリートに対して繰り返されてきたが、近年、様々な競技の選手たちが社会的アクションを起こすことで、その言葉の意味が問われ、揺さぶられた。2020年の全米オープンテニスでBLM運動を支持した大坂なおみや、2022年のサッカーワールドカップ・カタール大会で出稼ぎ労働者の実態や性的マイノリティ差別に抗議したヨーロッパの選手たちの行動が知られている。また、2022年12月にF1の統括団体が政治的発言に事前許可を求めたことに対し、2023年2月にルイス・ハミルトンが「自分が関心のあることについては誰にも止められない」と述べた。ハミルトンはBLM運動支持のTシャツを着用し、LGBTQ+の権利を支持するアクセサリーを身につけていた。また、2020年のMotoGPサンマリノGPでは、フランコ・モルビデッリが人種平等を訴えるメッセージが込められたヘルメットで参加し、初優勝を飾った。
日本のスポーツ界には「社会」がない
近年、アスリートたちが差別反対や平等を訴える活動は世界的に増えているが、日本人アスリートの場合は例外が多い。2021年東京オリンピックで、女子サッカー日本代表が人種差別に反対するジェスチャーを示したことが話題となったものの、これは例外であった。特に、2022年サッカーワールドカップ・カタール大会において、欧州の選手が人権抑圧に抗議した事実をどう捉えていたのか、日本人選手の反応は伝わっていない。
山本敦久氏によると、2016年にNFLのコリン・キャパニックが試合前に片膝をつく姿勢で人種差別反対を示し、BLM運動や#MeToo運動が活発化し、2021年東京オリンピックにも影響を与えた。IOCは選手の政治的表現を認めないガイドラインを2020年に打ち出したが、多くの国からはアスリートの表現の自由を尊重すべきだとの反論があった。しかし、日本のアスリートたちからは、ほとんど意見が聞かれず、特に日本サッカー協会会長の「サッカーに集中するとき」という発言に対する反応も明らかにされていない。
山本氏は、日本のスポーツがエンターテインメントと学校的世界に限定され、社会的な議論や問題提起から遠ざけられていると指摘する。アスリートたちは、社会的な問題に積極的に声を上げることが少ないと述べ、これは日本特有の社会的体質の一端を示していると説明している。
スポーツの常識とされるものが、そもそも政治的に偏っている
山本敦久氏は、スポーツにおける「政治」とは基本的人権の平等性を求める声がなぜ「政治的」と見なされるのかを問うている。スポーツが「政治的零度」として、何も偏らない純粋な場所とされる一方で、実際にはナショナリズムや性的差別などの偏見が混入しているのが現実である。スポーツが持つこの「政治的零度」の位置が、すでに偏った政治であり、多様化する社会の中でそれを再評価する必要があると山本氏は指摘している。
また、歴史を振り返れば、1936年のベルリンオリンピックや冷戦時代のイデオロギー対決を背景に、国家によるスポーツの政治利用を抑止しようとする動きがあった。しかし、1968年メキシコオリンピックでのトミー・スミスとジョン・カーロスのアクションが起点となり、スポーツにおける政治的表現が徐々に受け入れられるようになった。山本氏は、スポーツがスポーツ自体を「スポーツウォッシング」し、世の中の不都合を覆い隠しているとも説明しており、現代ではスポーツにおける「政治」の定義が拡大し、アスリートたちの個々人の行動や発言を規制する方向で作用していると述べている。
政治ではなく人権の問題
山本氏によれば、現代の日本におけるアスリートたちは、社会との積極的な関わりや発言をほとんど見せていない。彼らは「スポーツの力」という言葉に頼ることが多く、社会の複雑さや多様性に無批判であるため、現代社会において真のロールモデルとしての役割を果たすことは難しいと指摘されている。特に、スポーツの力がナショナリズムなどの道具として使われることはよく知られているが、スポーツが社会の不平等を改善する力にもなり得ると彼は述べている。
さらに、現代のアスリートたちは、過去のアスリートたちが経験したような社会的な締め出しを受けることは少なくなっており、発言の機会やメディア環境が整っているため、より多くの支持を受けることができる。大坂なおみのようなアスリートは、自己のアイデンティティとスポーツを分け隔てなく表現することで、人々の理解や共感を得ている。また、アスリートたちが「政治」という言葉を避け、「人権」という言葉を使うことで、社会運動や主張が過度に政治化されるのを防ぎつつ、より広く受け入れられやすくしていると山本氏は説明している。
オリンピックは各国の公金を食いつぶしていく植民地主義経済
山本氏は、スポーツが社会の一部として、社会の矛盾や歪みに対して声を上げ、それを是正していく動きは自然なことだと述べている。しかし、オリンピックにおける汚職事件など、組織的な問題に焦点が当てられる一方で、本質的な問題が見過ごされることを危惧している。特に、IOCがオリンピックを利用して開催都市の公金を使い、巨大な施設を建設し、負の遺産を残して去っていく行動を、植民地主義経済に例えて批判している。
また、山本氏は、オリンピックがアスリートにとって最高の舞台ではないかもしれないと指摘し、現代のスポーツ環境においてオリンピックは過去のものとなりつつあると語っている。これは、特定のスポーツで世界記録がオリンピック外で出ることが多いからであり、一部の選手はオリンピックを単なる一大会と見なしている。彼はスポーツが社会変容を促す力を持っていると信じており、過去のオリンピックが社会に与えた影響を評価している。
さらに、現代の若者はオリンピックに対して冷めた見方をしており、彼らにとってオリンピックは重要なものではなくなっているとし、彼らの関心は他のエンターテインメントに移っているという。
第九章 スポーツをとりまく旧い考えを変えるべきときがきている ――山口香氏との一問一答
スポーツウォッシングに関する問題は、2021年の東京オリンピック以降、日本でも徐々に認識されるようになってきたが、その発言は主に研究者やジャーナリストに限られていた。この問題に対してスポーツ界からの声はほとんど聞かれず、〈完黙〉に近い状態が続いていた。筑波大学の教授であり、1988年ソウルオリンピックで柔道銅メダルを獲得した山口香氏は、オリンピアンとしての経験と全日本柔道連盟強化委員、JOC理事としての職歴を持ち、東京オリンピックの際にはJOC当事者として、忖度なしに冷静かつ積極的な批判を展開してきた。山口氏は、スポーツやアスリートと政治・国家との関係について様々な角度から問いかけに対して、的確で刺激的な返答をしている。
日本の選手はなぜ自分の意見を言えないのか
山口香氏は、スポーツウォッシングについて言及しており、スポーツがプロパガンダの一形態として利用される場合があると指摘した。特に冷戦時代、ソ連や東ドイツなどはスポーツを政治的な目的で利用し、ドーピングも行われていた。山口氏によれば、スポーツはその魅力と価値が高いために、歴史的に様々な利用が行われてきた。現代でも、広告やコマーシャルにスポーツ選手が登場することは、そのイメージ戦略の一環と見ることができる。
山口氏は、アスリート自身がこの利用されやすさについてどれだけ自覚しているかについても言及し、現役時代には自分たちの努力が評価されることに重きを置いていたが、社会から離れた視点で見ると、その利用されやすさに警戒すべきだと気づいたと語った。一方で、年齢層が広がり、40代や50代の現役アスリートも増えており、彼らは社会経験が豊富で、より広い視野を持っている可能性がある。
また、日本のアスリートが国際的な舞台で積極的に発言することが少ない理由について、日本が島国であることや、文化的・歴史的背景が影響しているとの見解を示し、日本のアスリートが育成される環境が、彼らがスポーツ以外の事に対して発言し難い環境であることを指摘した。これに対して、山口氏は、社会の多様化に対応できるよう、アスリート自身が社会との関わりを自覚し、自立的に行動することが重要であると強調している。
政治とスポーツは切り離せるのか?
山口氏は、日本のアスリートたちが育つ環境について言及し、その環境がアスリートたちが社会問題に対して積極的に意見を述べることを抑制していると指摘した。また、多くの日本のアスリートたちにとって、大坂なおみやルイス・ハミルトンが訴えている社会問題は、実感として感じるものではなく、リアリティが伴わないと述べた。これは、日本が比較的平和で守られた状態にあるためであり、スポーツや学問に専念する環境が整っているためだと解説している。
山口氏はさらに、多くのスポーツが経済的な支援がなければ成立しないことに触れ、特にシーズンスポーツは高額な費用がかかり、恵まれた環境で育たなければならないと述べた。そのため、貧困や差別といった問題に対する実感が乏しいと指摘。ただし、才能がある場合はその選手を育成する試みがあるが、それがどれだけ効果的であるかは未検証であると語った。
さらに、日本ではスポーツが教育の一環として捉えられており、多くのアマチュアスポーツが国のサポートを受けていることを挙げ、スポーツと政治を切り離すことの複雑さについて議論した。国の支援と完全に切り離して民間スポンサーに頼るモデルが成立するかどうか、そしてその運営がうまくいくかについては、明確な答えがないと述べている。
「個人の資格でもオリンピックに参加する」という日本選手はいるのか?
山口氏は、「スポーツに政治を持ち込むな」という言葉がどのように使われているかについて述べ、スポーツが権力によって操られる可能性を警戒している。彼は、政治がスポーツに資金を提供する際、それが自由な資金提供であることはまずなく、国の方針や目標が前提にあると指摘した。例として、国のプレゼンス向上や国民の健康促進が挙げられたが、それには外交問題も絡んでくることがあると語った。
また、モスクワオリンピックのボイコットを例に挙げ、国と異なる立場を取る場合の複雑さを説明し、国が示す方針と異なる判断をする場合のアスリートの対応について考えを述べた。日本のアスリートが国の指示とは異なる行動をとる場合、その自己責任が問題となるかもしれないと述べ、アスリート自身が個人としての判断をすることの重要性を強調した。
山口氏は、日本のアスリートたちが国の方針に従うことを前提とした環境で育っているため、個人として独立した行動を取ることが難しいと指摘。しかし、彼はそうしたアスリートを育てていくことが望ましいと考えていると述べた。
アスリートの姿は日本国民の映し鏡
山口氏は、個人資格でオリンピックに参加する場合の複雑さについて説明し、政治とスポーツの独立性についての議論が不足していると指摘した。特に、政治がスポーツに対して資金を提供する場合、それには国の方針や目的が伴い、権力の行使が影響を及ぼすと述べた。これは、1980年のモスクワオリンピックのボイコットや最近の日本学術会議の任命拒否問題にも関連しており、国家の影響下にある状況を反映している。
また、JOCが独立組織として機能するための困難を説明し、国からの資金依存が独立性に与える影響について考えを述べた。JOCが実際に独立して活動を続けるための経済的基盤や政治的影響からの自由をどう確保するかが議論されていないとも指摘した。
この問題を、国がアスリートに対してどのように対応しているかというより広い社会的文脈で考えるべきであり、アスリートが個人として政治的な立場を表明することの複雑さを、日本国内での依存と従属の文化と関連付けて説明した。山口氏は、スポーツの世界も政治の影響から完全に独立することは期待できず、これが国民の姿勢や考え方の反映であると述べている。
スポーツは国家の枠組みから逃れられないのか
山口氏は、2023年5月にドーハで開催された柔道世界選手権について語り、ロシアとベラルーシの選手が中立の立場で参加し、ウクライナの選手団がボイコットした事例を挙げて、スポーツが政治とどれだけ難しいバランスを取らなければならないかを示した。彼女は、国間の直接的な対決の場となるスポーツイベントでは、選手たちがその国の政治的状況に影響され、中立と言えどもその背後には深刻な問題があると指摘した。また、スポーツイベントが平和の象徴とされる一方で、戦争で亡くなったアスリートがいるウクライナなどでは、スポーツと政治を簡単に分離できないと述べた。
さらに、アスリートが政治的な発言を避けるべきかどうかについても言及し、アスリートが自国に帰った際のリスクも考慮する必要があるとした。しかし、スポーツが社会を変えていくためには、理想論を繰り返し語ることの重要性を強調し、第三者がその役割を果たすべきだと説明した。この議論は、スポーツと政治が完全に切り離せない複雑さを示している。
スポーツは、世界に変化のさざ波を起こし続けていける!
山口氏は、アスリートが差別反対の意思を示す行為は政治ではなく人権の問題として捉えられるべきだと述べたが、その問題を解決するためには政治的なシステムの改変が不可欠であると指摘した。彼は、スポーツの世界での政治的な問題に対する国際的な抗議行動が、結局は政治の領域に行き着くと述べた。さらに、日本のアスリートたちは、そのような問題について積極的に発言することが少ないと指摘し、これが日本国内の文化的背景やスポーツに対する一般的な捉え方によるものだと説明した。彼女は、スポーツが単なる遊びではなく、重要な社会的役割を持っていると強調しつつ、スポーツと芸能がしばしば見下されがちな傾向にあると批判した。
スポーツが国家やジェンダーの枠組みを超えていくために必要なこと
山口氏は、オリンピックが理想的には国家を背負わないアスリートたちの祭典であるが、現実には国家代表としての意識が強いと説明した。彼女は、プロスポーツとアマチュアスポーツの違いについても言及し、大坂なおみや松山英樹のようなプロアスリートは個人的なチームを持っているため、国を背負う意識は薄いが、アマチュアスポーツでは国の支援と期待が重いため、その意識が強いと指摘した。また、スポーツと国家の関係を緩和するためのシステム変更に向けた提案もしており、国際競技の選抜を国家を超えた形で行うことで、スポーツの未来像が変わる可能性があると述べた。彼女は、スポーツが国家のプレゼンスを高める手段として使われがいるが、そうした状況を変えていく新しい考え方も広がりつつあると説明した。
スポーツとオリンピックの新しいありようを考える
山口氏は、2021年の東京オリンピックについて、その意義が未だに明確でないと述べた。彼女は、1964年の東京オリンピックが復興の象徴であったのに対し、2021年のオリンピックは賛否が分かれ、総括されていないと指摘した。先進国ではオリンピックの開催意義を見出しにくい現状を語り、特にウクライナのような紛争中の国々では、平和が訪れた後にスポーツが重要な役割を果たす可能性があるとした。しかし、彼女はスポーツが即座に国際問題を解決する力はないとも述べた。山口氏は、将来的にはアジアやアフリカの複数都市が共同でオリンピックを開催することで、新しい経験や価値を生み出せると提案し、IOCがオリンピックの理念をうまく提示していないと批判した。彼女は、オリンピックが本来持つべき価値について考察し、スポーツが国際的な友好と理解を深めるための平台であるべきだと主張した。
おわりに
2021年にバレンティーノ・ロッシがMotoGPチームのオーナーになり、サウジアラビアの企業をタイトルスポンサーに迎える計画を発表した際、ヨーロッパのメディアはこれをスポーツウォッシングに関連づけて批判的に報道した。ロッシへの厳しい質問が続いたが、スポンサー関係は最終的に破談となり、イタリアの企業が新たなスポンサーとなった。このエピソードは、スポーツと政治の関連性やスポーツジャーナリズムの重要性を浮き彫りにしており、スポーツウォッシングへの批判的なアプローチが示された。また、サウジアラビアの事例を引用しながら、スポーツウォッシングがもたらす社会的影響についても議論がなされた。本書の取材と執筆に対する謝辞とともに、スポーツが社会に与える影響とその責任についての洞察が示されている。
Share this content:
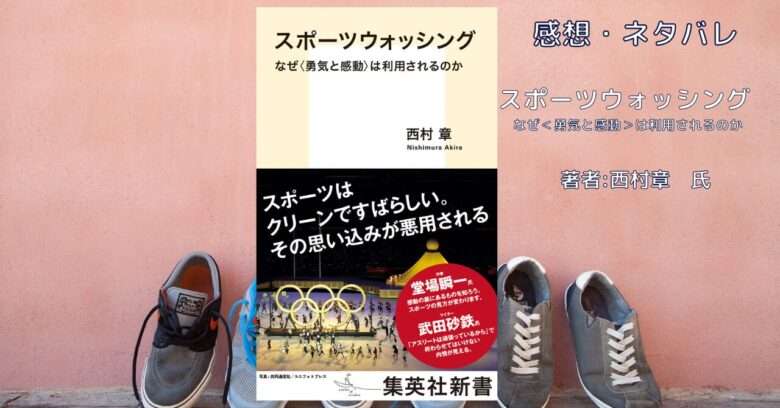

コメントを残す