森永卓郎さんが2025年1月28日に亡くなってしまった。
ご冥福をお祈りいたします。
2025年1月27日の”大竹まことゴールデンラジオ”に出演していた時の声を聴いたときにキツソウだと思ってたら。
残念でならない。
どんな本?
『遺言 絶望の日本を生き抜くために』は、がんで余命宣告を受けた経済評論家の森永卓郎氏と岸博幸氏が、日本の現状と未来について本音で語り合った対談本である。
この本は、単なる経済議論に留まらず、二人の経験や人生観が色濃く反映されている点が特徴的である。森永氏は、竹中平蔵氏や財務省の増税政策に対する批判、また日本の「失われた30年」の要因について過激な意見を述べているが、岸氏はその発言をマイルドに受け止め、二人の違いを踏まえながらも、建設的な対話が繰り広げられている。
特に、森永氏が「本当のことを言って死ぬ」という覚悟で発言する姿勢と、岸氏が冷静に日本の未来を見据えた分析を行う点が読みどころである。がんという共通の病を抱えながら、彼らは絶望的な状況に向き合い、未来をどう生き抜くべきかを語っている。
経済や政治、社会問題に興味がある人はもちろん、人生観を深めたい人にもおすすめの一冊である。
読んだ本のタイトル
「遺言」絶望の日本を生き抜くために
著者:森永卓郎 氏 岸博幸 氏
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
霞が関での宮仕え、退官してからの経済評論家や学者としての活動のさなか、がんが判明、余命宣告……そんな森永卓郎氏と岸博幸氏の2人による日本社会へのメッセージ。
死と向き合うことでどう人生観や生き方が変わったのか。その他「霞が関を去った理由」「がん治療」「ザイム真理教」「失われた30年と経済産業省」「原発」「防衛政策」「対米従属」「小泉構造改革」「今の株式市場はバブルか?」など、多岐のテーマで語る本音トークが満載の一冊です。
感想
『遺言』は、がんで余命宣告を受けた森永卓郎氏と岸博幸氏が、日本社会や経済について本音で語り合う対談本であった。
二人は全く異なる経済スタンスを持ちながらも、共に貧しい経験を持ち、がんという病気を共有しているという背景から、深い共感と相互理解が感じられた。
森永氏は、竹中平蔵氏への批判や「財務省と経産省の違い」など、これまで避けてきたテーマにも鋭く切り込んでいた。
特に「失われた30年」や小泉構造改革の影響に関する指摘は、彼の過激な発言を和らげながらも対話を進める岸氏とのやり取りが印象的であった。
反対に岸氏は、竹中平蔵氏と共に小泉構造改革に参加してる側の人だったので彼の視点から見た構造改革は森永氏の指摘してるのとは違うと云う辺りは責任逃れをする公務員の答弁だなとも感じつつ。
その辺りの見直しをしたがらない、事に苛立ちを感じた。
本書を通じて、二人が日本の未来について深く考え、警鐘を鳴らし続ける姿が浮き彫りになっている。未来は決して楽観的ではないが、開き直った彼らの語り口は意外にも前向きな力強さがあり、読者に「これからの生き方」を考えるきっかけを与えてくれる。
最後に残るのは、森永氏の「本当のことを言って死ぬ」という覚悟と、それを支える岸氏の冷静な対話術である。共に未来を憂いながらも、読者に何をすべきかを問いかけてくる一冊であり、深い示唆に満ちていた。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
その他の著者の著書








その他ノンフィクション

備忘録
まえがき(森永卓郎 氏)
岸博幸氏との対談において、著者はこれまで深い話をしたことがなかった。著者が本番前に話すことを好まなかったためである。対談では、著者と岸氏の人生に対するタイムスパンの捉え方の違いが明確に表れた。著者は余命4カ月と宣告され、短い時間で動いていたが、岸氏の余命は長く、長距離走のように息継ぎをしながら進める姿勢が見られた。
対談中、意見の違いはあったが、岸氏は対立を避けながらも巧みに会話を進めた。著者が過激な表現を使う場面もあったが、岸氏はそれを柔らかく表現することで、場を穏やかに保つ技術を発揮した。特に経済に関する議論では、二人の見解が一致し、日本経済の停滞の原因として分配の不平等を挙げた。岸氏は大企業と政府の癒着を批判し、著者はグローバル資本主義が日本を圧迫していると指摘した。
また、日本航空123便の墜落事件についても言及があり、著者はこの事件が日本の対米服従の源流だと考えていたが、岸氏は事件の詳細について知らなかったと答えた。
最後に、著者と岸氏の生き方の違いが語られた。岸氏は都会的で裕福なライフスタイルを提案し、著者は自然と共に生きる「トカイナカ暮らし」を推奨した。どちらの生き方を選ぶべきか、読者に問いかけていた。
1章 さらば「霞が関」
岸氏は経済産業省を40代で辞職した理由について、改革を進める立場にあったが、その後、省内での立場が難しくなると予想し、自分のやりたいことを優先して退職したと説明していた。彼は、竹中平蔵氏の秘書官として大きな権限を持ち、役所内の仕事よりも民間で挑戦することを選んだ。
一方、森永氏は日本専売公社(現・JT)に就職したが、貧困に陥った経験を語っていた。彼は経済企画庁に出向していたが、専売公社の民営化により、給与が大幅に減少し、当時の手取りは約13万円しかなかったという。また、バブル到来を予測した際、誰にも信じてもらえなかったため、自ら家を購入する決断をしたと振り返っていた。
二人はそれぞれ官僚としてのキャリアを持ちながらも、自分のやりたいことを優先する選択をした点で共感し合っていた。
森永氏は、家を購入した際、住宅ローンの支払いにより、月々の手取りが6万円を切るほど厳しい経済状況に陥っていた。当時、妻が粉ミルクを優先して購入し、晩御飯が「ひじき」だけの日もあった。彼は残業食を利用してカロリーを補給していたが、家庭の厳しさを感じていた。
その後、森永氏はJTでの仕事にやりがいを感じていたが、国家公務員上級職試験の年齢制限により役所でのキャリアを断念することになった。また、役所での中途採用において、キャリアの年数が半分しかカウントされないというルールに直面し、最終的にシンクタンクへの移籍を決断した。
バブル期にシンクタンクで働くことで、森永氏の年収は急上昇し、残業代も含めて給料が大幅に増加した。彼は妻に給与明細を見せ、自慢したが、わずかに100万円に満たなかったため、褒められることはなかった。
一方、岸氏は経産省を辞職する際、母親からも反対されていたが、自分のやりたいことを優先して決断した。官僚時代には政策に携わり、その後大学で教えながらテレビ番組にも出演するようになった。彼はテレビ番組出演が自身の思考を柔軟にし、様々な意見交換を通じて成長したと感じていた。
2章 「がん」と向き合う
岸氏は、多発性骨髄腫を患っており、2023年に診断された。この病気は血液のがんであり、治療によって10年から15年の余命が見込まれていた。岸氏は自家造血幹細胞移植を行い、現在は定期的な治療を受けていた。彼の医療費は毎月20万円ほどであり、経済的にはなんとかやりくりできていたが、収入が低い人には大きな負担であると語っていた。
一方、森永氏もステージ4のすい臓がんを宣告され、余命4カ月と診断されていた。彼はその後、複数の医師に診断を仰いだ結果、最終的には「原発不明がん」と診断された。治療には免疫療法を取り入れており、毎月100万円以上の医療費がかかっていた。
二人はそれぞれ、がんと共に生きる生活を送っていたが、岸氏はまだ10年の余命があることに感謝しつつ、惰性の仕事を排除し、やりがいのあることに集中するように生き方を見直した。一方、森永氏は「どうせ先行きは短いから、本当のことを言って死のう」と決断し、タブーとされる問題にも積極的に発言するようになった。
3章 「失われた 30年」と経済産業省
岸氏は、日本社会において企業は栄えるが、個人の幸せを追求しにくい状況があると感じていた。日本の企業は豊かだが、労働者の賃金が低く、経済成長が個人に還元されない現状に問題を見出していた。特に、企業の内部留保が増えている一方で、賃金の上昇はわずかであり、これが国民の豊かさにつながらないと指摘していた。
森永氏も同様に、企業の利益が個人に還元されない理由を岸氏に問いかけた。岸氏は、デフレ時代にサラリーマンとしてリストラやコストカットを経験した経営者たちが、インフレ下でも大胆な賃上げを行うマインドを持っていないことが一因だと分析していた。
森永氏は、自身が余命わずかであるという状況を「強いカード」とし、その立場から自由に発言できると考えていた。岸氏もまた、残された10年の間に、働く人々や家計を少しでも改善したいという意欲を持っていた。
また、企業が栄え、国民がやせ細る現象の責任者として、竹中平蔵氏が名指しされたが、岸氏は竹中氏だけでなく、政府の短期的な政策が影響を与えたと述べていた。森永氏も小泉政権の構造改革に批判的であり、当時の政策が日本経済に悪影響を与えたと考えていた。
岸氏は、小泉政権の政策に対する批判について、小泉政権が始めたと思われがちな非正規雇用の拡大やタクシー業界の規制緩和などは、実際には小泉政権以前に策定されていたものであると指摘していた。小泉政権が郵政民営化を推進したことから、規制緩和や競争原理の導入が小泉政権によるものだと誤解されがちであると述べていた。
また、木村剛氏については、批判されることが多いが、岸氏は不良債権処理において木村氏の貢献を高く評価していた。特に、りそな銀行への公的資金注入の際に木村氏の知識とアイディアが役立ったと述べていたが、木村氏が後に逮捕された事件は別問題であると強調していた。
森永氏は、1990年代の政策の問題が「失われた30年」の起点となり、日本経済の衰退が始まったと分析していた。岸氏は、経済企画庁が国民生活を豊かにする能力に欠けていたことを指摘し、経済や人口が右肩上がりだったバブル期には、政策の歪みが顕在化しなかったが、近年その影響が強く表れていると語っていた。
さらに、森永氏は自身がシンクタンクで通産省の仕事をしていた頃のバブル期を振り返り、当時は接待や不正が多く行われていたことを述べていた。その中で、官僚と業界の癒着が現場の理解を深める一因にもなっていたと述懐していた。
森永氏は、2000年代からの行政改革が進みすぎた結果、役所が現場の実態を無視して上から目線の政策を押し付けるようになったことが、日本の通商産業政策の崩壊につながったと述べていた。これに対し、岸氏は、官僚と業界の関係が2000年代以降に変わり、接待がなくなったことで情報が入りにくくなり、政策決定の主導権も財務省に移ったと指摘していた。
小泉構造改革の結果、政策決定権が官僚から政治家に移ったが、財務省は組織的に諮問会議を取り込み、一方で経産省は非協力的な態度を取ったため、財務省の支配が強化された。また、岸田政権下で再び財務省の影響力が強まったと述べていた。
さらに、経産省の国策プロジェクトに関して、森永氏は過去の失敗例(JDIやエルピーダメモリ)を挙げ、TSMCやラピダスの誘致も失敗する可能性が高いと見ていた。これに対し、岸氏は、今回のプロジェクトは過去とは異なり、成功の可能性があると述べていたが、人材不足が課題であると指摘していた。
また、森永氏は、アメリカが最先端の半導体を自国で生産し、日本にはリスクの高い汎用品を生産させる戦略に懸念を示していたが、岸氏は同盟国間の生産分担として理解できる部分もあると述べていた。
森永氏は、岸田政権が原発の新設や増設を推進し、重要な電源として位置づけた政策に疑問を呈していた。彼は、経産省が自身の利権のために政策を変えたと考えていたが、岸氏は、安倍政権も原発を容認していたが、憲法改正を最優先していたため、原発推進を控えたと説明していた。
森永氏は、原発の放射性廃棄物の最終処分が未解決であり、日本には適地が存在しないと指摘していた。岸氏も最終処分場の問題が重要であり、経産省が対応を怠ってきたと認めていたが、エネルギー政策の多様化が必要であり、再生可能エネルギーだけでは現状の日本を支えるのは難しいと述べていた。
森永氏は、電力料金を引き上げ、自然エネルギーを利用した地方移住や電力自給自足の推進が必要だと提案し、災害対策や安全保障の観点からもその重要性を強調していた。一方、岸氏は、日本にとってエネルギー問題は常に大きな課題であり、安定供給、低料金、環境保護のバランスを考えながら、原発を含めた議論を続ける必要があると述べていた。
森永氏は、原発立地地域や原発関連企業からの講演依頼が非常に高額なギャラを伴うことに疑問を持っていた。彼自身、1時間の講演で100万円以上の報酬が提示されることがあり、東日本大震災前には黒塗りのハイヤーによる送迎もあったと述べていた。このような高額な講演料は、何か後ろめたい事情があるのではないかと推測していた。
岸氏は、このような費用が予算に計上されていることを認め、ロビー活動やメディア対策の一環として世論を作るために使われている可能性が高いと述べていた。森永氏は、原発関連の講演や金融関係の講演は特に単価が高いと感じており、これらの業界に対して怪しさを指摘していた。
4章 ザイム真理教
森永氏は、財務省の官僚を「カルト教団」と表現し、彼らが政策を推進する際に嘘を用い、増税を強要する手法を批判していた。特に、財務省が財政破綻を煽り、増税を正当化している点に疑念を抱いていた。彼は、たとえば2020年度から2024年度にかけての財政絞り込みが約70兆円に達しているが、税収見積もりを正確に行えば、プライマリーバランスは黒字になると主張していた。
岸氏は、財務省を「軍隊」に例え、非常に組織的で戦略的に動く点を指摘していた。財務省は政策の実現のために、相手との貸し借り関係を最大化し、統一された説明を行うことで強力な影響力を持つと評価していた。
さらに、森永氏は財務省の出世システムにも問題があると述べ、増税を行うと「ポイント」が付与される一方で、経済成長による税収増には評価が伴わないと指摘していた。このため、増税が目的化していると批判していた。
森永氏は、特に消費税を増税した官僚が「レジェンド」として称えられ、財務省内で高く評価されるシステムが存在していると指摘していた。岸氏は、財務省が税収が増えているにもかかわらず、財政再建を強く主張し続けている理由として、慎重な役所の性格や財政のリスク管理を挙げたが、森永氏はそれが「カルト教団化」していると批判していた。
財務省の影響力について、岸氏は、財務省が政治家やメディアに対して非常に戦略的にロビー活動を展開し、その結果、多くの政治家が財務省の立場を受け入れてしまうと述べていた。森永氏は、これを「洗脳」と表現し、特に中途半端に経済を勉強した議員が財務省の主張に簡単に納得してしまうことを問題視していた。
また、森永氏は、野党議員に対しても財務省の説明が浸透しており、説得が難しいと嘆いていた。彼は立憲民主党の長妻昭氏との対話を例に挙げ、財務省の統計が誤導的であると説得しようとしたが、「腑に落ちない」と返され、納得させることができなかった経験を語っていた。
森永氏は、財務省が批判的なメディアに対して税務調査を行う可能性があることを指摘し、産経新聞や東京新聞の事例を挙げていた。田村秀男氏が財務省の「ご説明」を論破した直後に産経新聞に税務調査が入り、財務省の批判に対する圧力が感じられると述べていた。
岸氏は、財務省の「注射」によって増税路線が正当化される構造が、民主党政権時代や現在の岸田政権にも見られるとし、財務省が政治家やマスコミに対して影響力を持っていることを認めていた。しかし、彼は財務省の権力基盤が以前より弱体化しているとも述べていた。
また、近年の優秀な学生が官僚ではなくコンサルティングや投資銀行に就職し、起業を選ぶケースが増えていることにも言及し、東大生の霞が関離れが顕著であると指摘していた。森永氏は、外資系企業との待遇差が官僚離れの一因であり、岸氏も自らの激務経験を振り返りつつ、現在の「ブラック」「パワハラ」という風潮に違和感を覚えていた。
最後に、森永氏は財務省が名前を変えても体質が変わっていないと指摘し、カルト的な性質が強まっていると感じていた。
岸氏は、1990年代の橋本政権による行政改革で財務省の権限が弱まったとされるが、結果として、金融庁や国税庁のトップが依然として旧大蔵官僚であり、財務省の支配が続いていることを指摘していた。特に、厚生省と労働省の統合が現代の日本で多くの問題を引き起こしているとし、厚労省の大規模化が小回りの利かない組織に変えてしまったことを問題視していた。
森永氏は、財務省の支配が金融庁や国税庁だけでなく、検察や裁判所にまで及んでいると批判し、森友学園事件を例に挙げていた。近畿財務局の職員であった赤木俊夫氏が違法行為を強要され自殺したにもかかわらず、改ざんを指示した佐川宣寿元国税庁長官が処罰されず、退職金まで受け取っていることに強い疑念を抱いていた。
また、岸氏は安倍政権下で経産省出身者が官邸を取り仕切っていたことに言及し、安倍氏の「財務省不信」から、財務省が安倍政権を取り込むことに苦労したと述べていた。森友学園事件は、財務省の弱体化を象徴するものだと指摘していた。
5章 防衛政策
森永氏は、岸田政権が防衛費をGDP比2%に増加させたことについて、議論が不足していると指摘し、特にアメリカからの巡航ミサイル購入などが問題であると述べていた。岸氏は、東アジアの情勢変化を考慮すれば、防衛費の増加はやむを得ないが、自衛隊の装備や処遇改善に十分な予算が充てられていないことを懸念していた。また、円安により予定していた装備が買えなくなる可能性も指摘していた。
森永氏は、日本が他国から攻撃を受けた際には、全国民が「ベトコン化」して抵抗する必要があると主張していた。さらに、彼は自らもロケットランチャーで敵を迎撃すると冗談交じりに述べたが、この考えには支持者が少ないと嘆いていた。岸氏は、韓国の徴兵制に触れ、日本でも若者が自衛隊で修行する制度が必要ではないかと提案していた。
また、森永氏は、国産ジェット機事業の撤退に言及し、アメリカが型式証明を出さなかったため、三菱スペースジェットが失敗に終わったことを批判していた。彼は、アメリカが依然として日本にジェットを飛ばさせないようにしていると指摘し、経産省が反応すべき案件であったと述べていた。
岸氏はアメリカに対して強い反感を抱いており、その理由は自身の経験に基づいていた。1995年から3年間、ニューヨークにある国際機関KEDOに出向していた際、アメリカ人女性と交際していたが、その時にアメリカ人の「自国が常にナンバーワン」という優越思想を実感したと述べていた。アメリカ人は自分たちの考えが世界基準であり、日本を子分のように扱っていると感じたという。
森永氏も、アメリカとのいびつな関係を体験した一例として、1964年にアメリカの小学校に通った際、同級生に「お前は人間じゃない」と言われた経験を語っていた。また、アメリカが日本に輸出する穀物にだけ農薬を使用していたことにも疑念を持っていたが、アメリカ人農業関係者から「家畜にも農薬を使っている」と言われ、彼らの態度に不満を感じたとしていた。
6章 小泉構造改革
森永氏は、ダイエーの不良債権処理について、当時2つの対処法が存在していたと述べた。1つは放置することで、時間が経てば地価の回復とともに解決できた可能性があると指摘している。一方、竹中大臣はダイエーを政府の監視下で再生させる選択を取った。森永氏はこの決定を「アメリカの圧力に屈服した」と捉え、小泉総理がアメリカの要請に応じて不良債権処理を急いだと考えた。
これに対し岸氏は、アメリカの圧力によるものではなく、日本国内の経済政策として不良債権処理が必要だったと説明している。小泉政権は、日本経済の低迷を解消し郵政民営化を進めるために、不良債権処理を優先させたと述べ、アメリカの影響はなかったと反論している。
森永氏は、小泉政権の郵政民営化について、政府が提示したメリットは競争原理の導入、税収増加、資金の自由運用の3点だったと指摘し、民営化後のデメリットが国民に回っていると述べた。郵便事業の利便性が低下し、料金の負担も増加した結果、国民は幸せになっていないと批判した。
これに対し岸氏は、郵便局が独り立ちするために完全民営化を目指したが、その後の政権が民営化を逆行させ、中途半端な状態にしてしまったことが問題だと述べた。徹底的な民営化か国営化のどちらかを選ばなければ、結局国民に負担がかかるとし、現状に対する残念さを表明している。
森永氏は、郵貯・簡保の民営化により、国民の安全な貯蓄手段が失われ、代わりにリスクの高い投資信託が勧められるようになったことを批判し、民営化が国民にリスクを押し付けるものであると指摘した。岸は、投資のリスクを否定することはできないが、政府がリスクを煽りながら救済措置を講じていない点に問題があると認めた。
また、森永氏は小泉構造改革の一環で製造業への派遣労働が解禁されたことを非難し、竹中平蔵氏がその責任を否定している点を批判した。岸は、この政策は小泉政権以前に決まっていたもので、竹中氏が直接推進したものではないと説明したが、竹中氏が後にパソナの会長となったことについては、国民からの批判が当然であり、その評価は国民に委ねるべきだと述べた。
うーん、責任転嫁回答。ʅ(◞‿◟)ʃヤレヤレ
森永氏は、外国人労働者受け入れについて議論し、短期的には労働力不足解消に効果があるものの、中長期的には賃金低下や財政負担の増加を招き、結果的に日本経済の成長を阻害すると主張した。また、欧州の経験を引き合いに出し、日本も同じような問題を抱える可能性があると懸念した。
岸氏は、これまでの外国人労働者の受け入れは主に技能実習制度に基づいており、小泉政権時代には抑制的だったと述べた。しかし、岸田政権が受け入れを大幅に拡大し、低技能労働者の長期滞在や家族の帯同を認める方針に舵を切ったことが問題であると指摘した。特に、日本が優先すべきは高技能の外国人労働者の受け入れであるが、産業界の要望に基づいて低技能労働者の受け入れが拡大している現状を批判した。
森永氏はまた、1985年を境に日本の対外政策が対米従属に変わったと指摘し、その原因を日航機123便の墜落とプラザ合意に関連づけた。岸氏はその見解に対し、政府内でそのような説に触れたことはなく、1980年代の日米関係では日本がアメリカの圧力に対して弱気になっていたと感じたと述べた。
7章 株式市場はバブルか?
森永氏は、現在の世界は史上最大のバブルに直面していると述べ、特にエヌビディアの半導体バブルを「チューリップバブル」と比較して警戒していた。また、新NISAや投資信託への過度な依存が将来の資産暴落につながり、多くの国民が大損失を被ると予測していた。彼は特に、株価暴落と急激な円高による資産減少のリスクを強調していた。
岸氏は、日米の株価がバブル状態にあると認めつつ、日本の実体経済が悪化しており、日銀の利上げが早すぎた決定であると批判していた。また、彼は円安が長期的に進行する可能性が高いと予測し、新NISAへの投資者が大きな損失を被る可能性も指摘した。
さらに、両氏は投資詐欺に関する話題にも触れ、森永氏が詐欺広告で「ダントツ1位」として名前を悪用されていることを述べた。岸氏も同様に「ニセ岸博幸」による被害を受けたとし、政府の対応の遅さを批判していた。
森永氏は、AIについてもバブルであり、創造性に欠けるとし、AIが活躍するのは既存キャラクターの盗用やフェイク動画作成のような場面に限られると述べていた。岸氏はAIの可能性を認めながらも、現状ではまだ未成熟であり、過度な期待は禁物だと主張していた。
8章 森永流「これからの生き方」
森永氏は、新型コロナ禍で仕事が激減したことを契機に、「トカイナカ」という生き方を提案した。彼は畑を借りて自給自足を試みたり、太陽光発電で生活費を抑える実験を行い、月10万円もあれば生活できると証明した。これにより、資本主義の奴隷から脱却し、郊外や田舎での生活が可能であることを示した。
岸氏は、日本の強みとして「現場の力」を挙げ、現場の創意工夫が個人の幸福につながると述べた。欧米ではエリート層が国を動かす一方、日本ではエリートが弱く、現場の力が文化や産業を進化させてきたとした。森永氏もこれに同意し、企業に依存しない生き方が日本人の豊かな生活を取り戻す鍵であると語った。
森永氏は、グローバル資本主義が日本社会を行き詰まらせているとし、これを捨てるべきだと主張した。彼は、地球環境の破壊、格差の拡大、少子化、無意味な仕事(ブルシットジョブ)の蔓延が日本の問題を深刻化させていると述べた。また、東京一極集中が地域間格差を生み出し、不動産市場も異常な状態にあると指摘した。
彼はさらに、企業が労働者を「洗脳」し、アルバイトを「キャスト」や「クルー」と呼んで企業への一体感を強調しながらも、最低賃金で労働させている現状を批判した。こうした仕組みでは、本来の仕事の喜びはなく、ただ疲弊するだけであり、個人の幸福が遠のくと結論付けた。
森永氏は、静岡県知事川勝平太氏の「知性の高い県庁職員」と農業を比較する発言に対し、批判が集中したが、森永氏はこの発言が農業経験の欠如に基づくものだと捉えた。実際、農業は非常に知的な仕事であり、自然の厳しい環境と対峙しながら作物を守るための知恵と工夫が必要であると述べた。例えば、カラスによるスイカへの被害を防ぐための対策を挙げ、農業の難しさと達成感を強調した。
また、森永氏は都市生活が健康に悪影響を及ぼし、特に輸入食品の農薬や抗生物質が危険であると警告した。そして、都市生活のコストが高すぎて子育てや結婚が困難になり、少子化が進んでいると指摘した。森永氏は、首都機能の移転を提案し、「自産自消」「地産地消」「国産国消」を推進することで、都市への依存を減らし、国内の自給自足を強化すべきだと主張した。
さらに、森永氏はグローバル競争をやめ、農業への所得保障を強化する必要性を訴え、原子力発電からの完全撤退と、個々の家庭でのエネルギー自給を促進するべきだと述べた。首都機能移転については、過去の国会決議や法律に基づいて既に政府が責務を負っているとし、具体的な進展が必要であると強調した。
あとがき(岸博幸氏)
岸博幸氏は、森永卓郎氏との経済政策に対する見解の違いにもかかわらず、親近感を抱いていた理由が、両者が貧しい経験を共有していたことに気づいた。森永氏は貧困の中でやりたい仕事を追求し、岸氏も家庭の事情で奨学金なしでは進学できない状況にあった。これらの共通体験が、国や企業ではなく国民生活の豊かさを目指すという共通の目的につながっていた。
また、両者が同じ病気にかかっていることも奇遇であり、森永氏が余命宣告を受けながらも対談に時間を割いている姿に岸氏は深く感銘を受け、森永氏を「国士」と称した。森永氏は、自身の残りの時間を他者のために使い、真実を語り続ける姿勢を見せ、これが言論人としての真骨頂であると評価された。
岸氏は、デフレで弱体化した日本経済を再興するためには、企業が大胆な賃上げや投資を行い、個人が仕事や再訓練に全力を尽くす必要があると主張した。また、個人の幸福と経済復活を目指すために、現状の政治と経済政策の大幅な修正が必要であり、自民党の再生が日本経済の再生につながると考えていた。
最後に、岸氏は若者の才能を認め、彼らを支援することが重要だと強調し、森永氏や編集者に感謝の意を表した。
Share this content:
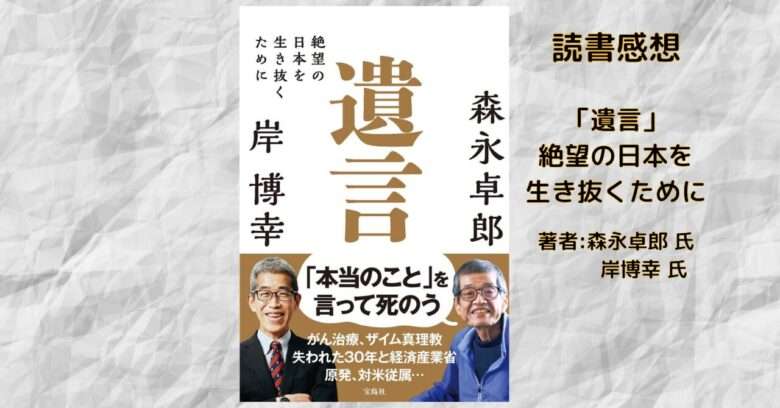

コメントを残す