どんな本?
『フェイクニュースの見分け方』は、ジャーナリストの烏賀陽弘道氏が著した新潮新書の一冊である。本書は、現代社会に氾濫する虚偽情報や誤情報を見抜くための具体的かつ実践的な方法を提供する。著者は、新聞、雑誌、ネットといった多様なメディアの第一線での経験を基に、情報の真偽を判断するためのノウハウを伝授している。
主な内容
• インテリジェンスの重要性:公開情報の活用法や、情報収集の基本的な姿勢について解説する。
• オピニオンの取扱い:意見と事実を区別し、根拠のない主張に惑わされないための指針を示す。
• 情報発信者の確認:匿名情報や主語のない文章を疑い、信頼性を評価する方法を紹介する。
• ビッグ・ピクチャーの適用:時間軸や空間軸を広げて情報を捉え、全体像から真実を見極める手法を提案する。
• フェアネスチェック:情報の公平性や偏りを検証し、バランスの取れた視点を持つためのチェックポイントを提供する。
本書の特徴
本書は、具体的な事例や実践的なアドバイスを豊富に盛り込み、読者が日常生活で直面する情報を批判的に評価する力を養うことを目指している。特に、情報の受け手としての責任や倫理についても深く考察し、他の類似書籍とは一線を画す内容となっている。
出版情報
• 出版社:新潮社
• 発売日:2017年6月16日
• ISBN:978-4-10-610721-4
• ページ数:256ページ
• 価格:880円(税込)
電子書籍版も主要なプラットフォームで配信されており、読者の利便性に配慮している。また、本書の内容を基にしたオーディオブックも提供されており、詳細は出版社の公式サイトで確認できる。
読んだ本のタイトル
フェイクニュースの見分け方
著者:烏賀陽弘道 氏
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
一見もっともらしいニュースや論評には、フェイク(虚偽の情報)が大量に含まれている。真偽を見抜くには何をすべきか。「オピニオンは捨てよ」「主語のない文章は疑え」「空間軸と時間軸を拡げて見よ」「ステレオタイプの物語は要警戒」「アマゾンの有効な活用法」「妄想癖・虚言癖の特徴とは」――新聞、雑誌、ネットとあらゆるフィールドの第一線で記者として活躍してきた著者が、具体的かつ実践的なノウハウを伝授する。
感想
こんな時代だからこそ読んでみた。3回も読み直したが、フェイクニュースを見分けるのはやはり難しい。
情報源や引用、参照元、署名は常識としても、知らぬ間に誘導されていることもあった。
海外ニュースでも、その記者が日本に詳しくないため観光客のような視点でレポートしていることがあるらしい。
本書で強調される「ビッグ・ピクチャー」や「フェアネス・チェック」の視点は重要だが、自分の知識の幅が狭いため難しく感じた。
その幅を広げるためには、色々な本を読むしかない。
自分がまだまだ未熟だと再確認した。
実例を挙げながらの解説は非常に納得でき、実際に役立ちそうだ。
必読の書であると感じた。
根拠のない情報をオピニオン、根拠のある情報をファクトと定義する本書のアプローチは明快であった。
「事実に基づかない言説は捨てる」「主語のない文章は疑う」「空間軸と時間軸を広げて情報を精査する」といった指摘は、情報を見極める上で非常に参考になった。
この本を読んでもなお、正しく見分けられるか自信はないが、心がけてみようと思う。
メディアの荒廃や、日本のネット規制の遅れについても警鐘を鳴らしており、考えさせられる内容だった。
現在、マスメディアの劣化は止まるところを知らず、元新聞記者である著者の思いが強く反映された一冊であった。
具体的な記事の事例も多く、メディアリテラシーを考える上で非常に有用な本であった。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
備忘録
はじめに
フェイクニュースの見分け方
新聞記者からフリー記者への道のり
著者は1986年に朝日新聞社へ入社し、新聞記者としてのキャリアを開始した。その後、週刊誌記者や編集者を経てフリー記者となり、活字媒体に関わる多様な職種を経験した。フリー記者となった現在は、写真撮影やビデオ撮影も行うようになった。
メディア技術革新の体験
著者は、アナログからデジタル、そしてオンライン化へのメディア技術の進化を職業の現場で体験してきた。新聞、雑誌、書籍、インターネットと媒体が変化する中で、原稿用紙とボールペンからワープロ、パソコン、さらにはiPhoneでの執筆へと作業環境も進化した。かつてはテレタイプやファクスで原稿を送っていたが、現在ではクラウドサーバーにリアルタイムで情報を入力することが一般的となった。
インターネットの恩恵と課題
著者は、インターネットの普及が自身の人生に大きな恩恵をもたらしたと述べている。ネットというメディア革命がなければ、新聞社を辞める決断には至らなかった可能性もある。しかし一方で、インターネットの普及は「信頼できる情報を見つける」作業を一層困難にした。何が事実で何が虚偽かを判別することが難しくなり、旧型メディアも衰退を始めた。
情報のカオスと民主主義への影響
インターネットの普及と旧型メディアの衰退により、社会全体は「情報のカオスの海」に投げ出された。この海では虚偽の情報と事実が混在し、人々は現実を知ることに苦痛を感じ、次第に無関心になる。この現象は民主主義社会にとって大きな不幸である。
事実を見つけるための方法
著者が本書で紹介するのは、職業生活の中で自然に身につけた「事実の見つけ方」である。この方法は著者個人の体験に基づくものであるが、混乱したメディア環境の中で正確な情報を見つけ出すための一助となることを目指している。
第 1章 インテリジェンスが必要だ
公開情報の重要性
アメリカ連邦議会調査局での経験
1993年夏、著者はアメリカ連邦議会調査局(Congressional Research Service)でインターンとして勤務した。スーパーバイザーのロバート・サッター氏は元CIAの中国担当分析官であり、彼から「CIAが扱う中国情報の95%は公開情報である」との教訓を得た。公開情報には新聞、テレビ、政府の公式見解、論文、名簿などが含まれ、非公開情報があっても、それを理解するためには公開情報の背景が不可欠であると説かれた。
情報分析のプロセス
CIA分析官は日々公開情報を収集し、それを基に非公開情報の価値を判断する。分析結果は議員や政府機関に提供され、「インテリジェンス」として活用される。この手法は記者の取材活動と類似しており、著者も公開情報を出発点に取材を進めてきた。公開情報と非公開情報(特ダネ)の組み合わせが、事実に近づく鍵である。
オープンソースインテリジェンス(OSINT)の役割
公開情報を分析する活動は「オシント(OSINT)」と呼ばれ、人間からの情報収集「ヒューミント(HUMINT)」や通信傍受「シギント(SIGINT)」と並ぶ重要な情報源である。質の高い報告は、公開情報と人間情報が有機的に組み合わさることで現実に近づく。
日本会議と安倍政権の関係性の検証
書籍と公開情報の調査
2016年、保守系政治団体「日本会議」に関する書籍が相次いで出版された。多くの書籍が「日本会議が安倍政権に影響を与えている」と主張したが、著者は記者としての経験からその説に疑問を抱いた。保守的政治団体と保守的政治家が同様の目標を掲げるのは一般的であり、それが直接的な影響力を示す証拠にはならない。
具体的な検証方法と結果
著者は公開情報を利用して日本会議と安倍政権の関係を調査した。政治資金規正法に基づく献金データや首相の動静を「Gサーチ」で検索した結果、過去10年間で安倍首相と日本会議関係者が公式に会ったのは2回のみであり、合計49分に過ぎなかった。この結果から、日本会議が安倍政権の政策決定に重大な影響を持つという説には納得できる証拠が見出せなかった。
批判と事実の必要性
著者は、政権や権力を批判する際には事実に基づく必要があると強調した。根拠のない批判は説得力を欠き、社会の不信感を助長するだけである。公開情報を精査することが、信頼性の高い批判の基盤となる。
効果的な情報収集ツール
Gサーチの活用
著者は、有料オンラインデータベース「Gサーチ」を推奨した。全国紙、地方紙、通信社、テレビ局など多岐にわたるメディアを横断検索でき、信頼性の高い情報源を効率的に探し出せる。一方、GoogleやYahooなどの無料検索エンジンは、リンク数やSEOに基づく結果が多く、信憑性の確認に手間がかかると指摘した。
アマゾンと図書館の活用
アマゾンは書籍と著者のデータベースとして優れており、新刊本から絶版書まで一括で検索できる。著者は福島第一原発事故後、この方法で専門家を探し出し取材を行った。また、国会図書館や東京都立図書館のネット検索も、公開情報収集において重要なツールである。
まとめ
膨大な公開情報を蓄積し分析することがインテリジェンスの第一歩であり、95%の公開情報が5%の非公開情報に意味を与える。マスメディア情報の信頼性を確認するには、他の公開情報でクロスチェックすることが不可欠である。Gサーチ、アマゾン、図書館のネット検索システムは、信頼できる情報収集のための有効なツールである。
第 2章 オピニオンは捨てよ
オピニオンとは何か
事実のない意見は捨てるべき
著者は、証拠となる事実が提示されていない意見(オピニオン)は捨てても構わないと述べた。ファクトの裏付けがない意見は社会において重要な意味を持たない場合が多い。例えば、斎藤美奈子氏が川内原発の再稼働と熊本地震の関係について述べたコラムでは、九州電力や政府関係者の発言や公式文書など、具体的な証拠が提示されていないため、著者はその意見に説得力を感じなかった。
ファクト・ベースド・オピニオンの重要性
裏付けとなる事実を伴う意見は「ファクト・ベースド・オピニオン」と呼ばれ、捨てる必要はない。このような意見は事実を基にしているため、検証の出発点として有用である。斎藤氏のコラムでも、川内原発が稼働していることや熊本地震の震源地が拡大しているといった事実は根拠として有効であるが、その後の推論には具体的な証拠が欠けていた。
インターネット時代のオピニオンの増殖
発信者の特権の消失
インターネットの普及により、誰でも自由に意見を発信できるようになった。ブログやSNSを通じて無数の意見が発表される中で、単なる主観や感想だけでは価値を持ちにくくなった。著者は、特別な知識や視点、個性がなければ他者との差別化は困難であると指摘した。
旧メディアの影響力の低下
インターネット以前の時代、マスメディアを通じて意見を表明することは特権であり、その特権自体が意見の価値を担保していた。しかし、現在ではメディア関係者以外にも優れた知識や感性を持つ発信者が多数存在し、旧メディアの発言者の意見は特権としての価値を失っている。新聞の社説やコラムも、もはや社会的価値を保証するものではなくなった。
オピニオンが事実として重要な場合
発言者の影響力が鍵
オピニオンそのものが事実として重要になるのは、発言者が社会的影響力を持っている場合である。例えば、オバマ大統領の「プラハ演説」は具体的な政策変更を伴わなくても、アメリカの軍事外交政策の転換を示す事実として重要であった。また、ISILの機関誌が日本を敵対視する国家として名指ししたことも、日本人がテロの標的となる可能性を示す事実とみなされた。
事実の探求の出発点としてのオピニオン
オピニオンは事実を探求するための出発点となり得る。斎藤氏のコラムの中で「日本地震学会の会長が南西方向にも注意が必要だと言っている」との記述があったが、著者がこれを検証した結果、その発言が川内原発に直接関係するものではないことが判明した。このように、オピニオンは新たな事実を探すきっかけとなる。
代理話者と自己検閲の問題
代理話者の増加と報道の質の低下
新聞やテレビのコラムやコメント欄に登場する「代理話者」は、取材不足や事実確認の甘さを補うために利用されることが多い。著者は、代理話者の意見が多用されることは、報道機関の取材能力の低下を示すものだと指摘した。取材によって裏付けられた事実が不足している場合、代理話者の意見に頼る傾向が強まる。
報道機関の自己検閲
報道機関が政権からの圧力を恐れて自主的に報道内容を抑制する「自己検閲」も問題視された。著者は、権力に対する監視が報道の責務であるにもかかわらず、圧力を恐れて自己規制することは報道機関自身の資質の問題であると述べた。
安倍政権の言論統制の実態
具体的な事実の欠如
著者は、安倍政権が報道に圧力をかけたとする主張に対して、具体的な証拠が提示されていないことを指摘した。例えば、『安倍政治と言論統制──テレビ現場からの告発!』という書籍は、NHKや民放のキャスター降板を政権の圧力と結びつけているが、著者はこれを支持する具体的な事実を見出せなかった。実際、降板したキャスター自身が政権からの圧力を否定しているケースも多かった。
報道と権力の関係性の再確認
報道機関と権力の間には常に緊張関係が存在するべきであり、政権がマスメディアに対して批判を行うこと自体は異常ではない。著者は、報道が権力を監視する責務を持つ以上、一定の摩擦は避けられないと述べた。圧力を受けたと感じたとしても、それが事実として証明されない限り、単なるオピニオンとして扱うべきである。
まとめ
著者は、証拠のないオピニオンは事実として受け入れるべきではなく、ファクト・ベースド・オピニオンのみが検証の価値を持つと結論付けた。報道と権力の関係は常に緊張状態にあるべきであり、圧力と感じる出来事も、それが証拠によって裏付けられない限り、単なる意見に過ぎない。報道の質を保つためには、事実に基づいた情報の提供と、自己検閲に陥らない姿勢が求められる。
第 3章 発信者が不明の情報は捨てよ
匿名情報の信頼性と報道の責任
匿名情報の受信と記者の原則
著者は報道記者として30年間、匿名者からの情報提供は確認できるまで事実と見なさない原則を守ってきた。新聞社や週刊誌勤務時代からフリー記者となった現在に至るまで、発信者が特定できない情報は信用度が低いと考え、無視することが基本姿勢である。特にネット上の匿名情報は責任感の低下を招き、事実性が損なわれやすいと警鐘を鳴らしている。
匿名情報提供の実例とその限界
1990年代、著者が医療問題を担当していた際、「国立N大学医学部のP教授が研究データを盗用している」という匿名の手紙を受け取った。教授が実在することは確認できたが、差出人は名前を明かさず、面会も拒否したため、情報の真偽を直接確認することができなかった。情報提供者の正体が不明である限り、その情報がどれほど事実に近いかを測る手段がないため、著者は記事化を見送った。
主語不明の文章と情報の信憑性
記事において主語が明確でない文章は、事実としての信憑性が著しく低下する。著者が新人記者時代に上司から「主語が何かわからない文章を書くな」と厳命されたことを例に挙げ、特に受動態で終わる文が多用される報道記事には注意を促している。具体的な発言者や行為の主体が明示されていない場合、読者は情報の真偽を判断する材料を欠くことになる。
組織による信用保証の限界
日本の新聞社は無署名記事が一般的で、組織が記事の信頼性を保証する形式をとってきた。しかし、このスタイルは時代遅れになりつつあり、特にインターネットが普及した現代においては、個々の記者の署名や責任が重視されるべきと著者は主張する。組織が信用を担保しても、内部腐敗が進めばその保証も形骸化する。
匿名発信とネット情報の危険性
ネット上の匿名情報は特に信用性が低く、誤情報やデマの温床となりやすい。例えば、熊本地震の際に「被災地に届いた生理用品を送り返した男性がいる」という話が広まったが、これは東日本大震災時の伝聞が誤って拡散された結果だった。こうした伝言ゲーム的な情報の変形は、匿名発信が責任感を欠くために発生しやすい現象である。
信用できる匿名者の例外
匿名情報すべてが信用できないわけではない。著者は福島第一原発事故後、ツイッターで匿名のP氏と交流を深め、最終的に対面して信頼関係を築いた例を紹介する。P氏の協力により、著者は封鎖区域の内部取材を実現した。また、エネルギー問題に詳しいQ氏からも正確な資料提供を受け、情報の正確さを確認できたことで信頼を寄せた。
記者の価値判断と報道の中立性
報道記事には、記者の価値判断が無意識に混入する危険性がある。例えば「連れ込み」「意気込む」といった表現は、読者の印象を操作するものであり、事実の裏付けがない限り使用すべきでない。著者は、記者自身の判断が混じった文章には常に疑いの目を向けるべきだと強調している。
メディアの印象操作とその影響
世界遺産登録の報道などで頻繁に使用される「意気込む」「胸を張る」といった表現は、現実の冷静な反応を誇張し、祝賀ムードを強調する傾向がある。著者はこうした報道スタイルが、実際の社会の反応を歪め、メディアが作り出した「祝賀一色」の虚像を読者に押し付けていると批判する。
結論
匿名情報は基本的に信用せず、主語が不明な文章や記者の価値判断が混じる表現には注意を払うべきである。双方の言い分を丁寧に聞き、事実の裏付けを取ることが報道の信頼性を高める鍵である。ネットや旧メディアを問わず、発信者の責任感と情報の正確性が求められる時代であることを著者は強調している。
第 4章 ビッグ・ピクチャーをあてはめよ
ビッグ・ピクチャーの視点で事実を再検証する
空間軸と時間軸の拡大による視野の広がり
「ビッグ・ピクチャー」とは、事実Fが発生した際にその出来事を空間軸と時間軸に配置し、広い視野で再検証する手法である。例えば、地球上の出来事は緯度と経度で特定でき、時間は直線的に進むため、これらを組み合わせた座標空間で事実を捉えることが可能となる。ニュースの基本要素「5W1H」のうち、「どこで」と「いつ」がこの考え方に基づいている。
舛添要一と猪瀬直樹の金銭問題の再評価
2016年5月、舛添要一都知事の金銭問題が報じられる中、前任の猪瀬直樹氏が自身の知事時代の経費使用について語った。猪瀬氏は、自身が経費に厳しく、自腹での支出も多かったと述べ、舛添氏の公私混同を暗に批判していた。しかし、時間軸を広げると、猪瀬氏自身も5000万円の選挙資金問題で略式起訴され、有罪判決を受けた過去がある。この視点から見ると、猪瀬氏の発言の説得力は薄れ、倫理的な正当性も疑問視される。
高市早苗大臣の電波停止発言とその背景
2016年2月、高市早苗総務大臣が放送法違反に対する電波停止の可能性を示唆し、報道の自由への介入と非難された。しかし、時間軸を遡ると、2010年の民主党政権下でも同様の発言があったことが明らかになる。当時の総務省副大臣も、法律に基づき電波停止が可能であると述べており、この権限は政権の違いに関わらず存在していた。つまり、この問題の本質は発言内容ではなく、日本の放送行政の制度にある。
放送行政の制度的問題と国際比較
日本では総務大臣が放送免許の許認可権を持っているが、これは他の民主主義国と比べると例外的な制度である。アメリカのFCCやイギリスのOfcomなど、他国では放送行政は政治から独立した機関が担っている。日本でも戦後直後には独立行政委員会「電波監理委員会」が存在したが、1952年に廃止され、再び国家管理に戻された。この制度的背景が、高市発言を巡る議論の本質であり、民主主義の観点から見直しが求められる。
メディア報道の偏りとクロスチェックの重要性
ソニーのウォークマンがiPodを国内販売で上回ったという報道は、表面的にはソニーの勝利と見えるが、実際にはiPhoneの普及やiPodの新製品発表前の買い控えが背景にあった。このように、記事が書いていない事実や前提を疑い、他の情報と照らし合わせるクロスチェックが重要である。読者は報道の表面だけでなく、その背後にある意図や省略された情報に目を向ける必要がある。
報道の自由と情報提供の責任
報道機関やジャーナリストは事実を調べ、読者に提供する責務を負っている。しかし、特定の視点に偏った報道や、重要な情報を省略することで、読者を誤った方向へ導く危険性がある。例えば、福島第一原発事故後の放射線被曝の健康影響に関する報道でも、「科学的に証明されていない」という表現が、実際には「影響があるともないとも断言できない」という事実を覆い隠していることがある。メディアは「わからない」という結論を避けがちだが、それこそが真実を伝える上で重要な姿勢である。
第 5章 フェアネスチェックの視点を持つ
フェアネスとは何か
フェアネスの定義と文化的背景
「フェアネス」とは、人を平等かつ合理的に扱う態度を指す。これはキリスト教文化に根差しており、神が人間の善行と悪行を公平に裁く態度が由来である。西欧の司法制度もこの神の裁きを模しており、裁判官は「judge」と呼ばれ、天秤が公正さの象徴とされる。報道もこの考えを継承しており、フェアネスは「ニュートラル原則」や「インディペンデンス原則」と並び、重要視される。
現実の複雑さとフェアネス
現実には完全な善人も悪人も存在せず、誰もが善悪両方の側面を持っている。このため、実在する人物を一面的に描写することは現実から乖離している。情報のフェアネスは、その記述がどれだけ現実に近いかを示す指標となる。この考え方を「フェアネス・チェック」と呼ぶ。
吉田昌郎所長の描写と報道のフェアネス
福島第一原発事故で現場指揮を執った吉田昌郎所長は、多くの書籍で英雄的に描かれている。門田隆将氏の『死の淵を見た男』では、彼の行動が戦時中の特攻隊と重ねられ、使命感と責任感を持つ勇者として称えられている。しかし、吉田氏は東電本店で原子力設備管理部長を務め、2008年に津波のリスクを示すシミュレーション結果を受け取っていた。彼はこれを軽視し、適切な対策を取らなかったため、結果的に原発事故を招いた責任の一端を担っている。この二面性を無視し、ポジティブな面だけを強調する報道はフェアネスを欠いている。
弘中惇一郎弁護士と「無罪請負人」像
弘中惇一郎弁護士は「無罪請負人」として称賛されるが、彼の過去には消費者金融会社「武富士」の代理人としてスラップ訴訟を担当した経歴もある。これは批判的な報道を封じ込める目的で行われたものであり、フェアな報道とは言い難い。ジャーナリストの江川紹子氏は、弘中氏の業績とともにこの事実も紹介し、バランスの取れた報道を行った。フェアネスの欠如は情報の信憑性を損なうため、ポジティブ・ネガティブ両方の側面を記述することが求められる。
報道における現実の単純化とバイアス
現実は複雑で矛盾に満ちているが、マスメディアは単純化されたストーリーを好む傾向がある。これは視聴率や販売部数を意識した結果であり、取材の労力を省くためでもある。ポジティブまたはネガティブに偏った報道はフェアネスに欠け、現実から乖離している。災害時の日本人の行動を賞賛する報道も、実際には略奪や犯罪が存在していた事実を無視している場合が多い。
情報のフェアネスと報道の役割
報道はフィクションやプロパガンダとは異なり、現実に近い事実を伝える責任がある。フェアネスはそのための重要な手段であり、報道が信頼に足るものであるかどうかのリトマス試験紙となる。ポジティブ・ネガティブ両方の視点を取り入れることで、より現実に近い情報が提供される。
当事者の発言と社会的意義
小保方晴子氏や元少年Aの手記のように、当事者が自身の視点から発言することは社会にとって重要である。これにより、読者は多面的な情報を得ることができ、判断材料が増える。フェアネスを守ることで、情報はより現実に近づき、社会全体の知識の向上に貢献する。
警察・検察報道の問題点
警察や検察による逮捕・起訴ニュースは、一方的に負の情報を強調し、フェアネスに欠けることが多い。逮捕された人の反論や弁護人の意見が欠如しており、これが冤罪事件の温床となる。フェアネスの欠如は報道の質を低下させるため、改善が求められる。
結論
実在する人物や出来事を描く際には、善悪両面を公平に扱うことが求められる。フェアネスは報道の信頼性を保つための重要な要素であり、真実に近づくための方法でもある。ポジティブ・ネガティブ両方の情報に触れることで、読者はより現実的な理解を得ることができる。
第 6章 発信者を疑うための作法
発信者が多すぎる
インターネット時代の発信者の増加と信用性の問題
インターネットの普及により、発信者の数が爆発的に増加した。それに伴い、発言の正確性や信用性が問われるようになった。かつてはマスメディアが発信者を選び、情報の正確性を担保していたが、インターネットでは誰もが自由に情報を発信できる。その結果、発信者の信用性を見極めるのは個人の責任となり、情報の取捨選択が難しくなった。
旧メディアと発信者の選別の役割
旧メディア時代には、新聞やテレビなどのマスメディアが発信者を選び、情報の正確性を担保していた。発信者は主に学者や評論家などの「高リテラシー層」であり、マスメディアの編集責任のもとで発言していた。しかし、インターネットの登場により、この選別機能は失われ、発信者が自らの意志で情報を公開する時代となった。
フォロワー数と信用性の関係
インターネットではフォロワー数やページビュー数などの「注目度」が数値化されるが、それが発言の質や正確性を保証するわけではない。旧メディアもこの注目度を基準に発信者を選ぶようになり、質の低い情報が広まりやすくなった。特に、炎上を狙った過激な発言が注目を集めることが多く、発信者の信用性はさらに曖昧になっている。
引用の正確さで発信者の質を見極める
発信者の信用性を見極める方法の一つとして「引用の正確さ」がある。正確な引用を行っているかどうかは、発信者が事実の正確性にどれだけ注意を払っているかの指標となる。例として、フリーアナウンサーの長谷川豊氏のブログが挙げられ、彼の発言は引用の誤りや誤解を招く表現が多く、結果として信用を失った。
言葉の定義の正確さと議論の質
発信者が使う言葉の定義が正確であるかどうかも重要である。定義の不正確さは議論の混乱を招き、事実の歪曲につながることがある。特に社会的な論点に関わる場合、正確な定義を確認することが発言の質を保つ鍵となる。
発信者の経歴と専門性の確認
発信者の専門性や過去の著作を確認することで、その情報の信頼性を判断できる。アマゾンなどで著者の略歴や著作をチェックすることは有効な手段である。また、著作が多く、一定の知的作業を経ている発信者は信頼性が高い傾向にある。
専門家の発言の信用性と利害関係
専門家とされる人物の発言も常に中立で正確とは限らない。特に福島第一原発事故の際には、専門家とされる人物が誤った情報を断定的に発信した例が多く見られた。これは、専門家自身が利害関係や立場に影響されていることが一因である。
ステルスマーケティングと発信者の透明性
ステルスマーケティング(ステマ)は、発信者が広告であることを隠して情報を発信する行為である。特にビューティー・コスメ業界などではステマが常態化しており、読者は発信者の背後にある利害関係を見抜く必要がある。欧米ではステマは違法行為とされているが、日本では依然として野放しの状態である。
発信者の選別と情報の信頼性
情報の信頼性を判断する際には、媒体よりも発信者個人の質に注目すべきである。信用できる発信者を見つけ、その人の情報を追いかけることが重要である。発信者の経歴や過去の発言、著作を確認することで、信頼性の高い情報を選別することができる。
第 7章 情報を健全に疑うためのヒント集
妄想に満ちた世界と記者の経験
日常の情報提供と妄想的な主張
三重県で新聞記者を務めていた筆者のもとには、読者から様々な情報提供が寄せられた。巨大カボチャの収穫や珍しい動物の発見といった話題もあったが、中には「世界連邦の総裁に就任した」という中年男性からの発表も含まれていた。この男性は弁護士を雇い、記者会見まで開いたが、地元では精神疾患を抱える人物として知られていた。彼の主張は真実と信じ込まれており、悪意はなかった。同様に、「時間の流れを撮影した」という男性や、「嫁に殺される」と訴える女性も現れ、筆者はこうした情報提供者と接する中で妄想性障害に興味を持つようになった。
妄想性障害の理解とそのパターン
精神医学の知識を深める中で、筆者は妄想性障害が誇大妄想や被害妄想と分類されることを知った。世界連邦総裁や時間の流れを撮影した男性は誇大妄想、嫁に殺されると訴える女性は被害妄想に該当する。被害妄想が進行すると、逮捕や誘拐、偽者の家族といった話に発展することが多い。このような妄想には一定のパターンが存在し、筆者の元には後年も「裁判官が偽者だった」「FBIに逮捕された」という訴えが寄せられたが、経験を積んだ筆者は騙されることがなくなった。
ネット社会と妄想の拡散
30年が経過し、筆者はネット上でかつて見た妄想性障害に似た話を頻繁に目撃するようになった。新聞やテレビでは簡単に記事にされないが、ネットではそのまま拡散され、信じる人々も現れる。筆者はネットでこうした話を目にした際、妄想性障害の可能性を念頭に置くよう助言している。妄想的な主張は笑い話ではなく、報道のプロですら騙されることがあると警告している。
陰謀論への警戒
陰謀論の実例とその影響
陰謀論もネット上で頻繁に見られる。例えば、「フリーメーソンが大戦を引き起こした」「ユダヤ国際金融の陰謀」といった主張が広がっている。1995年には医師の西岡昌紀氏が「アウシュビッツにガス室はなかった」と主張し、雑誌『マルコポーロ』が廃刊に追い込まれた事件もあった。筆者はこの事件を取材し、陰謀論がいかに現実に影響を与えるかを目の当たりにした。
陰謀論の構造と特徴
陰謀論には「ほんの少しの事実に大量の空想が混ざっている」という特徴がある。陰謀論者は、自分たちが被害を受けたと信じるときのみ陰謀を主張し、その証拠がない場合は「隠蔽された」と説明する。このような主張は、存在を証明することも否定することもできないため、いつまでも生き延びる。筆者は陰謀論に耳を傾けることは無駄であると断言している。
企業や政府のプロパガンダに対する警戒
電通事件と報道の矛盾
2015年、電通の女性新入社員が過労自殺し、労災認定された事件が報じられた。電通は午後10時の一斉消灯を実施したが、筆者は現場で再び明かりが灯る様子を目撃した。この一斉消灯はメディア向けのプロパガンダであり、実際の労働環境の改善とは無関係であった。筆者は、企業の宣伝に基づいた報道を疑う姿勢の重要性を強調している。
組織のルールと行動の理解
法律と規則の重要性
筆者は取材活動を通じて、組織の行動を理解するためにはそのルールや法律を知ることが重要だと学んだ。福島第一原発事故の原因を探る際も、事故対応マニュアルや関連法規を調べることで対応の適切さを評価できる。法律は社会全体に影響を与え、行動や生活様式を変えるため、社会の変化を理解するためには法律の施行や改正を確認する必要がある。
福島第一原発事故と法律のギャップ
福島第一原発の津波被害の背景には、当時の国の立地ルールが存在しなかったことがあった。東電は国の規制が整う前に立地を決め、津波への備えも不十分だった。この事実を知った筆者は、原発の脆弱性の理由を理解した。また、福島第一原発事故後の避難命令の遅れも、法律の重複による判断の迷いが原因であったと指摘している。
メディア情報の取捨選択と事実の見極め
発問のゴールを明確にする
筆者は福島第一原発事故報道の中で、重要な論点が埋もれてしまうことに気づいた。メルトダウンの有無よりも、放射性物質がどの程度拡散しているかが住民にとって重要だった。このように、自分が何を知りたいのかを明確にし、情報の重要性を見極める姿勢が必要であると筆者は述べている。
事実の全貌は時間が必要
重要な事実は時間をかけて徐々に明らかになる。福島第一原発事故に関する報道も、初期のニュースから書籍、政府報告書と情報が積み重なって全体像が見えてきた。筆者は短期間で結論を出さず、全貌が明らかになるまで待つことの重要性を強調している。
ロジックの逆転とXファクターの探求
前提を逆にすることで見える真実
筆者は福島第一原発事故の分析において、「政府の規制があった」という前提を逆にし、「政府の規制がなかった」と考えることで、ずさんな津波対策の理由を理解した。また、「全交流電源喪失は30分で回復する」という規制が存在していたことが、事故の背景にあったことも突き止めた。このように、腑に落ちない点がある場合は「Xファクター」を探し、合理的な説明を見つけ出すことが重要である。
断言の強さと事実の関係
断言の強さは正確さと無関係
福島第一原発事故の初期には、「メルトダウンなんてありえない」といった強い断言がネット上に溢れていた。しかし、これらの主張は後に完全な誤りであることが判明した。筆者は、どれほど強く断言されても、それが事実に基づいていなければ信じる必要はないと結論づけている。重要なのは断言の強さではなく、事実そのものである。
同著者の書籍




その他ノンフィクション

Share this content:
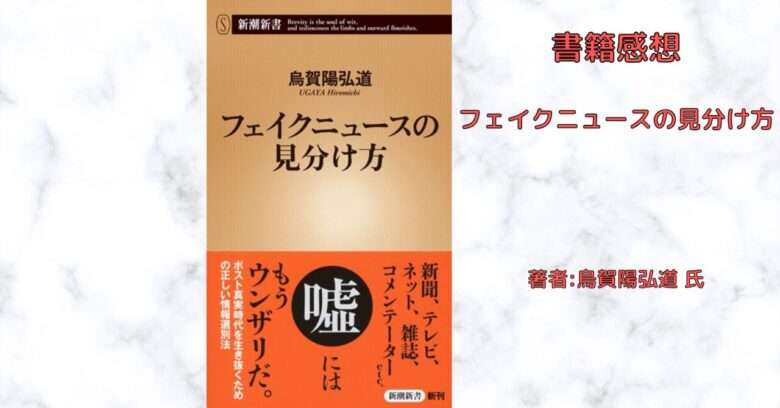

コメントを残す