どんな本?
『ALPS水・海洋排水の12のウソ』は、ジャーナリストの烏賀陽弘道氏が、福島第一原発事故後の政府の情報発信に対し、12の誤りを指摘するノンフィクション作品である。著者は震災直後から現地取材を続け、その経験を基に政府の主張を批判的に検証している。
書籍の特徴
本書は、政府が発信する「海洋排水しか方法はない」「タンクの置き場はもうない」「ALPS水に放射性物質はトリチウムしか残っていない」などの主張に対し、著者がそれらを「真っ赤なウソ」として徹底的に指摘している点が特徴である。公開直後から17万再生された動画を基に緊急出版された本書は、他の作品とは一線を画す鋭い視点と深い洞察を提供している。
出版情報
• 出版社:三和書籍
• 発売日:2023年11月10日
• ISBN:978-4-86251-524-7
• 価格:1,500円+税
• ページ数:176ページ
読んだ本のタイトル
ALPS水・海洋排水の12のウソ
著者:烏賀陽弘道 氏
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
★日本政府の12のウソを徹底的に指摘!
★福島第一原発を震災直後から取材し続ける著者による告発
★公開直後から17万再生された動画をもとに緊急出版
「海洋排水しか方法はない」、「タンクの置き場はもうない」、「ALPS水排水は被災地の復興に必要」、「ALPS水に放射性物質はトリチウムしか残っていない」、「福島第一原発のような原発からの海洋排水は世界中でやっている」、「日本政府の基準を満たしているから安全だ」などなど……
2023年8月24日、日本政府は福島第一原発からでた汚染水を「ALPS」で浄化した、いわゆる「ALPS処理水」を海洋放出した。ALPSで処理した水は安全で、環境に対する影響はないと発信している。
「真っ赤なウソです。信じないでください」
著者は、政府が発信する情報にはウソがあるとして、海洋放出の翌々日、動画を公開した。動画は反響を呼び、1か月経つころには17万回再生された。
本書は、動画で話した内容に大幅な加筆修正を施し、一冊にまとめあげた。
感想
3.11から本格的に表面化した日本の劣化。
それを誤魔化そうと詭弁を駆使する政府とマスメディア。
そして今回の福島第一原発の事故の対応のために発生した汚染水を多少マシにしたALPS水を海洋に放出している東電の対応から見える間違いを指摘している本書。
先ずはコレを念頭に置いておく。
原子力発電所事故時の防護の鉄則
・核分裂反応の停止
・核燃料の冷却
・放射性物質の閉じ込め
福島第一原発には、メルトダウンによって溶け落ちた合計880トンの核燃料デブリが存在する。
このデブリは高線量の放射線を放ち続けており、冷却のために使用された水が汚染水として排出される。
ALPS(多核種除去設備)は、この汚染水を処理する装置であるが、完全に放射性物質を除去するものではない。
そのALPS水が満タンになり海洋に放水しているのが現状。
『国内問題だった放射性物質汚染を国際問題に拡大した』
「海洋排水しか処理方法はない」
海洋排水という政策の誤り
福島第一原発から排出されたALPS水を海洋に放出するという日本政府の決定は、国際政治上最悪の選択であった。
海洋は国際法によって全ての国が共有する財産とされており、この公共の場に廃棄物を捨てる行為は国際社会全体に影響を及ぼす。
これまで福島第一原発事故の放射性物質汚染は国内問題にとどまっていたが、海洋放出によって国際問題化し、全ての国が意見を表明する権利を得る結果となった。
日本政府がALPS水の安全性をどれほど主張しても、他国がそれを受け入れる義務はない。
日本政府は、福島第一原発の汚染水を海洋に放出する以外に方法がなかったと主張したが、これは事実ではなかった。
少なくとも二つの陸上処理方法が存在していた。
一つ目は「自然蒸発」であり、これは1979年のスリーマイル島(TMI)原発事故で実際に採用された方法である。
TMIでは9,000トンの汚染水を蒸発させ、残留した放射性物質を固化して隔離保存した。
福島第一原発でも、事故発生から12年間でこの方法を適用すれば、汚染水の量を大幅に減少させることが可能であった。
政策の遅れと対策の不備福島第一原発事故後、経済産業省が汚染水処理の検討を開始したのは事故発生から2年9か月後の2013年12月であった。
この遅れは、初期対応の不備を示しており、汚染水対策の開始が遅れたことが結果的に海洋排水の必要性を強調する根拠となってしまった。
コンクリート固化という現実的代替策もう一つの選択肢は「コンクリート固化」である。
この方法では、汚染水にセメントを混ぜて固体化し、陸上に安全に保管する。
実際、福島第一原発の放射性廃棄物の処理にはすでにこの方法が採用されており、「リプルンふくしま」施設では固形化された廃棄物が埋め立てられていた。
それにも関わらず、政府は汚染水処理にこの方法を採用しなかった。
福島第一原発からのALPS水海洋排水は、人類史上初の試みであり、放射性物質の環境中での拡散については前例がなかった。
TMIやチェルノブイリの事故では、汚染水はすべて陸上で処理されており、海洋放出は行われていない。
福島第一原発の海洋排水は、国際問題化し、長期的な外交的リスクを伴う結果となった。
最終的に、海洋放出が選ばれたのはコストと時間を優先した結果であった。
しかし、この判断は放射線防護の原則に反し、国際社会を巻き込む大きなリスクを伴うものであった。
陸上処理を優先して国際問題化を防ぐべきであり、政府の選択は賢明とは言えない結果となった。
/(^o^)\オワタ
今の政府の体質だと誰も責任を取らないな、ロシアンルーレットのように、その時の大臣が責任を取る程度かもしれない。
「タンクの置き場はもうない」
福島第一原発の敷地面積は約3.5平方キロメートルと限られているが、原発周囲には約16平方キロメートルに及ぶ広大な中間貯蔵施設が存在している。
4300人の住民が立ち退かされた場所である。
広大な空き地が存在するにもかかわらず、政府と東京電力はこの土地を活用せず、「福島第一原発敷地内のみが満杯である」という前提で海洋排水を進めた。
経済産業省は、中間貯蔵施設が環境省の管轄であることを理由に協議を避けたが、同じ日本政府内での調整がなされなかったことは不可解であった。
多くの国民は、メディア報道により「汚染水タンクの置き場所がない」と信じ込まされていた。
新聞やテレビは、福島第一原発構内のタンクが密集した映像ばかりを報道し、広大な中間貯蔵施設の存在を意図的に無視した。
これは「フレーミング効果」による認識誘導であり、政府と東電の意図に沿った形で世論を操作した結果であった。
「ALPS水排水は被災地の復興に必要だ」
2023年8月24日、岸田文雄総理はALPS水の海洋排水開始に際し、ツイッターで声明を発表した。
「ALPS処理水の放出が福島第一原発の廃炉に向けた歩みであり、被災地復興の新たな一歩である」と述べた。
しかし、この発言には明白な虚偽が含まれていた。
ALPS水の排水は福島第一原発構内のタンクを減らすだけであり、原発外の被災地復興とは一切関係がなかった。
ALPS水の排水によって減少するのは、福島第一原発の敷地内(約3.5平方キロメートル)に設置されたタンクのみである。
一方、放射性物質の影響を受けた被害地は原発を中心に半径20キロメートル、約628平方キロメートルに広がっており、事故当時約96,541人が生活していた。この広大な被害地に対して、原発構内のタンクが減少したところで、復興には何の影響も及ぼさない。
さらに、2023年8月24日、岸田文雄総理はALPS水の海洋排水開始に際し、「福島第一原発の廃炉に向けて歩まなければならない道」と述べた。
しかし、この発言は明らかな虚偽であった。
廃炉の完了は、メルトダウンした核燃料デブリを3基の原子炉から完全に取り出し、安全に隔離・処分することによって達成される。
ALPS水を海洋に排水しても、デブリの除去作業には全く影響を及ぼさない。
デブリは現在も崩壊熱を発し続けており、冷却のために水をかけ続けなければならない。
この冷却水が汚染水となり、ALPSで処理された後に排水される。
しかし、どれだけALPS水を海に排水しても、デブリ自体の状態は一切変わらない。廃炉作業の核心は、このデブリを安全に取り出し処分することであり、排水はその過程に直接関与しない。
岸田総理の発言は単なる美辞麗句では済まされない。
一国の総理大臣の発言は国内外に大きな影響を及ぼし、世界に誤った認識を広める可能性がある。
ALPS水の排水が安全であったとしても、それを被災地復興、廃炉と結びつけるのは誤導であり、意図的なディスインフォメーションとみなすべきである。
/(^o^)\オワタ
「ALPS水を海洋排水すればタンクはなくなる」
タンクの全撤去は不可能
ALPS水を海洋排水すれば、福島第一原発の敷地に並ぶタンクが全て消えると誤解している人が多い。しかし、実際には海洋放出可能なALPS水は全体のわずか33%に過ぎなかった。つまり、海洋排水を行ってもタンクの3分の2、67%は依然として残ることになる。排水基準を満たさない高濃度汚染水残るタンクの多くは、日本政府が設定した排水基準すら満たさない高濃度の放射性物質を含んでいた。そのため、これらの汚染水は海洋放出が不可能であった。日本政府自身が制定した基準が障壁となり、全ての汚染水を処理することは現実的ではなかった。
_| ̄|○ オワタ
「風評被害をなくすことが必要だ」
2023年8月24日、ALPS水の海洋排水開始と同時に外務省は声明を発表した。
その内容は「最初の一滴の放出が始まったこの日から、最後の一滴の放出が終わる日まで責務を果たす」というものであり、戦時体制を思わせる強い表現であった。
しかし、海洋放出可能なALPS水は全タンクの33%に過ぎず、残りの67%は高濃度汚染水であり排水不可能であった。
この矛盾は、政府が自信を持つはずの安全基準を国際機関の権威で補強しようとする姿勢からも読み取れた。
「風評被害」の定義とプロパガンダの構造外務省の声明には「#STOP風評被害」というハッシュタグが付され、「風評被害」が撲滅すべき悪として位置づけられていた。
この表現は「我々の取り組みを正しく理解しない者は誤っている」というメッセージを含み、日本政府の主張に同意しない勢力を加害者とする対立構造を作り上げていた。
これは典型的なプロパガンダの手法であり、「善と悪」「被害者と加害者」という単純な二元論を通じて世論の誘導を試みていた。
( ̄▽ ̄)オワタ
「ALPS水に放射性物質はトリチウムしか残っていない」
「ALPS処理水にはトリチウム以外の放射性物質が含まれていない」とする政府やマスコミの主張は誤りであった。
実際にはセシウム137やストロンチウム90を含む複数の放射性物質が残留している。
東京電力の公開データによれば、2023年6月30日時点で1リットルあたり0.1~1ベクレルのセシウム137が確認されている。
この事実は、東電の「廃炉資料館」でも確認され、東電職員もその存在を認めていた。
メディアの誤報と政府のプロパガンダ新聞・テレビ各社は「ALPS水=トリチウム水」と誤った情報を広めており、産経新聞が66件、毎日新聞が49件と、多数の誤報が確認された。
この背景には経済産業省が公表した「トリチウムしか残留していない」という誤った情報がある。
メディアはこれを十分に検証せずに報道し、結果として国民の誤解を助長した。
「福島第一のような原発からの海洋排水は世界中でやっている」
福島第一原発と世界の原発の排水処理の違い
健全炉と事故炉の排水処理の違い世界の健全炉(事故を起こしていない原子炉)では、核燃料棒に直接触れた水は密閉されたループ内を循環し、絶対に外部に放出されない。この水は高レベルの放射性物質を含むため、廃炉や点検時に取り出された場合も固体化され、厳重に保管される。一方、福島第一原発のような事故炉では、メルトダウンした燃料デブリを冷却するために直接水をかけ、その水をALPS(多核種除去設備)で処理した後に海洋へ排出している。このような排水方法は世界中で福島第一原発のみである。
_| ̄|○ オワタ
「日本政府の基準を満たしているから安全だ」
政府のALPS水安全基準とその問題点
放射性物質残留と政府の基準
政府がALPS処理水の海洋排出を許可した理由は、「基準値以下だから」であり、「放射性物質がゼロだから」ではなかった。ALPS水にはトリチウム以外の放射性物質も残留しているが、それらが政府の定めた濃度規制値を下回っているため、安全と判断された。
具体的には、各放射性物質の濃度を規制値で割り、その結果を足し合わせた「告示濃度比総和」が1以下であれば排出が許可される。この基準は人体の被曝許容量をもとに設定されており、環境への影響は考慮されていない。告示濃度比総和の計算方法とその曖昧さ告示濃度比総和は、経口摂取による内部被曝のみを基準にしており、呼吸器からの吸入被曝や外部被曝は無視されている。また、放射線の種類(α線、β線、γ線)や臓器ごとの感受性の違いも考慮されていない。これはもともと放射性廃棄物を扱う作業員向けの基準であり、一般公衆や環境への影響を正確に評価するものではなかった。この基準をもとに「ALPS水は飲んでも安全」とする政府の主張は、前提と結論を誤って逆転させたものである。
毎日ALPS水! /(^o^)\ オワタ
「希釈して排水するから安全だ」
希釈による安全性の誤解
希釈の限界と放射性物質の持続性
東電および日本政府は「希釈して排水するから安全」と主張したが、自然環境には放射性物質を消す力が存在しない。希釈によって放射性物質の総量は減少せず、人間が被曝する確率が一時的に下がるだけであった。放射性物質は移動し続け、時間が経つほど人類がそれに遭遇する確率は高まる。特にセシウム137やストロンチウム90の隔離期間は1万5千年に及び、希釈による短期的な効果は長期的には無意味となる。
「環境への影響は長期的に見ても無視できる」
海洋放出と生物濃縮の影響
マグロの回遊と放射性物質の拡散
マグロは生涯泳ぎ続ける回遊魚であり、福島県や他の地域の境界を意識することはない。放射性物質を含む水域を通過したマグロが、カナダやチリで捕獲される可能性は現実的であった。既にUNSCEARの2022年報告ではカナダでの放射性物質の検出が報告されており、太平洋沿岸国で福島第一原発由来の放射性物質が確認される可能性は高いと考えられる。
生物濃縮と食物連鎖の影響
放射性セシウムが海底に沈殿すると、それをプランクトンが摂取し、次第にクラゲやミジンコ、イワシやタコ、さらにはサバやヒラメ、最終的にはマグロなどの大型魚へと濃縮されていく。この現象を生物濃縮と呼び、人間は食物連鎖の頂点に立つため、最も高濃度の放射性物質を摂取することになる。日本政府はALPS処理水が海洋生物に与える影響についてのシミュレーションや評価を行っておらず、実測データも存在しないため、影響は未知数であった。
行って無いんかーーい!
_| ̄|○ オワタ
ホントに、、
ロクな事をしない。
自国内で処理出来たのに、世界に粗相をして国内ではプロパガンダで隠蔽し、それにマスメディアが協力しているとは。
革命を知らない国民性にも絶望感しかない。
コレは衰退するわけだ。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
同著者の書籍




その他ノンフィクション

Share this content:
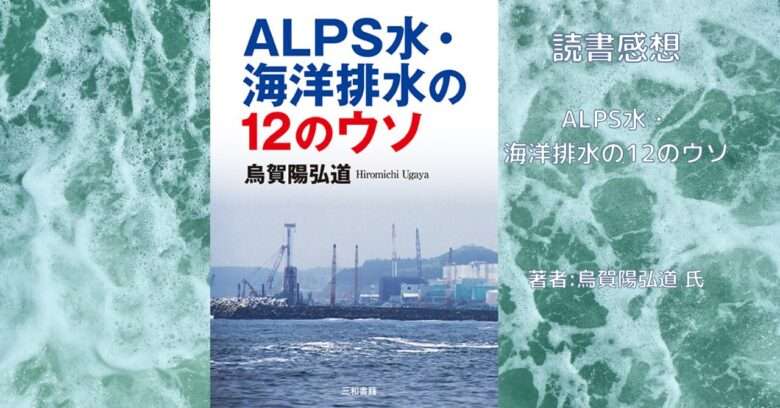

コメントを残す