どんな本?
本書は、現代社会におけるプロパガンダの手法とその影響を分析するノンフィクション作品である。メディアや政治、広告など、日常生活の中で知らず知らずのうちに受けている情報操作の実態を明らかにし、読者がそれらを見抜くための方法を提供する。具体的な事例や歴史的背景を交え、プロパガンダのメカニズムを解説している。
著者
• 著者:烏賀陽弘道(うがや・ひろみち)。1963年生まれ。京都大学経済学部卒業後、朝日新聞社に入社。名古屋本社社会部や「AERA」編集部勤務を経て、2003年に退社。以降、フリージャーナリストとして活動し、メディアリテラシーや報道の在り方について多くの著作を執筆している。
物語の特徴
本書の特徴は、理論的な解説だけでなく、具体的な事例を豊富に取り上げている点である。ニュース報道、政治キャンペーン、広告など、身近な例を通じてプロパガンダの手法を解説し、読者が日常生活で情報を批判的に受け取る力を養うことを目的としている。また、各章末にはチェックリストや実践的なアドバイスがまとめられており、読者がすぐに活用できる内容となっている。
出版情報
出版社:新潮社
発売日:2025年2月15日
ISBN:978-4-10-611079-5
定価:1,056円(税込)
ページ数:256ページ
判型:新潮新書
関連メディア展開:著者による講演会やオンラインセミナーが定期的に開催されている。
読んだ本のタイトル
プロパガンダの見抜き方
著者:烏賀陽弘道 氏
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
政治家、官僚、企業、インフルエンサーetc. ──思考を操られないための必読書。全手口暴露!
日々見聞きするニュース、SNS経由の“真実”、皆に愛される「ゆるキャラ」、評判の映画、国家的規模のイベント……発信されるあらゆる情報の裏にある意図と目的を見抜けないと、知らないうちに思考や行動は誘導されていく。それがプロパガンダ3・5時代の現実だ。常に情報戦の最中にいる私たちは何を知っていればいいのか。古今の成功例、巧みな手口、定石等を示しながら、具体的な「見抜き方」を伝授する
感想
あとがきの一部からの要約。
原発事故と安全神話
東日本大震災以前、日本の大半の人々は「原発事故は日本では起こり得ない」と考えていた。
私もその1人だった。
スリーマイル島やチェルノブイリでの事故を「遠い国の出来事」と捉え、電力産業が発信する「安全神話」を無批判に受け入れていた。
その結果、原発事故の危険性を警告する声は少数派として扱われた。
そもそもそんな話がある事自体知らなかった。
しかし、実際には「巨大地震 → 津波 → 冷却電源の喪失 → メルトダウン」という単純なプロセスで福島第一原発は崩壊し、大量の放射性物質が放出された。
自身の地域もホットスポットと呼ばれていた。
現状がそんなに変わらないのに、終わった事になり、現在は子育てしやすい場所となっている。
コレもプロパガンダの一種だろう。
事故後、多くの人が「なぜ、これほど単純な事実に気づけなかったのか」と後悔することになった。
本当にそれ!
世界的に高額なの電気代を支払い、それを原資に原発は安全だとプロパガンダを流布されていた。
そんな危険な事に2度とハマりたくないと思い注意しながら生活しているが、、
知らない間にプロパガンダにハマってる事が散見される。
気を付けていてもそうなってしまう自身のアホさに呆れながらも、二度と原発事故のような絶望感は味わいたくないと思いながら注意して世間を穿って見てるが上手く行かない。
そのための参考になればとこの本を手に取り読んだ。
最初はプロパガンダの歴史。
あぁ、宗教勧誘もプロパガンダか、、
言われてみればそうだもんな。
そのせいで十字軍のような戦争が起こり、同じ宗派でも30年戦争なんて物も起こったりしていた。
現在でもガザ地区を中心に虐殺が行われている。
それが、異教徒は人間じゃないというプロパガンダが利用されているようだ。
本当に信じてる奴居るのかと思うが、、
宗教的な戦争ではよくある話しでもある。
近年だとドイツのナチスだが、元祖はアメリカ、イギリスだったとは、、
大衆の望む事、特に見捨てられたと思ってる人たちにへの起爆剤としてプロパガンダは非常に有用ではあるが、、
それを扇動する側の利益に利用されてると思うと非常に面白くない。
そういうのを理解しながらも動くなら多少は良いのだろうが、自身のアホさを考えるとそう上手く動けるわけが無いと思ってる。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
備忘録
序 章 なぜ見抜く技術が必要なのか
新人時代のプロパガンダとの遭遇
新米記者として津市に赴任した著者は、取材依頼の山に直面した。企業や役所から毎日のように届く「お知らせ」を精査し、広告的なものを排除するのが新人の最初の仕事であった。ある日、農業用水の完成視察の取材に出向いたが、写真の撮り方ひとつで記事の印象が変わることを痛感した。町長を主体に撮影した写真が上司に却下され、「住民が要望を伝える姿」を撮るべきだと指導を受けた。この経験は、報道が行政ではなく市民のためにあるという基本姿勢を学ぶ重要な教訓となった。
プロパガンダに利用されない報道の原則
記者としての経験を重ねる中で、著者は報道がいかにプロパガンダの影響を受けやすいかを実感した。政府や企業は、広告よりもニュースとして報道されることで宣伝効果を高めようとする。そのため、記者は「情報が掲載に値するか」を厳密に判断する能力を求められる。報道の基準は読者の利益を優先し、企業や役所の都合に左右されないものでなければならなかった。
現代社会とプロパガンダの不可避性
新聞社を辞めてフリーランスになった後も、著者はプロパガンダと無縁ではいられなかった。情報の発信手段が多様化し、SNSの普及によって個人が発信するプロパガンダも増加した。街には広告が溢れ、インターネット空間も宣伝で埋め尽くされている。このような環境では、プロパガンダを完全に避けることは不可能であり、それを見抜くリテラシーが不可欠となる。著者は、記者として培った経験をもとに、プロパガンダを識別する方法を読者と共有することを本書の目的とした。
プロパガンダの定義と影響
プロパガンダとは、発信者が意図的に受信者の思考や行動を誘導する情報であり、その意図は表面上は隠されていることが多い。発信者は政府や企業だけでなく、個人がSNSを通じて拡散する場合もある。プロパガンダの影響を受けないためには、受け取る情報の背後にある意図を常に疑う習慣を持つことが求められる。
五輪とプロパガンダの関係
オリンピックはスポーツの祭典であると同時に、開催国のプロパガンダの場でもある。北京五輪では「復興五輪」という名のもと、震災の被害者を聖火ランナーとして起用し、国際的な非難を逸らす手段として利用された。東京五輪でも同様に「復興五輪」の名のもと、震災被害者をランナーに選び、原発事故の記憶を薄める意図があった。美談として語られるこうした物語は、感情を揺さぶることで異議を唱えにくくする効果を持つ。
ゆるキャラとプロパガンダの手法
行政が積極的にプロパガンダに利用している例として、「ゆるキャラ」の成功が挙げられる。かつて無味乾燥だった地方行政にキャラクター性を与え、観光誘致や地域振興に活用した。くまモンやひこにゃんといったキャラクターは、自治体そのものを擬人化し、広告としての機能を果たしている。これにより、行政の無機質なイメージが和らげられ、親しみやすい存在へと変化した。
プロパガンダ・キャラクターの活用
現代のプロパガンダでは、影響力のある「キャラクター」が重視される。環境活動家のグレタ・トゥーンベリや香港の民主活動家・周庭のように、若い女性が象徴的存在として登場することが多い。彼女たちは視覚的に注目されやすく、社会変革の象徴として受け入れられやすい。これは、若い女性が「未来」や「変革」を象徴する存在として機能するためである。
物語の力とプロパガンダの影響力
人間は物語に引き込まれやすく、それを通じて現実を理解しようとする。この心理を利用し、プロパガンダは「感動的な物語」を作り出すことで社会の認識を操作する。歴史上の成功したプロパガンダも、共通して強い物語性を持っていた。例えば、聖火リレーはもともとナチス・ドイツが考案したもので、国威発揚のためのプロパガンダイベントであった。現代においても、物語の力を利用した情報操作はさまざまな場面で見られる。
プロパガンダの普及とその影響
プロパガンダはウイルスのように広まり、社会全体の認識を形成する力を持つ。経済のバブルや政治的キャンペーンは、多くの人が同じ物語を信じることで成り立つ。情報が「ヴァイラル化」する過程は、ウイルスの感染と同様に急速かつ広範に広がる。そのため、プロパガンダの影響を受けずに判断するには、情報の背後にある意図を見極める力が必要である。
まとめ
プロパガンダは避けることのできない存在であり、それを見抜くリテラシーが求められる。美談や感動的な物語は、社会の認識を誘導するために利用されることが多い。本書では、情報に対する疑う視点を持ち、プロパガンダに惑わされない思考力を養うことを目的としている。
第 1章 どう生まれ、どう発展したか──プロパガンダの歴史
カトリックとプロパガンダの関係
プロパガンダという言葉は、もともとカトリックの布教活動に由来する。1622年、ローマ教皇グレゴリウス十五世が「布教聖省(Sacra Congregatio de Propaganda Fide)」を設立し、カトリックの教えを広めるための省庁とした。この組織は1967年まで存続し、その後「福音宣教省」に改称された。2022年には教皇自らがトップを務める筆頭省に昇格し、依然としてローマ教皇庁の最重要機関の一つであった。
宗教改革とカトリックの対抗策
1517年にマルチン・ルターが宗教改革を開始すると、ドイツやオランダを中心に新教徒が増加した。これに対抗するため、カトリック教会はイエズス会を設立し、新教徒をカトリックへ回帰させる活動を展開した。しかし、三十年戦争(1618~1648年)の影響でヨーロッパ全土が混乱し、布教の移動が困難になった。そこで、ローマ教会は布教聖省を設置し、組織的な布教活動を強化した。
プロパガンダの本来の意味
プロパガンダという言葉は、本来「福音を広める」「布教」「伝道」という意味のラテン語に由来する。カトリック文化圏では、プロパガンダには「これは素晴らしいものですよ」と勧める肯定的な語感が含まれていた。政治や経済を問わず、良い知らせを広める行為として認識されていた。しかし、20世紀に入ると、政府や企業の宣伝という意味合いが強まり、現在のようなネガティブな語感が定着した。
キリスト教とプロパガンダの関係
キリスト教には、福音を広めることが信者の義務とされる教義があった。イエス自身が「私の教えを広めよ」と述べており、その伝統は宗派を問わず受け継がれた。聖書は、福音を広める手段として活用され、伝道活動の中心的な役割を果たした。
宗教改革と印刷技術の影響
1517年、マルチン・ルターが「95か条の論題」をヴィッテンベルク城教会の門に貼り出し、ローマ教会の免罪符販売を批判した。この文書は活版印刷によって広まり、庶民でも読めるようにドイツ語に翻訳された。ローマ教会を公然と批判する文書が庶民の言葉で書かれたことは革命的であり、大衆の支持を得る要因となった。こうして、宗教改革はプロパガンダの成功例の一つとされた。
識字率の向上と印刷メディアの普及
プロパガンダの成立には、識字の普及が不可欠であった。識字率が向上することで、大衆が情報を理解し、共有することが可能となった。19世紀には各国で義務教育が導入され、識字人口が増加した。新聞も普及し、大衆向けのメディアが発展した。こうして、印刷メディアを利用したプロパガンダが確立された。
国家プロパガンダの誕生
ナチス・ドイツのプロパガンダは有名だが、その手法の多くはアメリカやイギリスの戦時宣伝から学ばれた。第一次世界大戦中、アメリカでは「公共情報委員会(CPI)」が設立され、プロパガンダ活動を展開した。CPIに雇われたエドワード・バーネイズは、精神分析学を応用したプロパガンダ技術を確立し、後に「PR(Public Relations)の父」と呼ばれた。
広告とプロパガンダの関係
バーネイズは、広告や宣伝活動にもプロパガンダ技術を応用した。例えば、プロクター・アンド・ギャンブル社の「アイボリー石鹸」を宣伝するために、全国規模の「石鹸彫刻コンクール」を開催し、大衆の関心を引いた。こうした手法は、商業広告だけでなく、政治プロパガンダにも応用された。
ナチスとアメリカのプロパガンダ手法
ナチス・ドイツのプロパガンダは、アメリカの手法を参考にしていた。ヒトラーは『わが闘争』の中で、イギリスやアメリカの戦時宣伝を評価し、それを模倣する重要性を説いた。ナチスの宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスも、ソ連共産党のプロパガンダに注目し、映画やラジオを活用した大衆操作を行った。
建築とプロパガンダの関係
建築もプロパガンダの一環として利用された。ナチス・ドイツやソ連では、巨大建築物を用いて権力を誇示し、国民に統一されたイメージを植え付けた。アメリカのワシントンD.C.も、記念碑や建築を活用し、民主主義の象徴として機能させた。日本でも、明治政府が西洋風の建築を各地に建設し、文明開化の象徴として活用した。
現代のプロパガンダとその影響⭐︎
プロパガンダは、広告や政治活動だけでなく、文化や教育、イベントなど様々な形で展開される。音楽や映画、スポーツイベントもプロパガンダの手段として用いられる。現代では、SNSやインターネットを活用したプロパガンダが主流となり、大衆の意識形成に大きな影響を与えている。
第 2章 現代日本人は何に乗せられたか──成功した 2例の研究
アメリカ流プロパガンダが日本を変えた「郵政民営化」
郵政民営化とプロパガンダ戦略
小泉純一郎総理による「郵政民営化」は、戦後日本で最も成功した政治プロパガンダの一つであった。法案の提出から否決、解散、総選挙、圧勝、そして可決へと至る過程には、周到な戦略が存在していた。その中心人物は、当時若手議員であった世耕弘成である。彼はNTTの広報部出身であり、アメリカ流のPR戦略を修得していた。世耕氏は「広報はプロジェクトマネジメントである」と述べ、政策の実現には国民の支持を得ることが不可欠であると考えた。
広報戦略とキャッチフレーズ
2005年の郵政解散総選挙において、世耕氏は自民党広報本部長代理として広報戦略を指揮した。小泉総理は「広報が重要だから、お前がやれ」と直接指示し、「改革を止めるな」というキャッチフレーズを決定した。世耕氏は自民党内の宣伝部門を統合し、PR会社「プラップジャパン」と連携して効果的な情報発信を行った。結果、自民党は大勝し、郵政民営化法案は成立した。
シンプルなメッセージの反復
成功の鍵は、シンプルなメッセージの繰り返しにあった。「郵政民営化こそ、すべての改革の本丸」といったスローガンは、具体的な説明を省きながらも国民に浸透した。人間は繰り返し聞かされると、その内容を深く考えずに受け入れる傾向がある。世耕氏はこの手法を駆使し、「改革を止めるな」とのフレーズをポスターやCMで何度も提示した。
二者択一の手法
郵政民営化の争点化においても、世耕氏は「イエスかノーか」の単純な問いを繰り返した。これにより、国民は複雑な背景を考えることなく、自民党の改革路線を支持するか否かの判断を迫られることになった。この「二進法アルゴリズム」とも呼ばれる手法は、思考を誘導するプロパガンダの常套手段である。
望月衣塑子記者というリアリティ・ショー
調査報道記者としての望月衣塑子
望月衣塑子記者が広く知られるようになったのは、2017年に菅義偉官房長官の会見に参加し始めた頃である。しかし、彼女の名前が注目される以前から、調査報道記者としての実績があった。2016年に出版された『武器輸出と日本企業』では、日本の軍需産業の実態を暴き、調査報道の手腕を示した。
官邸会見での劇場化
しかし、望月記者が官房長官会見で繰り返し質問を投げかける姿がメディアで報じられるようになると、彼女の役割は変化した。調査報道記者としての活動は減り、むしろ官邸との攻防が「劇場」として消費されるようになった。東京新聞内でも、彼女の会見参加は「自発的な意思」によるものであったとされる。
プロパガンダとしての望月記者
望月記者は、反権力の象徴として持ち上げられ、講演会や書籍出版を通じて知名度を上げた。映画『新聞記者』の公開はその極致であり、彼女の存在自体が「物語」として機能するようになった。この映画はイオンエンターテイメントが配給し、東京新聞を含むリベラル系メディアが後押ししたプロパガンダ作品と見ることができる。
「権力 vs. 庶民」の物語構造
日本の大衆は「権力者が隠れて悪事を働き、それを記者が暴く」という物語を好む。望月記者と菅官房長官の対立は、まさにこの構造に当てはまるものだった。会見の場は「リアリティ・ショー」として消費され、望月記者は「ジャンヌ・ダルク」のような役割を担うこととなった。
報道の本質の喪失
しかし、こうした劇場型報道の問題は、肝心の調査報道が失われることである。望月記者は、かつてのような独自のスクープを発掘する機会を失い、結果的に官邸会見のパフォーマンスに終始することとなった。記者個人が有名になっても、報道の本質である「事実の掘り起こし」にはつながらない。結局、政権にとって痛手となるスクープは望月記者ではなく、別の調査報道によって暴かれることとなった。
第 3章 私たちは情報戦の最中にいる──駆使される数々の定石
戦時プロパガンダの時代
情報と戦争の関係
戦争や武力衝突は国家や民族の存亡をかけた「究極の国際関係」であり、自国を有利にするためにあらゆる資源を投入する。その中で情報も重要な武器となり、国内外の世論を操るためにプロパガンダが活用される。戦時プロパガンダはその最も顕著な例であり、現代ではウクライナ戦争やイスラエル・ガザ紛争などの実例が豊富である。
歴史上前例のない情報環境
現代の戦時プロパガンダはインターネットとSNSの発展により、これまでにない形で展開されている。市民や兵士がスマホやGoProを使って撮影し、それを直接SNSに投稿できるため、情報の発信者と受信者がダイレクトに結びついている。既存のマスメディアはこうした即時性や現場性においてSNSに対抗できず、編集を経ない生の情報が飛び交う状況が生まれている。戦時プロパガンダはこの環境に適応し、国家だけでなく市民個人や企業も積極的に発信を行うようになった。
クライシス・スケールとプロパガンダの変化
プロパガンダは社会の危機の規模に応じて形を変える。平時には政府の施策を支持させるための「平時型プロパガンダ」が用いられるが、戦争や大規模災害の際には「クライシス型プロパガンダ」、さらに戦時には「戦時プロパガンダ」へと進化する。
ハイブリッド・ウォーの展開
戦争は通常の武力戦闘(キネティック・ウォー)だけでなく、情報戦や心理戦(ノンキネティック・ウォー)を組み合わせる「ハイブリッド・ウォー」の形をとる。敵国の戦意を削ぐために虚偽情報や印象操作が行われ、戦争の勝敗は軍事力だけでなく、情報戦の成否によっても左右されるようになっている。
プロパガンダの手法と影響
フレーミングと情報操作
プロパガンダでは「額縁化(フレーミング)」が多用される。例えば、破壊された街ではなく復興した部分だけを報道し、あたかも戦争が終息し平和が訪れたかのような印象を与える。ロシアのプーチン大統領がマリウポリ訪問時に見せた映像では、戦争の被害を映さず、新築された建物や公園を強調することで、ロシアの統治を正当化するメッセージを発信していた。
「われわれ」と「彼ら」の区別
プロパガンダでは常に「われわれ(内集団)」と「彼ら(外集団)」を区別し、敵対する側を否定的に描く手法が使われる。戦争では敵国の国民を「非人間化」し、敵対心を煽るために侮蔑的な呼称を用いることが一般的である。また、言葉の選択もプロパガンダの一環となり、ウクライナでは「キエフ」から「キーウ」への表記変更が行われた。
恐怖アピールと被害者アピール
プロパガンダは恐怖を煽ることで人々を特定の行動へと導く。例えば、「この戦争が続けばヨーロッパ全体が核の脅威にさらされる」といった表現を用いることで、国際社会の支援を得ようとする。また、自国を「被害者」として描くことで、道徳的な正当性を確立し、国際的な同情を引き出す手法も頻繁に用いられる。
情報の曖昧さと混乱の利用
プロパガンダでは必ずしも真実を示す必要はない。情報の真偽が曖昧なまま流布され、人々が混乱し判断を保留する状態が作り出される。イスラエル・ガザ紛争では、ハマスが子どもを斬首したという情報が広まり、後に否定されたが、その間に国際世論は大きく影響を受けた。プロパガンダは「正しい情報を広める」ことではなく、「受け手の認識を都合の良い方向に誘導する」ことを目的としている。
結論
戦時プロパガンダはインターネットとSNSの時代に進化し、国家や組織だけでなく個人も積極的に発信する状況が生まれている。プロパガンダの手法は、恐怖を煽り、敵を悪魔化し、情報をフレーミングすることで人々の認識を誘導する。戦争において情報は強力な武器であり、プロパガンダの影響力はますます増大している。
プロパガンダのパターン
1. 有利な認識の形成 – 真実でなくても、受け手の認識を誘導できればよい。
2. フレーミング – 都合のいい事実だけを切り取って見せる。
3. 発信者の多様化 – 政府だけでなく、市民や団体もプロパガンダを発信できる。
4. ハイブリッド・ウォー – 武力戦と情報戦を組み合わせる。
5. グルーピング – 「われわれ」と「彼ら」に分ける。
6. ワーディング – 用語の選び方で敵味方を区別する。
7. 非人間化・悪魔化 – 相手を劣った存在、または極悪非道な存在に見せる。
8. 記憶の上書き – 新しい情報で過去の不都合な記憶を塗り替える。
9. 現実の改変・加工 – 証拠の隠滅や歴史の書き換えを行う。
10. 正解の曖昧化 – 情報を混乱させ、どちらが正しいかわからなくする。
11. 恐怖アピール – 不安を煽り、行動を促す。
12. 被害者アピール – 自分たちは被害者であり、正義は自分たちにあると主張する。
13. 敵の成功を矮小化 – 相手の功績は軽視し、自分たちの成果は誇張する。
14. 部分的な真実の活用 – 少しの事実と大量のフィクションを組み合わせる。
15. 敵の行為のすり替え – 自分たちの失敗や問題を敵のせいにする。
16. 国際世論の操作 – 国内だけでなく、国外にも影響を及ぼすように情報を発信する。
第 4章 プロパガンダ 3. 5時代が到来した──マユツバ思考の重要性
1 スマホと SNSが生み出したプロパガンダ 3. 5世代
インターネットの進化と情報環境の変化
インターネットの普及により、かつてマスメディアが独占していた情報発信が解放された。個人が自由に情報を発信できるようになり、政治や経済、生活スタイルにも影響を与えた。SNSとスマホの普及によって情報の伝播速度が加速し、コストは大幅に低減した。また、写真や動画、音声といった多様なコンテンツが容易に配信できる環境が整った。こうして、誰もが低コストでマスメディアを持つ時代が到来したのである。
インフルエンサーとプロパガンダの拡大
SNSの普及により、個人が影響力を持ち、情報を広範囲に伝えることが可能となった。こうした影響力を持つ個人は「インフルエンサー」と呼ばれ、彼らの発信が企業や政治のマーケティングに活用されている。ビジュアル・マーケティング会社の定義によれば、インフルエンサーとは特定の分野で影響を与える人物を指し、SNSを通じた情報発信によってユーザーの購買行動にも大きな影響を与える。特に、企業の広告戦略としてインフルエンサーを活用する手法が一般化し、消費者はインフルエンサーの発信を信用する傾向が強まっている。
ステルス・プロパガンダの実態
福島第一原発事故の取材を続ける筆者に対し、福島県が運営する伝承館のPR記事の執筆依頼が届いた。依頼内容は、報酬を支払う代わりに伝承館の記事をSNSで発信するというものであった。通常の報道記者は取材対象から金銭を受け取らない「ニュートラル原則」を守るが、この依頼は明らかにその原則を逸脱するものであった。こうした手法は「ステルス・マーケティング」、すなわち広告であることを隠した宣伝行為であり、筆者はこれを「ステルス・プロパガンダ」と呼ぶ。
インフルエンサー・マーケティングの市場拡大
SNSを活用したマーケティング市場は急成長しており、2027年には1兆円規模に達すると予測されている。特にインフルエンサーを活用した広告戦略は、消費者の購買行動に影響を与えるため、企業の宣伝活動において重要な役割を果たしている。SNSは世界人口の約六割が利用し、FacebookやYouTube、Instagramといったプラットフォームが強大な影響力を持つようになった。この環境下で、プロパガンダがより巧妙に拡散されるようになったのである。
ブラック・プロパガンダ業者の存在
2019年の参院選広島選挙区では、選挙対策としてSNSを利用した隠密なプロパガンダが行われた。検察の調査によれば、インターネット関連業者が選挙対策のための情報操作を請け負い、対立候補を貶める内容の発信を行っていた。このように、ネット空間での情報操作が選挙戦に利用される実態が明らかとなった。
Dappi事件と政治的情報操作
SNS上で匿名のアカウント「Dappi」が自民党を支持し、野党議員への批判を展開していた。訴訟によって、このアカウントの発信元が特定され、企業による組織的な情報操作であったことが判明した。裁判では、この企業が業務として政治的プロパガンダを行っていたと認定され、賠償命令が下された。この事件は、日本国内においてもSNSを利用したブラック・プロパガンダが企業によって組織的に行われていることを示すものであった。
SNSとハラスメントの関係
SNSは匿名性を持ち、複数のアカウントを取得できるため、誹謗中傷やフェイクニュースの温床となっている。特に政府批判を行う個人に対し、組織的な嫌がらせが行われることが指摘されている。こうした活動は、政府との関係を明示しないまま言論統制を行う新たな手法として利用されており、現代の情報戦における重要な要素となっている。
プロパガンダの新たな時代
SNSの普及により、個人が影響力を持ち、情報発信がかつてない規模で行われるようになった。一方で、ステルス・プロパガンダやブラック・プロパガンダといった手法が蔓延し、世論形成に大きな影響を与えている。これにより、政治や企業の情報操作が巧妙化し、受け手が意図を見抜くことが難しくなっている。
2 プロパガンダからの自衛策とは
トロール工場の組織と運営
ロシアのサンクトペテルブルクに本拠を置く「インターネット・リサーチ・エージェンシー(IRA)」は、プロパガンダを目的とする組織であった。同社はエフゲニー・プリゴジンによって創設され、彼は「プーチンの私兵」と呼ばれた民間軍事会社「ワグネル」の創設者でもあった。IRAは偽情報や誹謗中傷を世界中にばらまき、特にSNSを利用した世論操作を展開した。
IRA内部の実態
2015年、ロシアのテレビ記者リュドミラ・サヴチェフがIRAに潜入取材を行った。彼女は高額な報酬を提示され、主婦向けの占星術ブログを運営する役割を与えられた。そのブログにはアメリカ批判やウクライナ批判が紛れ込ませられ、読者を誘導する仕組みになっていた。IRAには元ジャーナリストが多数雇用されており、彼らは「コメンター」としてネットニュースのコメント欄で敵対勢力を攻撃する任務を担っていた。
2016年アメリカ大統領選挙への介入
IRAの活動が最も活発化したのは2016年のアメリカ大統領選挙であった。同組織はSNS上に無数の偽アカウントや偽グループを作り、右翼や民族主義者、トランプ支持者を装ってヒラリー・クリントンを貶める情報を拡散した。その影響で約3,000万人のアメリカ人がIRAのコンテンツをシェアする事態となった。2018年、アメリカの特別検察官が捜査に乗り出したものの、実質的な制裁は行われず、IRAはむしろ拡大を続けた。
西側諸国も同様の戦略を展開
IRAがアメリカで制裁を受けなかった背景には、西側諸国も同様のプロパガンダ活動を行っていた事実がある。2011年、アメリカ軍は「正直な声作戦(Operation Earnest Voice)」を実施し、SNS上に偽アカウントを作成して中東諸国で親米的な世論を形成しようとした。西側諸国とロシアは、互いにディスインフォメーションや誹謗中傷を駆使し、SNS上で情報戦を繰り広げていた。
マケドニアのフェイクニュース工場
2016年のアメリカ大統領選挙では、マケドニアのヴェレスという町がフェイクニュースの発信拠点となった。18歳の青年ボリスが偶然発見したフェイク記事を転載したところ、アメリカで拡散され、Googleから広告収入を得ることになった。これを機にボリスはフェイクニュース専門業者となり、複数のニュースサイトを運営して多額の利益を上げた。
フェイクニュースの収益構造
フェイクニュースはSNSのアルゴリズムを利用して拡散され、広告収入を生む仕組みになっていた。ボリスは200以上の偽アカウントを作成し、トランプ支持者向けの記事を転載することで、Googleから広告料を得ていた。2016年には彼のサイトから1万6,000ドル以上の収益が発生し、マケドニアでは数年分の収入に相当する金額となった。しかし、Googleが広告掲載を停止したことで彼のビジネスは終焉を迎えた。
東京都知事選とSNSの影響
2024年の東京都知事選挙では、小池百合子氏が当選したが、次点で165万票を獲得したのは広島県の元市長・石丸伸二氏であった。選挙期間中、クラウドワークス上で「石丸氏の演説を撮影・編集して投稿する」業務に対し、5〜10万円の報酬を支払う求人が大量に掲載されていた。この求人の依頼主は不明であり、石丸氏の支持者が自主的に行った可能性もあるが、選挙運動への報酬提供が公職選挙法違反となる可能性も指摘された。
SNSの匿名性と選挙運動の変化
SNSを利用した選挙戦では、発信者の匿名性が高いため、誰が資金を提供し、情報を拡散したのかが不明瞭なままとなる。選挙運動における資金提供は、特定の候補者に有利な状況を作り出すため、公職選挙法によって制限されている。しかし、SNSを利用した広報活動は規制が難しく、違法行為が発覚しにくいという課題がある。
プロパガンダのアルゴリズム化
コンピュータ科学者ジャロン・ラニアーによれば、SNSの基本設計には「行動修正」のアルゴリズムが組み込まれており、ユーザーの思考や感情を操作する仕組みが存在するという。彼はこれを「BUMMER(Behaviors of Users Modified, and Made into an Empire for Rent)」と名付け、SNSはプロパガンダを拡散するためのプラットフォームになっていると指摘した。
プロパガンダ時代を生き抜くための思考法
SNSがプロパガンダの温床となる中、情報を無条件に信じるのは危険である。著者は「マユツバ思考」、すなわち情報を疑いながら接することの重要性を説いた。SNS上で流れる情報が作為的に操作されている可能性を考慮し、「ほんまかいな」という視点を持つことが、プロパガンダに流されないための唯一の手段であると述べている。
あとがき
日本社会におけるプロパガンダの影響
経済プロパガンダへの無防備さ
日本の大衆は政治プロパガンダに対して敏感であったが、経済プロパガンダ、特に広告に対しては極めて無防備であった。その典型的な例が2007年1月7日に放送されたフジテレビ系列の『発掘!あるある大事典Ⅱ』である。この番組で「納豆がダイエットに効果的」と紹介されると、多くの視聴者が納豆を買い求め、店頭から姿を消した。しかし、後に番組内で提示された実験データが捏造であることが発覚し、関西テレビは謝罪放送を行い、番組を打ち切った。
納豆ブームと情報操作
納豆や大豆関連食品は、大手食品メーカーが健康食品として販売を促進したい商品であった。そのため、番組が企業の利益に沿った情報を提供していた可能性は高い。もし視聴者にプロパガンダ・リテラシーが備わっていれば、納豆の品切れという現象は起こらなかったかもしれない。
原発事故と安全神話
東日本大震災以前、日本の大半の人々は「原発事故は日本では起こり得ない」と考えていた。スリーマイル島やチェルノブイリでの事故を「遠い国の出来事」と捉え、電力産業が発信する「安全神話」を無批判に受け入れていた。その結果、原発事故の危険性を警告する声は少数派として扱われた。しかし、実際には「巨大地震 → 津波 → 冷却電源の喪失 → メルトダウン」という単純なプロセスで福島第一原発は崩壊し、大量の放射性物質が放出された。事故後、多くの人が「なぜ、これほど単純な事実に気づけなかったのか」と後悔することになった。
社会的価値観の変化と広告戦略
タワーマンションの上層階に住むことが「ステータス」とされるようになった背景には、広告やメディアによる価値観の誘導があった。一生かけて住宅ローンを返済する生活が、本当に必要なのかという視点が欠落していた。同様に、薄毛治療の広告も、「ハゲ」という言葉を「薄毛」や「AGA」に置き換え、治療が可能であるとするイメージを植え付けた。かつての「毛生え薬」や「カツラ」が、新しい形で市場に浸透していったのである。
プロパガンダの終わりなき影響
資本主義社会において、商品やサービスを購入することは避けられないが、一方で「必要でないものまで買わせる」ことを目的とする企業や広告が存在する。そのため、プロパガンダが完全になくなることはあり得ない。高度に発展した消費社会の中で、プロパガンダの影響をゼロにすることは不可能である。
流されないための意識
この絶え間ないプロパガンダの中で生きる限り、人々は自身を守る術を身につけなければならない。大衆が一斉に同じ方向へ動き出したときこそ、警戒すべき瞬間である。その流れに無批判に従うのではなく、一度立ち止まり、情報を疑う視点を持つことが重要である。「ほんまかいな」と考える習慣が、プロパガンダに飲み込まれないための防衛策となるのである。
同著者の書籍




その他ノンフィクション

Share this content:
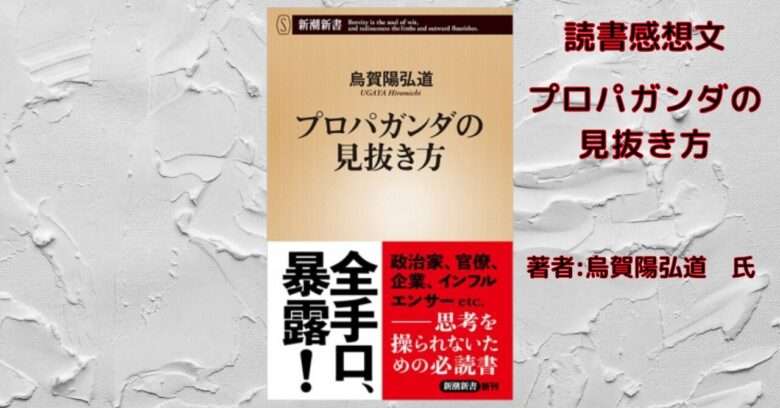

コメントを残す