どんな本?
戦国小町苦労譚は、夾竹桃氏によるライトノベル。
農業高校で学ぶ歴史好きな女子高生が戦国の時代へとタイムスリップし、織田信長の元で仕えるという展開が特徴。
元々は「小説家になろう」での連載がスタートし、後にアース・スターノベルから書籍としても登場。
その上、コミックアース・スターでも漫画の連載されている。
このシリーズは発行部数が200万部を突破している。
この作品は、主人公の静子が現代の知識や技術を用いて戦国時代の農業や内政を改革し、信長の天下統一を助けるという物語。
静子は信長の相談役として様々な問題に対処し、信長の家臣や他のタイムスリップ者と共に信長の無茶ブリに応える。
この物語には、歴史の事実や知識が散りばめられており、読者は戦国の時代の世界観を楽しむことができる。
2016年に小説家になろうで、パクリ騒動があったらしいが、、、
利用規約違反、引用の問題だったらしい。
前巻からのあらすじ
土壌改良、暗渠、草刈機、塩、レンガ、コンクリート、木酢液等を創造し。三河の綿も入手。
織田家の中で静子の重要度が上がったので信長は静子直属の馬廻を入れた。
前田慶次、可児才蔵。そして森長可。
さらにビットマン達オオカミ達。
そんな彼等が家に住み静子の身辺を護る。
元服してない長可だけはヤンチャをして、ビットマン達から粛正され。
それにもめげずに静子の寝込みを襲ったら、静子の無意識の関節技を食らって撃沈。
それからは大人しくなった。
読んだ本のタイトル
#戦国小町苦労譚 3 上洛
著者:#夾竹桃 氏
イラスト:#平沢下戸 氏
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
タイムスリップJK、ついに戦場デビュー!?
この時代に迷い込んで早三年……生き残るため、存在価値を示すため、がむしゃらに農業改革に邁進していた静子だったが、ついに「女が軍勢にいると宜しくない、という験担ぎなどぶち壊す」という信長のお達しにより、戦場へ赴くことに!
そんな静子の支援の甲斐あってか、信長はいよいよ上洛を果たす。
一方、濃姫が新しい料理人を雇うことになるが、そこにいたのは静子もよく知った人物で−−
戦国小町苦労譚 三、上洛
感想
「女が軍勢にいると宜しくない、という験担ぎなどぶち壊す」と信長が言って、静子が従軍することになる。
周りには馬廻衆の前田慶次、可児歳三、森長可が従い。
直掩にはオオカミ(表紙)達がピッタリ寄り添って、男性しかいない軍の中で静子を護衛する。
そして順調に上洛を果たす。戦闘があったけど静子はほとんど関わっていない。
その後ルイス・フロイスとの会談も、信長の側で意見を言わされたりして、ルイス・フロイスも静子を何者だと驚いて見る。
遂に歴史にがっぷり四つに関わって来た静子。
徳川、浅井と共に六角を攻め滅ぼして上洛を果たす織田家。
上洛を果たして京に到着したら、信長から静子に5,000の兵を指揮して京の治安を良くしろと命令される。
それを手伝うのが馬廻の前田慶次、可児歳三、森可長。
森可長は京を警邏して犯罪の取り締まり。
容赦なく取り締まるので苦情もきたりするが、静子はスルー。
可児歳三は孤児、浮浪者を保護しようとするが逃げられてしまうのを悩んでいたが静子がアドバイスをしてやってみたら上手く行く。
それにより、京の治安は良くなり織田家への評価が上がる。
その裏で、前田慶次は職人の引き抜き。
そんな引き抜いた京の職人達300人達の中の料理人たち、岐阜に到着したら濃姫に引っ立てられて、濃姫は料理人の試験を開始する。
多くの料理人が濃姫の試験を拒否する中。3人の男が濃姫の試験を通過する。その3人のうち2人は、静子と同じくタイムスリップして来た足満とミツオだった。
そして、足満は元はこの時代の人だった。
しかも足利幕府の将軍だった。
13代将軍、足利義輝。塚原卜伝の直弟子の剣豪将軍。
暗殺されて重傷を負って倒れていたのを静子の家族が見付けて病院へ。
奇跡的な回復をしたが身元不明な男を静子の家族は身許引受人になって共に生活をしていた。
そんな足満を濃姫が多くの料理人の中から見出して静子と引き合わせる。
その後、信長とも会談させる。
そこまでする濃姫の慧眼って、、
そして足満の役職は神社の神主でありながら静子の守護者となる。
一緒に来たミツオも畜産関係で静子に協力する。
そしてアグー豚を求めて琉球へ向かう。
さらに静子は古代米から現代米へ尾張の米を変換。
安定的なタンパク源の供給が出来れば、子供が体格向上するかもしれない。
領民の栄養状態改善は富国強兵の基礎。
さらに、加工食品に螺旋盤で木工、竹工が盛んとなり産業革命前夜が訪れる織田領。
戦略面で領内の生産性向上は流民の受け皿にもなり国力増強になる。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
備忘録
永禄十一年上洛
千五百六十八年六月上旬
作付け計画の見直し
静子は、新たに入手した種や苗を考慮し、作付け計画を練り直すことにした。基本方針として四年サイクルの輪作を維持しつつ、栽培作物を変更することで対応する方針を採った。作付け計画書は、土耕しから収穫までの工程を考慮しなければ、収穫と後作の準備が重なる事態を招くため、慎重に組み立てる必要があった。
静子は既に、作物の連作障害や相性の良し悪しをまとめた資料を作成し、百姓たちに配布していたため、彼らは自主的に計画を見直すことが可能であった。そのため、静子は移住によって生じた余剰地の分配を村人たちと話し合ったが、具体的な作付け計画には深く関与しなかった。結果として、50人が使用していた田畑を30人で分配することとなり、各農家が広大な田畑を持つことになった。
畑の区分と輪作プランの策定
静子は分配された土地を四つのエリアに分けた。一つは連作障害が起こりにくいカボチャ、サツマイモ、ニンジン、コマツナを栽培するエリアとし、毎年同じ作物を育てる形を取った。他の三つは輪作プランA、B、Cとして運用することにした。
輪作プランAでは、大豆の栽培を中心に、グループAに落花生、グループBにトウモロコシと大豆、グループCにサツマイモ、グループDに鶏卵を配置した。輪作プランBでは、グループAがトウモロコシと白菜、グループBがナスと大根、グループCがトマトとほうれん草、グループDが鶏卵を育てる形とした。最後の輪作プランCでは、スイカ、オクラ、じゃがいも、白花豆をそれぞれ育てることにした。
しかし、それでも細かな土地が余り、静子はその部分にオカヒジキを植えた。オカヒジキは害虫が寄り付きにくく、農薬が不要で栽培が容易であるため、土地の有効活用に適していた。
環境配慮と石鹸製造の検討
オカヒジキはソーダ灰の原料にもなるが、日本では菜種油やごま油が貴重であり、大量の薪を消費する石鹸製造にはメリットが薄かった。そのため、静子はムクロジを大量に植え、実の皮を洗剤として活用する方針を採った。
また、土地の肥沃度を維持するため、一部の畑は休耕地とした。フレンチマリーゴールドやローリエをコンパニオンプランツとして活用し、病害虫対策を強化するため、素焼きの鉢に植えて時期を見て配置することにした。
果樹園には広い土地を確保したものの、苗木の数が少なく、閑散とした状態であった。柿や栗の栽培も検討したが、害虫を引き寄せる可能性を考慮し、畑の近くでの栽培を断念した。
蚊取り線香の材料と新たな試み
白花虫除菊、ひまわり、アロエベラの栽培も進め、特に白花虫除菊は蚊取り線香の原料になることから優先的に割り当てた。静子はスマートフォンの情報を整理している際にその効能を知り、一時的に信仰心を抱いたが、誤ってスマートフォンを額に落とし、その思いは消え去った。
また、アロエベラは「医者要らず」とも称され、多様な用途に使えるため、大量栽培することにした。ひまわりも種が栄養豊富で、植物油の採取が可能であるため、活用価値が高かった。
米の生育状況と栄養管理
静子が持ち込んだ二種類の米は順調に育っていた。病気に強く品種改良されているため成長は良好であったが、肥料を前提とした品種であったため、土壌管理が難しかった。収穫後の栄養保持も課題となり、静子はその改善策を模索していた。
信長の家臣の動きと上洛の予兆
信長は静子に緊急の命令を出さず、自由に行動させていた。しかし、織田家の家臣たちが発する空気に変化があり、静子は美濃攻略時以上の熱気を感じ取った。そして、信長が上洛を決意したことを悟った。
信長の上申への対応が鈍くなり、忠勝との文通頻度が減少していたことも、その兆候であった。さらに、軍需品や日用品の大規模な買付が行われており、明らかに軍事行動の準備が進められていた。
濃姫、ねね、まつの訪問
上洛を控えた状況にも関わらず、濃姫はおね、まつと共に静子の村を訪れた。彼女は静子が竹串を用いた串焼きや焼き鳥を試作していたことを知り、それを味わうために訪れたのであった。
炭火で焼き鳥を焼く静子に、三人は熱々の料理を楽しんでいた。戦国時代の武将は毒見の関係で冷めた飯を食べることが多かったが、側室や正室はその心配が少なく、温かい料理を楽しむことができた。
濃姫は静子に対し、彼女の功績を認めつつ、織田家の血を引く者の正室になれば安泰な生活が得られると指摘した。しかし、静子が依然として農作業に励んでいることに興味を示し、努力の意味について語った。そして、「何か一つ、自分だけのものを作るべきだ」と助言した。
信長の決断と義昭との会談
その頃、信長は立政寺で足利義昭と会談していた。信長は義昭に銭や武具を贈り、上洛を約束した。そして、京にいる三好勢力を駆逐した後に義昭を迎えると述べた。
細川藤孝は、信長の迅速な行動力に驚き、彼が最初から上洛を計算に入れていたことを悟った。しかし、義昭自身は信長を見下しており、上杉謙信への期待を捨てていなかった。
静子への辞令と上洛への同行
数日後、信長上洛の報せが静子のもとにも届いた。彼女は戦支度のために家臣たちが姿を消し、自由に農作業ができることを喜んでいた。しかし、その矢先、彩が静子のもとへ甲冑を届けに来た。
信長は「女が軍勢にいると縁起が悪いという験担ぎを打ち壊す」との意図で、静子を戦場に同行させる決定を下していた。これは公的文書として発行されたものであり、拒否の余地はなかった。
そして、静子は彩から「明後日には出陣する」と告げられ、動揺しつつもその現実を受け入れることとなった。
千五百六十八年六月中旬
上洛軍の準備と静子の異質な装い
信長の上洛軍は岐阜に集結し、町は兵士や物資で混雑していた。静子は甲冑を身にまとい、指定された場所を探しながら歩いていた。しかし、甲冑だけでは女性であることを隠し切れず、多くの兵士たちが彼女に注目した。しかし、慶次や才蔵、さらには大型の犬であるカイザーとケーニッヒが付き添っていたため、周囲の者たちは視線を外した。
静子の装備も異質であった。彼女は大型の革製バックパックを背負い、食料や工具、矢竹で作られた矢筒を収納していた。さらに、鹿狩りに使用していたコンパウンドボウを持ち歩いていた。威力を調整していたものの、60ポンド程度の強さで、和弓と比較すると中途半端な性能であった。しかし、静子自身は戦場で使用する機会はないと考え、主に移動中の食料調達用と割り切っていた。
森長可との合流と狩猟の経験
静子たちは長可の元へ向かった。長可は年齢的に前線での戦闘は許可されていなかったが、十文字槍を携えていた。また、彼も静子と同様にコンパウンドボウを装備していたが、和弓の矢を使用できるように調整されていた。
長可は鹿狩りを通じて弓の腕を磨いており、その熟練度は相当なものであった。静子も害獣駆除を行っていたため、弓の腕は確かであった。しかし、鹿の増殖による森林破壊を食い止めるため、継続的な狩猟が必要であった。
上洛軍の行軍開始と軍事的背景
上洛軍の行軍が始まり、前軍の兵たちは士気を高めるために雄叫びを上げていた。信長の軍は前軍、中軍、後軍の三部隊に分かれて進軍していた。六角氏は織田軍の上洛に対し抵抗の姿勢を示していたが、信長は事前に国衆への調略を進め、六角家の孤立を図っていた。
また、信長は義昭に対して上洛の表明を行った後、近江・高宮に着陣し、浅井軍と合流する予定であった。しかし、予定に変更が生じ、翌日に家康と合流することになった。
奇妙丸との会話と戦時食
静子は行軍中の食事として、干し飯を使用した粥を作っていた。そこに奇妙丸が現れ、当然のように食事を分け与えられた。奇妙丸は戦場に同行していたが、実際に戦闘には参加せず、学びのために同行していた。
彼は戦場での将軍家の動向について静子と議論し、六角氏が上洛軍に参加しない理由を問うた。静子は、六角氏が義昭の過去の行動を恨んでいる可能性があると説明し、さらに将軍家の権威が衰退していることにも触れた。
また、静子は戦場における栄養補給の重要性についても説明し、一夜酒や甘酒の効能を語った。甘酒にはビタミンB群やアミノ酸が豊富に含まれており、兵士の体力維持に役立つことを伝えた。
兵站の重要性と信長の関心
静子は奇妙丸との会話の中で、兵站の重要性について触れた。戦国時代の軍勢は基本的に小荷駄による補給を行っていたが、これには限界があり、補給が尽きれば撤退を余儀なくされることが多かった。対して、兵站を整備すれば、戦争の継続能力が大きく向上する。
この話を聞いた信長は、静子の考えに興味を持ち、彼女を軍議に参加させた。彼は黒板を用意し、主だった家臣たちと共に兵站についての議論を始めた。柴田勝家や佐々成政は不服そうであったが、竹中半兵衛や丹羽らは興味を示した。
静子は戦略と戦術の違いを説明し、戦争を遂行するために必要な物資とその輸送の重要性を説いた。さらに、上杉謙信や武田信玄が小田原城の攻略に失敗した例を挙げ、小荷駄による補給の限界を指摘した。
信長は静子の話を聞き、彼女が農業改革を進めていた理由が兵站の整備にも繋がっていたことを理解した。そして、彼女の評価をさらに高め、兵站の導入を検討することを決定した。
静子は、自身の意図とは異なる形で高評価を受けてしまい、内心動揺しながらも、信長の決定に従わざるを得ない状況となった。
兵站会議と革新的な提案
信長の兵站会議では、従来の軍事行動を大きく変える案が次々と提示された。彼は『伍』の制度を取り入れ、五人を一組とする軍事行動の基本単位とした。この制度を基に、竹中半兵衛は現代のインスタント食品に似た食糧筒を提案し、干し飯や干し肉、干し野菜、梅干しを入れてお湯を注ぐだけで調理できる方式を考案した。
一方、森可成と丹羽長秀は、静子が導入したマカダム舗装を軍事物資の輸送路に採用する案を出した。この舗装は水はけが良く、雨天でも道路がぬかるむことがないため、輸送の効率を飛躍的に向上させると見込まれた。さらに、静子は荷馬車として三九式輜重車を提案し、物資輸送の効率化を図った。
また、秀吉は駅馬車制度を導入し、一定間隔で馬を交換することで移動距離を一定に保つ計画を立てた。これにより馬の負担を軽減し、輸送の安定性を向上させることが可能となった。これらの提案は実現までに時間を要するものの、運用が軌道に乗れば他勢力を圧倒する戦略的優位を確立できるものであった。
柴田と佐々の疑念と対話
兵站会議が終了すると、柴田勝家と佐々成政が静子のもとを訪れた。彼らは静子を快く思っていなかったが、信長が彼女を重用する理由を探るために直接話を聞くことにした。静子は兵站の必要性を説明し、戦術や戦略と同じく重要な要素であることを強調した。
竹中半兵衛は、兵站を理解することで軍の運用がより明確になると補足し、信長が静子を評価する理由を説明した。柴田と佐々は納得しきれない様子だったが、無意味な反発は不和を生むとして、今後は静子への露骨な敵意を抑えることを決めた。
信長の戦略と六角氏への対応
信長率いる上洛軍は、浅井軍と合流後、愛智川北岸付近に布陣した。信長は自ら馬を駆り、敵情を視察し、観音寺城、箕作城、和田山城を攻撃目標と定めた。六角氏は和田山城に主力を配置し、上洛軍を釘付けにした上で、観音寺城と箕作城から挟撃する作戦を取ると予測された。
また、信長は南近江の国人たちが戦況が不利になると戦場から撤退する傾向があることを見抜き、六角氏を完全に制圧する必要があると判断した。彼は浅井・徳川と軍議を開き、戦の準備を整えた。
静子の散策と本多忠勝の登場
信長が軍議を進める中、静子は退屈を持て余し、本陣周辺を散策していた。しかし、彼女はすぐに何者かに見られていることに気付き、鏡を使って相手を確認した。そこにいたのは本多忠勝であった。
忠勝は静子を探していたものの、適切な言葉を見つけられず、草陰から様子を窺っていた。静子は問い詰めることなく、忠勝を陣に戻るよう促した。忠勝は静子との関係を深めようと試みたが、カイザーとケーニッヒの妨害により大した進展は得られなかった。
家康と長政の訪問
その後、家康と長政が信長のもとを訪れ、噂になっている「名物兵」を見せてほしいと頼んだ。信長は静子を指し示し、彼女の護衛として連れてきたカイザーとケーニッヒを紹介した。しかし、静子はちょうど昼寝をしており、カイザーとケーニッヒを枕代わりにして寝ていた。
この異様な光景に家康と長政は驚きを隠せなかったが、信長は静子を叩き起こし、彼女に状況を説明させた。周囲の兵たちは狼を恐れて陰口を叩いていたが、信長は彼らを一喝し、家康も謝罪した。
家康は静子に興味を抱き、改めて話し合いたいと伝えた。そして、彼はカイザーの頭に手を置こうとしたが、巧みに避けられた。家康はそれを冗談めかして笑いながら、静子にさらなる関心を寄せていた。
千五百六十八年八月上旬
観音寺城の戦いと六角氏の崩壊
六角軍の布陣と戦略
六角義治は父・義賢、弟・義定とともに本陣の観音寺城に構え、精鋭の馬廻衆1000騎を配備していた。さらに、箕作城に吉田重光・建部秀明らを含む3000余人、和田山城には田中治部大輔を大将とする6000余人を配置し、総勢1万ほどの軍勢で上洛軍に備えていた。しかし、六角軍の布陣は戦略的には脆弱であり、各城が相互に支援できる形ではなかった。六角義治は長年築き上げた防衛線に絶対の自信を持っていたが、織田信長は六角軍の布陣や逃走経路までも完全に把握していた。
織田・徳川・浅井連合軍の進軍
織田軍4万~5万、徳川軍1000、浅井軍3000の合計6万近い上洛軍は、戦端を開くべく三手に分かれた。第一隊の稲葉良通は和田山城、第二隊の柴田勝家・森可成は観音寺城、第三隊の信長・秀吉・丹羽長秀は箕作城を目指した。戦闘は箕作城で始まり、秀吉の2300人と丹羽の3000人がそれぞれ北口と東口から攻撃を仕掛けたが、急坂と大木に囲まれた堅城のため、六角軍の吉田出雲守隊に苦戦を強いられた。
信長の火攻め作戦
信長は箕作城へ通じる唯一の道を封鎖し、退路を断った。その後、兵たちはアルコール度数60度以上の液体を壺に詰め、それを城内に投げ込んだ。城内に酒の水たまりができるほど投げ込まれた後、一本の火矢が放たれた。気化したアルコールに引火し、一瞬で箕作城は炎上。六角軍の兵士たちはパニックに陥り、組織的な撤退が不可能となり潰走した。退路を塞がれた彼らは、待ち伏せしていた織田軍に討ち取られ、箕作城はわずか半日で陥落した。
観音寺城への波及と六角家の崩壊
箕作城の陥落により、和田山城の守備隊も士気を失い総崩れとなった。六角義治は観音寺城で戦況を確認したが、最も頼りにしていた馬廻衆700が壊滅し、父・義賢と弟・義定が討ち死にしたとの報を受け、膝から崩れ落ちた。彼はもはや観音寺城の防衛は不可能と判断し、甲賀へ逃走を決意。側近20余人とともに隠し通路を使って城を脱出した。しかし、信長の配下である滝川一益の忍びが待ち伏せしており、義治は罠にかかって重傷を負う。滝川の命令で処刑され、六角家当主・六角義治は非業の最期を遂げた。
戦後処理と織田軍の統治
観音寺城、和田山城、箕作城は全て廃城とされ、六角家の有力武将はほぼ討ち死にした。日野城の蒲生賢秀のみ降伏し、織田家の家臣として組み込まれた。織田軍の損害は1000人程度、浅井軍は300人、徳川軍は数十名だったのに対し、六角軍は4000人が戦死し、4500人が逃亡するという壊滅的な敗北を喫した。
京への進軍と足利義昭の将軍就任
信長は戦後すぐに京への進軍を開始し、三好三人衆を撃破しながら畿内を制圧した。義昭は正式に征夷大将軍に任命され、室町幕府最後の将軍となった。信長は義昭を支えるため、細川藤孝を京に、和田惟政を摂津に配し、京の治安維持のため『京治安維持警ら隊』を編成。この隊の設立と運営を静子に任せ、彼女は短期間で治安維持の基盤を整えた。信長はまた関所の廃止、座制度の撤廃を行い、民衆の支持を集めた。
浅井軍の帰国と上洛軍の解散
京の安定が進む中、農繁期に戦に駆り出された浅井軍の士気低下が問題となった。信長は長政に感謝の意を表し、浅井軍と徳川軍の帰国を許可。7月20日、上洛軍を解散し、織田軍のみが京に留まった。その後、信長は義昭を擁して畿内の人事を掌握し、畠山・三好・松永勢を巧みに統治。8月12日、義昭は正式に征夷大将軍に任命され、信長は幕府の実権を掌握した。
治安維持と信長の改革
信長は京の治安を回復するため、『京治安維持警ら隊』を正式に発足させ、静子がその基盤を整えた。戦災孤児の収容と教育の制度も整備し、将来的な反乱の火種を未然に防いだ。静子は治安維持における細部の制度を策定し、明智光秀に引き継いだ。8月15日、信長は岐阜へ帰国を決意し、京の統治を義昭と光秀に委ねた。
観音寺城の戦いは、六角氏の崩壊と信長の上洛を決定づけた重要な戦いだった。信長は徹底した情報戦と火攻めによって短期間で六角氏を滅ぼし、畿内の統治に成功。義昭を擁立することで名目上の正統性を確保しつつ、実質的な権力を掌握した。この戦いを通じて、織田家の勢力は全国的な影響を持つようになり、信長の天下統一への道が開かれた。
千五百六十八年八月中旬
信長の帰国と岐阜での再編
信長は義昭に帰国の旨を伝えた。義昭は「織田弾正忠殿」と記された感謝状とともに、足利家の紋章である「桐紋」と「引両筋」を授与した。信長は京の治安維持のために五千の兵と明智光秀らを残し、残りの軍を率いて岐阜へ戻った。道中、浅井長政と会談した後、八月十九日に岐阜へ到着。上洛軍は解散され、各自が帰路についた。
静子の帰宅と日常の再開
静子は慶次、才蔵、長可と共に帰宅した。装備を片付けた後、長く風呂に入れなかった身体を温泉で癒した。田畑の様子を確認し、スイカを収穫して冷やした。帰宅後、彩から濃姫やおね、おまつにスイカを届けたと報告を受け、彼女たちが収穫量の減少の原因であることを知る。さらに、おまつからの贈り物として小袖や絵巻物を受け取った。
信長の訪問と新たな計画
翌日、信長が村を訪れた。入浴を済ませた後、側近を集め、堺の情勢や近江の商人との交渉、京の治安維持などについて報告を受けた。信長は軍の再編を発表し、六つの軍を設立する方針を示した。第一軍は政治・軍事の頭脳、第二軍は精鋭部隊、第三軍は森可成率いる独立戦力、第四軍は京の治安維持、第五軍は後方支援、そして第六軍は情報機関とされた。
新たな軍制の導入
信長は従来の中央集権型から権限委譲型へ移行し、各軍の自律性を高める方針を示した。特に伊勢の平定後、さらなる敵勢力の増加を見越し、常備軍を各方面へ配置する計画を立てた。具体的な作戦は各軍に任せることで、機密保持と対応の迅速化を図った。信長は森可成を側近とし、明智光秀に京の守護、丹羽長秀に後方支援軍、滝川一益に情報機関の指揮を任せた。
京の料理人試験
一方、岐阜では濃姫が静子が集めた料理人たちに試験を課していた。課題は京風の料理を用意された食材で作ること。提供された食材の大半が京では馴染みのないものであり、多くの料理人が辞退した。しかし、五郎と二人の助手が残り、料理を完成させた。濃姫は彼らの努力を評価し、織田家の料理人として採用したが、配属は信長ではなく濃姫専属となった。
新作物の収穫と試験
九月中旬、静子は作物の収穫を行った。ひまわり、スイカ、オクラ、じゃがいも、白花豆は種の確保が優先された。米の収穫では、ともほなみ系列が一反あたり六俵、名無し米が八俵と高い収量を記録した。しかし、現代の品種は戦国時代の米と食感が異なり、信長の評価が分かれる可能性があった。試食の結果、信長や配下の武将たちはその味を絶賛し、尾張米・岐阜米として名付け、大量生産が決定された。
家畜の飼育と新たな問題
静子は養鶏場の一部を家鴨の飼育場へ変更した。家鴨は肉や卵の生産に加え、羽毛の利用が期待された。しかし、発注ミスにより予想以上の数が届き、鵞鳥も混ざっていた。急遽、専用の飼育場を設け、病弱な個体を間引いた。羽毛は防寒着の生産に活用され、極寒地でも使える装備が試作された。
落花生の栽培と普及
落花生の収穫と乾燥が行われたが、大人には不評だった。信長や森可成らは油分の多い食物に慣れておらず、評価が分かれた。保存性の高さから緊急時の食料としての可能性が示されたが、普及には時間を要した。
信長の経済改革
信長は作物の売買や貯蔵の効率化を進め、単位系の統一を推進した。静子は技術者に測量や計量の道具を作らせ、軍需品として納入した。また、綿花の加工について信長の許可を得ようとしたが、布団の生産は禁止され、代わりにマスクやハンカチを製造した。洗濯の負担増加を懸念し、洗濯機の試作も開始した。
静子と技術部隊の編成
信長は静子に五百名の兵を預けた。彼らは土木技術を持ち、将来的には工兵部隊としての役割が期待されていた。静子は兵たちの生活環境の改善に着手し、食生活の向上を図った。
濃姫の訪問と不満
静子の不在が続き、濃姫は不満を募らせていた。彼女は静子に料理人の腕前を披露しようと考えていたが、静子が日中不在であることに不満を漏らした。しかし、静子が兵士を引き連れて帰還すると知り、ようやく機嫌を直した。彼女の意向により、料理人たちも静子の元へ派遣されることになった。
千五百六十八年十二月中旬
静子の帰還と日常の再開
静子一行は村に到着し、五百名の兵を解散させた。慶次は風呂へ向かい、長可は甲冑姿のまま山へ向かったため、静子の護衛には才蔵だけが残った。静子は荷物を片付けた後、白菜の収穫に取り掛かり、才蔵とともに五玉を収穫した。浅漬けを作ることを決めた静子は、調理場で作業を開始し、梅干しと塩昆布を用いて短時間で完成させた。才蔵はその味を評価し、ご飯が欲しくなると感想を述べた。
濃姫の訪問と料理人の紹介
静子が白菜を干すために外へ出ると、彩が彼女を探していた。彩は濃姫が村へ来訪していることを伝え、静子に対応を求めた。濃姫は自身が連れてきた料理人を紹介しようと考えていたが、静子は美食に関心が薄いため、あまり期待していなかった。濃姫はお市を遊びに誘っているが、浅井長政が許可しないことに不満を漏らした。静子はこれをお市の妊娠が関係しているのではと推測した。
信長からの急な召喚
料理人との対面を前に、信長から緊急の呼び出しが入った。内容は不明だったが、静子はすぐに支度を整え、信長のもとへ向かった。道中、遠くから濃姫の料理人たちが静子を見ていたが、彼女は気づかなかった。信長のもとへ到着すると、彼と家臣団は朝まで街道整備について熱心に議論を交わし、静子もそれに加わることとなった。
磁器蚤の市と信長の関心
十二月、信長と家臣団は静子の技術街で開かれる磁器の蚤の市に集まった。磁器の材料は他国に依存していたため、織田領内では公然と販売できなかったが、商人たちは出所を偽り、高値で取引していた。磁器は南蛮人にも人気があり、信長は特に赤絵磁器に強い関心を示した。今回の蚤の市では四百枚の磁器が用意され、家臣たちも各々好みの品を選び、購入した。柴田と佐々は前衛的なデザインの皿に興味を示し、静子の度量を称賛して去っていった。
特産料理の模索とスッポン養殖計画
信長は岐阜の特産料理の開発を静子に依頼した。彼女は豆腐や油揚げ、稲荷寿司、海老天丼、鍋料理などを試作したが、信長を満足させるものはなかった。唯一、スッポン鍋が興味を引き、静子は養殖計画を立案した。スッポンは冬眠するため、適切な環境を整える必要があった。計画を提出すると、信長はその可能性を評価し、前もって資金を提供した。静子はその期待に応えるべく、養殖場の整備に取り掛かった。
朝廷との直接交渉と「仁比売」の誕生
信長は義昭を介さず朝廷と直接交渉するため、静子の苗字「綾小路」を利用した。朝廷への献金と物資の提供を行い、静子を「綾小路家の隠し子」とする偽りの背景を作った。朝廷はこの話を信じ、静子に「仁比売」の名を与え、従四位上の位を授けた。信長はこれにより朝廷との独自の繋がりを確立し、寺社勢力の影響を削ぐための布石を打った。
濃姫との対話と信長の戦略
濃姫は信長の策略を評価しつつ、彼が静子を直接利用せず、自由な環境を維持させたことに感心していた。信長は個人に忠誠を誓う静子の存在を貴重と考え、織田家ではなく自らに忠義を尽くす家臣の重要性を理解していた。さらに濃姫は信長が密かに隠していた書物を読んでおり、その内容について議論を持ちかけた。信長は彼女の鋭い洞察に舌を巻きつつも、言葉遊びを楽しんだ。
千五百六十九年一月上旬
本圀寺の変と織田軍の動向
永禄十二年一月五日、室町幕府十五代将軍・足利義昭は本圀寺を仮御所として使用していたが、三好三人衆の襲撃を受けた。義昭の警護は光秀を中心とした近江と若狭の国衆のみで、信長の本軍は関与していなかった。京の治安維持部隊は戦闘向けではなく、非殺傷武器しか持たないため、三好勢は容易に進軍した。本圀寺は砦とは言えない構造であったが、若狭国衆の山県源内や宇野弥七の奮戦により、寺域への侵入は阻止され、初日の攻撃は防がれた。
信長の出陣と三好勢の敗北
六日、信長は本圀寺襲撃の報を受け、直ちに出立した。大雪の悪天候の中、本来三日かかる行程を二日で走破し、八日に十騎ほどの供を連れて到着した。しかし六日の段階で、細川藤孝、三好義継、伊丹親興、池田勝正、荒木村重ら畿内の織田勢が集結し、三好勢は劣勢に陥っていた。治安維持部隊も兵站支援や情報収集に徹し、三好勢を追い詰めた。不利を悟った三好三人衆は撤退を試みたが、桂川河畔で織田・足利軍の追撃を受け、敗北を喫した。この戦いは後に「六条合戦」または「本圀寺の変」と呼ばれることとなる。
信長の対応と将軍御所の建設
戦が決した後、信長は池田正秀や若狭国衆の奮戦を称えた。義昭からの叱責を受けるも、信長は受け流し、将軍御所の建設計画を進める。義昭の安全を確保する目的もあったが、信長にとっては自軍の損害を抑えるための策であった。一月十日、義昭側の三好義継は堺に使者を派遣し、三好三人衆を支援した堺商人を責めた。堺側はこれに恐れをなしつつも、戦に備える動きを見せた。信長はこの動きを監視しつつ、光秀と秀吉に二条城の建設を命じ、自らが普請総奉行として指揮を執った。
技工総奉行への任命と軍用食糧改革
静子は信長により「技工総奉行」に任命された。技術改革を行う責任者の署名が必要ではあるが、静子自身が直接命令を出せる立場となった。任命から一週間後、竹中半兵衛が訪れ、軍の食糧事情の改革を提案した。彼は栄養の重要性に着目し、軍用食の改善を求めた。静子は試作としてオートミールを用意し、水煮、味噌煮、醤油煮の三種類を提供した。麦の香りが強いため水煮は不評だったが、味噌や醤油を加えることで改善の余地があると考えられた。
軍用食の課題と調整
半兵衛は、戦場では食事が重要な娯楽であり、不味い食事では士気が下がると指摘した。また、行商人の商売を損なうと反発を招くため、雑兵は現行通りの食糧調達とし、上級足軽から武将向けに戦闘食を導入する案が出た。さらに、オートミール単体では受け入れられにくいため、米と混ぜて雑穀飯として提供することが提案された。これにより、米の消費を抑えつつ栄養価の高い食事を提供することが可能となる。
濃姫と足満の接触
濃姫は、信長居館に仕える料理人・足満に違和感を覚え、彼の素性を問いただした。足満は警戒したが、濃姫は静子と会わせることを条件に協力を求めた。その内容は、静子が避けてきた「人を殺す技術」、つまり兵器開発への関与であった。静子が技術改革を進める一方で、兵器開発に関与しないことを理解した濃姫は、足満にその役割を求めた。足満は一度は拒んだが、濃姫の計略によって最終的に協力を承諾した。
静子と足満の再会
一月中旬、濃姫は静子を信長の別荘へ連れて行き、料理人を紹介した。その中に足満の姿があり、静子は驚いた。足満はかつて静子の家に住み、共に過ごした過去があった。再会した二人の間には緊張が漂い、静子は感情を抑えきれなかった。みつおの介入により、三人はタイムスリップの経緯について話し合ったが、原因は不明のままであった。
戦国時代での生き方の選択
みつおは静子に、「この時代に骨を埋めるか、現代へ帰るか」という覚悟を問うた。静子は自らの立場を考え、二人が後ろ盾もなく生き延びてきた苦労を理解した。彼らにとっては、食料を得ることさえ困難な日々であり、互いに協力することが生存のために不可欠であった。静子は自らの未来を改めて見つめ直し、戦国時代での生き方について考えることとなった。
千五百六十九年一月中旬
静子の迷いとみつおの決意
静子は即答できなかった。タイムスリップ直後ならば迷わず「帰りたい」と答えたであろう。しかし、この時代に長く居続けた彼女にとって、帰還は今生の別れを意味し、無意識に親しい人々の顔が浮かんだ。そんな彼女の心情を察したのか、みつおは明るい声で「すぐに答えを出すのは難しいでしょう。しかし覚悟はしておいてください」と告げ、話を打ち切った。
その後、みつおは改めて自己紹介をした。彼は畜産業の経営補佐をしていたが、歴史的な品種には詳しくないことを正直に語った。静子は、みつおの知識が現代の畜産に限られていることを理解しつつも、「基礎は変わらない」と考え、畜産計画の再開を提案した。みつおに意欲があるかが鍵であったが、彼は「この時代に骨を埋める覚悟です」と即答した。
みつおは、最初は現代への帰還を望んでいたが、今では戦国時代での生活に充実感を覚え、この世界で生き抜くことに意義を見出していた。彼の決意を確認した静子は、「織田領で畜産を牽引してほしい」と提案する。迷いながらも、足満の助言を受けたみつおは、その申し出を受け入れることを決めた。
畜産計画の詳細と導入種
静子は、鶏に加えて、黒豚アグーや山羊、猪の飼育を提案した。みつおは予想以上の規模に驚いたが、「牛は必須」とし、天然痘対策として牛痘を用いた種痘の導入も検討することとなった。
静子は、琉球王国の政治腐敗を利用し、黒豚アグーを取り寄せる計画を立てた。また、山羊の飼育を推奨し、乳製品の供給を視野に入れた。豚や山羊を加えることで、獣肉の種類が増え、食文化の向上にも寄与する狙いであった。
足満の過去と静子との関係
足満は、自身の過去について「覚えていない」と述べた。彼の名前も仮のものであり、本名は不明であった。静子が彼を発見した際、足満は満身創痍で倒れており、瀕死の状態であった。しかし、驚異的な回復力を見せ、半年後には退院した。
足満は戸籍も不明だったため、静子の両親が保証人となって引き取ることとなった。当初は現代の技術や設備に怯え、テレビを破壊するなどの騒動を起こしたが、次第に順応していった。やがて図書館に通い詰め、義務教育レベルの知識を独学で習得し、特に心理学に関心を持つようになった。
畜産・農業改革の推進
静子は、畜産計画を実行するため、信長の直営漁村を訪れた。牡蠣、海苔、わかめの養殖に加え、ホンモロコとドジョウの養殖も進めた。海苔やわかめの養殖は、麻繊維を用いた支柱式で行い、竹材を活用して大量生産を目指した。
また、ボラの燻製やカラスミの製造にも着手し、戦国時代の食料事情を改善する取り組みを始めた。これらの取り組みは、冬季の食糧不足を補うとともに、兵站の強化にもつながった。
信長の居住環境整備と濃姫の関与
信長は上洛後、敵対勢力の増加に備え、静子の村の住民を移住させる方針を打ち出した。その一環として、村の再開発を行い、防衛施設の強化や宿泊施設の建設を計画した。
しかし、その計画には濃姫の意向も強く反映されており、女性専用の宿泊施設やスイカ畑など、彼女の趣味が反映された要素が随所に見られた。
静子は、畜産計画に加え、信長の生活環境改善の要望にも応えなければならず、対応に追われていた。そんな中、光秀と秀吉から「信長のわがままをなんとかしてほしい」という手紙が届き、さらに頭を抱えることとなった。
戦国時代の変化と静子の課題
静子は、自身が推進してきた改革によって信長の生活水準が上がったことを実感しつつ、それが新たな負担を生んでいることに気づいた。彼女の技術革新は、織田領の発展に寄与していたが、それと同時に管理すべき領域も増えていた。
戦国時代に適応しつつも、未来を見据えた取り組みを進める彼女にとって、これからの課題は尽きることがなかった。
千五百六十九年三月上旬
信長の焦土作戦と堺の屈服
信長の苛立ちは二月上旬に限界に達していた。彼は三千の軍勢を率い、尼崎へと進軍した。港町である尼崎に矢銭を課したが、尼崎衆はこれを拒否した。堺衆に続くこの態度に、信長は軍事的圧力が必要だと判断し、尼崎四町を徹底的に焼き払った。この焦土作戦により諸都市は混乱し、恭順派、抗戦派、他勢力との連携を主張する派に分裂した。
この内部分裂こそが信長の狙いであった。結果、尼崎衆を扇動していた堺衆は屈服し、二月十一日には堺の事実上の接収が完了した。会合衆は矢銭二万貫を納め、兵士の雇用と牢人の受け入れを禁止された。これにより堺は大損害を被り、衰退する者と台頭する者が明確に分かれた。
今井宗久の台頭と信長の茶の湯への関心
信長にいち早く恭順した今井宗久は、信長の鉄砲・火薬の御用商人として勢力を拡大した。しかし、宗久が信長を歓待するために「茶の湯」に誘ったことが思わぬ結果を招く。信長は茶の湯に強い関心を持ち、文化的な象徴として茶器の収集を始めた。
彼は骨董や美術品の蒐集において、定石を無視し、武力と資金力を背景に一方的に買い漁った。この強引な収集は「茶器狩り」「名物狩り」として恐れられ、堺や京の茶人を震え上がらせた。しかし、茶器を集めても信長の苛立ちは完全には解消されなかった。
信長の生活環境への不満と静子の出立
信長は食住環境への不満を募らせ、特に寝所、入浴環境、食事が大きな問題であった。すでに九人の料理人が解任されており、解決が急務であったが、静子は信長の命令で尾張を離れられなかった。そのため、三月上旬まで秀吉と光秀は信長の威圧に晒され続けることとなった。
三月上旬、ようやく静子は京へ向かう準備を整え、五百の兵と共に出発した。彼女は強行軍で京に先行し、荷駄隊は秀吉の兵士の護衛のもと数日遅れで到着した。京に着くと、出迎えた光秀は胃痛を抱えながら静子に助力を求めた。
信長の味覚と京の文化の衝突
信長の食事への不満の原因を探るため、静子は彼の食生活を調査した。信長は京風の贅を凝らした料理ばかりを提供されており、武家出身の彼には塩分が不足していた。
京の文化人は、京の味を理解できない者を野蛮と見なしていたが、静子は武家文化と公家文化の違いを理解し、信長に尾張の家庭料理を提供した。鶏肉じゃが、味噌汁、小松菜のおひたしといった質素な献立は信長の心を満たし、彼の苛立ちは収まった。
光秀の謝辞と信長の信頼
信長の機嫌が改善したことで、光秀は静子に深く感謝した。彼は信長を前にしても動じない静子の胆力を高く評価し、「お館様の力となってくれ」と言い残して去った。
静子は光秀を真面目な人物と見たが、警戒を解かなかった。本能寺の変が起こるかは不明だったが、信長を守るために備える必要があると考えた。
信長の生活環境の改善と文化人の動揺
静子は信長の生活環境を整えるため、木桶風呂や布団などを京に運び込んだ。特に陶磁器の食器は、信長が文化人に意趣返しをするための道具となった。
京や堺の文化人は信長を「教養のない野蛮人」と見下していたが、彼が洗練された陶磁器を扱い、それを褒美として下賜したことで、彼らは衝撃を受けた。文化人たちは言い知れぬ恐怖を抱き、信長の力を改めて思い知った。
南蛮人との謁見と静子の役割
信長はフロイスとの謁見を控え、静子を同行させることにした。静子は顔を隠し、武家の正装を着用し、男装して参列することとなった。
謁見の場でフロイスは信長に金平糖と有平糖を献上した。信長はその珍しい菓子に興味を示し、静子に説明を求めた。静子が南蛮菓子の詳細を説明すると、フロイスとロレンソは驚き、静子の知識量に恐れを抱いた。
信長とフロイスの対話
信長はフロイスに対し、多岐にわたる質問を投げかけた。フロイスは自らの信仰を語り、「たとえ信者が一人になろうとも、私は日ノ本に留まる」と断言した。
信長はイエズス会の活動が布教だけでなく、植民地政策の一環であることを理解していたが、フロイスの信仰心が本物であると判断し、彼の布教を認めることに決めた。
静子の進言と信長の評価
信長は配下にフロイスの布教をどう思うか尋ねたが、まともな意見は出なかった。そこで静子に意見を求めると、彼女は「彼らが愛をもって布教するならば、某は彼らの友となりたい」と答えた。
その発言に対し、信長は「面白い」と笑った。静子の発言は単なる社交辞令ではなく、織田家と南蛮の関係を円滑にするための一歩であった。信長は彼女の考えに興味を示し、さらに彼女を側に置くことを決めた。
信長とフロイスの会見
信長はフロイスと二時間に及ぶ会見を行った。世界についての知識を求める信長は、フロイスに様々な質問を投げかけ、時折静子に確認を取る場面も見られた。会見は穏やかで文化的な雰囲気を保っていたが、フロイスの本来の目的は未だ達せられずにいた。彼は京での布教を許可する允許状を求めており、今回こそはと願っていた。銀の延べ棒を献上することで允許状を得ようとしたが、信長はそれを拒絶し、「賄賂を受け取れば腐敗した権力者と同じになる」と述べた。しかし布教自体には理解を示し、允許状の発行を検討することを約束した。
謎の従者とフロイスの疑念
会見後、フロイスは織田家に仕える一人の従者に注目した。頭巾を被り、少年のように高い声を持つその人物は、異様なまでにヨーロッパの文化に詳しく、聖書の一節すら暗唱していた。彼の正体に疑念を抱いたフロイスは、情報を集めようとしたが、詳細を得ることはできなかった。
宗論と日乗の暴走
その後、フロイスは天台宗の僧・朝山日乗と信長の前で宗論を交わした。二時間に及ぶ議論の末、日乗は怒りのあまり信長の長刀を抜こうとし、周囲の者たちによって取り押さえられた。信長は「口で敵わぬと知ると刃を抜くか」と日乗を咎めた。この一件の後も日乗は宣教師追放を訴え続け、ついには正親町天皇に嘆願し、『伴天連追放綸旨』を得た。しかし義昭はこれを退け、信長も対応を内裏に任せる形を取ったことで、宣教師の立場は微妙なものとなった。
濃姫と足満の対話
信長不在の間、濃姫は足満を呼び出し、彼が持つ三日月宗近の来歴について問い詰めた。足満はとぼけたが、濃姫は彼がその刀を大事に扱っていることを見抜いていた。さらに濃姫が彼の正体に言及しようとした瞬間、足満は突然小刀を投げ、襖の向こうに潜んでいた武田の間者を仕留めた。濃姫は「せっかちな男子じゃ」と嘲笑しつつも、足満が殺されたはずの人物であることを指摘した。結局、濃姫の探りに対し、足満は「奇妙な老婆に『己の役目を果たせ』と言われただけ」と語った。
静子の帰還と刀剣の収集
京での任務を終えた静子は尾張へ戻った。信長からの褒賞として童子切安綱と大包平を下賜され、次の功績次第では鬼丸国綱をも得られる可能性があった。彼女は刀剣を美術品としてではなく実用目的で収集しており、その行動は信長の関心を引いた。
ガラス職人の挑戦
静子はガラス職人を育成し、望遠鏡を作る計画を進めていた。しかしガラスの品質が低く、職人たちは挫折しかけていた。静子は「失敗を恐れるよりも、挑戦しない事を恐れなさい」と叱咤し、彼らに再挑戦の機会を与えた。彼らは「負けたくない」との思いで決意を新たにし、一年以内の成果を約束した。
反静子派の台頭と信長の裁定
静子の開発計画は資源を大量に消費し、一部の織田家臣の反発を招いた。木下秀長は静子を貶める策を講じ、反静子派を扇動した。その結果、信長は一年以内の成果を条件に静子の計画を容認した。静子は開発の存続を確実にするため、望遠鏡に加え、ガラス工芸品の制作にも着手した。
各国の諜報活動と静子の捜索
静子の技術によって織田領が繁栄する様子は、他国にも注目された。上杉謙信、武田信玄、北条氏政、そして徳川家康までもが静子の情報を集めるよう指示を出した。特に家康は信長を出し抜くのではなく、静子の技術を横から盗み取る戦略を採っていた。しかし当の静子本人は、自身の価値に気づかぬまま、日々の研究と開発に没頭していた。
千五百六十九年五月上旬
再開発事業の開始
四月上旬、静子の村を含む五つの村は信長から朱印状が発行され、正式に解体された。今後、岐阜周辺から知多半島の根本まで本格的な再開発事業が始まる。知多半島周辺には港町が作られ、それらと村を結ぶ道路が敷かれる。道祖神が一里ごとに配置され、旅行者の目印となり、休息所としても機能する。また、主要街道には五里ごとに水場、十里ごとに茶屋が設置され、旅行者が自由に利用できるように規定された。さらに、道祖神には通常の人間には分からない裏の情報が刻まれ、経緯度で管理されていた。
都市構造と行政機関の整備
尾張の主要都市は幹線道路で結ばれ、各地の村と港町へと通じる街道が整備される。都市の中央には立法機関・行政機関・司法機関が置かれ、西側には工業地帯と商業地帯、東側には農業地帯と醸造・漁業地帯が配置された。また、各地に軍事施設が建設され、美濃と尾張の国境、関ヶ原付近には要塞が築かれることとなった。この計画は短期間で実現できるものではなく、十年、あるいは数十年かかる大規模な国家プロジェクトである。
物流と商業の掌握
従来、寺社が独占していた物流と商業の制御を、信長は自らの手で行うことを決意した。しかし、寺社勢力のように長年培われた支配のノウハウがないため、信長は試行錯誤を繰り返しながら新制度を敷く必要があった。そのため、各責任者には定期報告書に加え、発生したトラブルとその対処法を記した障害対処報告書の提出を義務付けた。
度量衡の統一と用紙規格の制定
信長は美濃紙を公用紙として使用していたが、紙のサイズが統一されていない点に着目し、現代のA0からA6に相当する七つの寸法を制定する「用紙標準規格令」を発布した。さらに、静子が量産した「ものさし」を無料で配布し、制度の普及を図った。
村人の移住と静子への感謝
信長の移住計画により、静子の村の初期住民である三十名が村を離れることとなった。彼らは静子への感謝を述べ、「彼女がいなければ餓死していたかもしれない」と振り返った。一方で、村には新たに五十人の百姓とその家族が移住した。この移住には、静子が村の事に関与しなくなったことで生じた一部住民の不満を解消する意図も含まれていた。
尾張米の影響と供給問題
尾張米は、その美味しさから信長によって徳川や浅井、さらには義昭や帝にまで贈られ、大きな反響を呼んだ。しかし、尾張米は愛知県の環境に適応するように品種改良されており、他地域での栽培は困難であった。そのため、信長は尾張米の苗の提供を断り、生産量を制限しながら供給を管理する方針を取った。
食文化の発展とパンの試作
静子はおねの要望に応え、ポルトガル由来のパンを試作した。戦国時代の日本では天然酵母を自作するしかなく、彼女はレーズン酵母を用いた食パンの製造に取り組んだ。試作品は成功し、タマゴサンドや鶏南蛮サンドとして提供された。また、じゃがいもの冬栽培にも成功し、今後の食糧生産に新たな可能性をもたらした。
農業実験と空中栽培
静子は新たな農業手法として「稲のバケツ栽培」と「農作物の空中栽培」の実験を行った。特に空中栽培は、通常畑を作ることができない山城などでの作物栽培に適しており、籠城戦の際の食料確保に有効と考えられた。薩摩芋の多層栽培により、限られた空間での高収量が期待された。
茶葉の契約と魚粕の活用
静子は岐阜の茶農家と契約し、煎茶、玉露、かぶせ茶の三種類を独占的に確保した。この契約の背景には、小魚の処理に困っていた漁村との取引があった。彼女は魚粕を肥料として利用し、茶畑の土壌改良に活用することで、双方に利益をもたらした。
近衛前久との会談
五月上旬、近衛前久が岐阜を訪れた。彼は信長との関係を模索し、静子の真意を探るための会談を望んでいた。静子は彼を丁寧にもてなし、茶碗蒸しや櫃まぶしなどの料理を振る舞った。前久はこのもてなしを受け、静子の計算された行動に感銘を受けた。彼女の目的は近衛家を織田陣営に取り込むことであり、そのための交渉を進めていた。
前久の決意
食事の席で静子の本音を聞いた前久は、彼女の交渉の巧みさを理解し、焦って決断を下すことの危険性を認識した。彼は一旦友誼を深めることを優先し、取引を急がずに慎重に進める決意を固めた。そして、再度の会談を求めることで、静子との関係をより確かなものとする道を選んだ。
このように、静子は村の発展を推進しながらも、食文化や農業の改革、政治的交渉にも積極的に関与し、信長の改革を支える重要な存在となっていた。
千五百六十九年五月中旬
会談後の策略と前久の罠
静子は前久に醤油、出汁味噌、梅干しを土産として渡した。前久は喜んで受け取ったが、これが静子の仕掛けた罠であった。日々の食事にそれを使い切った後、味気ない粗食に耐えられず、次の会談を待ち焦がれる自分に気付いた前久は愕然とした。
本願寺と前久の関係
静子の真の目的は、前久を取り込むことではなく、本願寺宗主顕如の長男・教如と前久の猶子関係を解消させることにあった。石山本願寺は信長の宿敵であり、石山合戦は十一年にも及ぶ大戦となった。前久は第一次信長包囲網の調整役として本願寺を説得し、反信長の立場を明確にさせた人物であった。
本願寺の権力構造と守護使不入権
本願寺は庶民の支持を得ることで勢力を拡大したが、膨大な門徒と所領を維持する力を持たなかった。解決策として『守護使不入権』の獲得があった。これにより、本願寺は外部の干渉を排除し、独立した支配体制を築いた。そのため、宗主は五摂家の猶子となり『門跡寺院』の資格を得る必要があった。顕如は九条家の猶子となることで本願寺の地位を確立した。
前久との再会と交渉
二週間後、静子は再び前久と会談を行った。前回より警戒は薄れたものの、信頼関係の構築には至らなかった。前久は静子の意図を探るため、「私にどのような利があるのか」と問いかけた。静子は織田家の意向とは関係なく独断で行動していることを告げ、前久の狙いが公方足利義昭と二条関白の排除であることを指摘した。
前久は静子の話に賛同したが、それに見合う対価を求めた。彼は脚病に苦しむ知人の治療を要求し、静子はこれを了承した。脚病は当時不治の病とされていたが、静子はビタミンB1不足によるものと看破し、食事療法による回復を確約した。
治療と前久の決断
七日後、脚病患者の症状が改善し、前久は約束通り織田陣営に加わることを誓った。また、教如との猶子関係の解消にも協力すると申し出た。しかし、それだけでは不足とし、織田信長との会談の場を設けることを要求した。静子は信長の了承を得るため時間を求め、前久はそれを待つ間、静子の別邸に滞在することを決めた。
信長と前久の対面
信長は静子の働きを評価し、前久との会談に応じた。前久は静子の才覚を高く評価し、彼女を猶子に迎えたいと申し出た。信長はその影響を懸念しつつも、時期を調整することを条件に受け入れた。前久は静子がいずれ時代に求められる存在になると見込み、猶子関係を利用して彼女の立場を強固にしようと考えていた。
技術革新と産業の発展
静子のもとでは、歯車やクランクの研究が進み、水車式洗濯機の量産化が実現した。また、醸造街では米酢、味噌、醤油、日本酒などの生産が始まり、塩の流通拡大により尾張・美濃では庶民も塩を容易に入手できるようになった。
技術革新が進むにつれ、静子のもとには大量の物資が贈られるようになった。中には彼女を引き抜こうとする意図を含むものもあったが、静子はそれを拒み、信長の軍備に供する形で処理した。
清酒の開発と試飲
醸造街では清酒の試作が進められ、半年熟成の初吞切りが行われた。信長と前久はその透明な見た目と芳醇な香りを高く評価し、清酒の可能性を確信した。清酒は濁酒と異なり、料理との相性が良く、食文化の発展に寄与することが期待された。
信長の戦略と食糧政策
信長は食料供給の安定が治安維持に直結すると理解し、食の不安を解消する政策を推進した。静子の技術により、尾張・美濃の食糧生産は飛躍的に向上し、信長の軍事力を支える基盤となった。
視察の最後、信長は静子の才覚に感嘆しつつ、彼女がもたらす可能性を楽しみにしていた。
千五百六十九年六月下旬
信長の動向と間者の混乱
信長は伊勢侵攻の兆しを一向に見せず、間者たちは報告内容に頭を悩ませていた。軍事的な動きが皆無であり、信長は小規模な角力大会を催したり、時折行方をくらませたりしていた。その実態は静子の村へ赴き温泉で寛ぐというものだったが、間者たちはその詳細を掴めなかった。結果として、「信長は遊びに興じている」としか報告できず、雇い主の怒りを買い、責められた間者たちは無理を重ねて捕縛されたり、事実を捏造して報告するようになった。こうして複数の経路から送られる情報は支離滅裂となり、さらに混乱を招く悪循環に陥っていた。
囲碁と将棋による戦略的思考の養成
信長が熱中していたのは単なる遊戯ではなく、囲碁や将棋の研究と統合だった。戦国時代には統一されたルールが存在せず、信長は各流派の規則を整理し、「尾張囲碁」「尾張将棋」として規定を設けた。その過程で静子の知識を参考にし、現代の洗練されたルールと戦国時代の特色ある規則を融合させた。この取り組みの目的は、配下の「想像力」を鍛えることにあった。信長は、有能な人材には豊かな想像力があることに気づき、それを養う手段として遊戯を選んだ。遊戯ならば本人が楽しみながら取り組め、外部からは文化人として見られる利点もあった。
信長は商人や百姓にも遊戯を広め、大会を頻繁に開催し、優勝者には奨励金と名誉を与えた。彼の意図は、相手への敬意を持ち全力を尽くす精神を育むことであり、遊戯を通じた教育の場を提供していた。しかし、間者たちはその意図を正確に把握できず、信長が単なる娯楽に興じていると誤認していた。
みつおの帰還と予期せぬ同行者
そんな中、家畜を求めて旅立っていたみつおが帰還した。彼は琉球在来豚のアグーや山羊の入手に成功し、さらには琉球国王から下賜品を受け取っていた。しかし、問題は彼が二人の同行者を連れて帰ってきたことだった。一人は華やかな着物を纏った幼い少女、もう一人は彼女の侍女と見られる女性だった。静子は最初、奴隷でも買ったのかと考えたが、少女の立ち居振る舞いには気品があり、百姓の類には見えなかった。
みつおの説明によると、琉球で飲み比べをし、薩摩に戻った際に捕らえられたが、再び飲み比べに勝った結果、少女を嫁に迎えることになったという。静子は困惑しつつも、騒動に関わらないよう距離を取ることにした。最終的に、みつおは状況を受け入れ、少女である鶴姫と正式に夫婦となることになった。
静子のスッポン養殖計画
静子は新たにスッポンの養殖に取り組んだ。尾張ではタニシが大量発生しており、それをスッポンの餌として活用する計画だった。スッポンの繁殖には適切な環境が必要であり、養殖池の設計には細心の注意を払った。産卵場の整備や温度管理の工夫を凝らし、順調に孵化が進んでいた。
しかし、スッポン養殖が話題になるにつれ、商人たちは漢方薬としての需要を見込み、信長もまたスッポン料理を求めるようになった。養殖されたスッポンの一部は食用とされ、静子たちはスッポン鍋を振る舞うことになった。
スッポン鍋の饗宴
調理は足満とみつおが担当し、スッポン鍋と雑炊が用意された。秀吉や竹中兄弟をはじめとする武将たちは、スッポンの味に驚嘆し、その旨味を堪能した。スッポンの肉は鶏肉に似た弾力を持ち、独特の旨味が口いっぱいに広がった。ポン酢を加えることでさらに味が際立ち、鍋を囲んだ面々は次々と箸を進めた。
食事を終えた後、秀吉は鶴姫の件について話を切り出した。他国の姫が織田の家臣に嫁ぐことは国防上の問題となりうるため、彼女の処遇が議論された。最終的に、みつおと鶴姫の婚姻は認められたが、監視役が置かれることになった。
信長と足満の戦略論
信長は濃姫に連れられ、足満との会談に臨んだ。そこで、足満の正体がかつての将軍・足利義輝であることが明かされた。彼は新たな戦略として、伊勢の北畠家を仮想敵とし、麻疹の流行や農地の破壊を用いた間接的な戦術を提案した。単なる兵器開発ではなく、敵を無力化させる方法を模索するべきだと説いた。信長はこの提案に興味を示し、より実効性のある戦略を考案することになった。
梅酒と新たな試み
一方、静子は黒糖梅酒の試作を行い、薬湯として利用することを考えた。彼女は梅酒を「梅薬湯」と称し、健康維持の一環として提案した。また、信長の命により梅干しが上杉謙信に贈られ、その味が高く評価されたことで、武将の間で静子の梅干しが広まることとなった。
パイナップルの導入
静子はスナックパインの収穫に取り掛かった。これは小ぶりで甘みが強く、手で簡単に千切れる品種だった。しかし、彼女が試食しようとした矢先、信長と近衛前久が現れ、興味を示した。結局、二人にすべて食べられてしまい、静子の手元には苗だけが残った。
戦国小町苦労譚 小話
怒りの武神 本多平八郎忠勝
和田山城の戦いと忠勝の猛攻
和田山城では、稲葉良通率いる織田軍の一隊とともに徳川軍が参戦していた。徳川軍はわずか千名であり、織田軍の一部と見なされる規模であった。しかし、その中でひと際目立つ武将がいた。本多平八郎忠勝である。彼は蜻蛉切を振るい、六角兵を次々と斬り伏せていった。雑兵四十名が忠勝に襲いかかったが、彼の圧倒的な気迫に足が竦み、戦意を喪失した。忠勝は槍の一振りで三人を一瞬にして斬り裂き、戦場を地獄絵図へと変えた。その猛威に六角兵は戦意を喪失し、散り散りに逃げ去った。
忠勝の怒りの理由
遠巻きに戦場を見守っていた榊原康政は、忠勝の異常なまでの猛りに疑問を抱いた。正重がその理由を尋ねると、康政はため息混じりに答えた。忠勝は腰に下げていた静子特製の握り飯を六角兵に踏み潰され、それに激怒していたのである。
静子の贅沢な鰻丼
信長が上洛した頃、静子は京の民を雇い、宇治川で天然の鰻を捕獲させていた。旬を外れていたが、静子にとっては関係なく、彼女の目的はただ豪勢な鰻丼を食べることだった。雇った者たちは川に飛び込み、次々と鰻を捕獲した。静子は良質な鰻を捕まえた者に報奨を与え、さらに競争心を煽った。その結果、太い鰻が十匹集まり、彼女は七輪で焼き上げ、贅沢な二段重ねの鰻丼を完成させた。信長もその味に満足し、静子の料理を賞賛した。
狼たちのベストポジション争い
静子に懐いた狼の群れは、彼女の左側で眠る権利を巡って激しい競争を繰り広げていた。彼らにとって最上の位置は静子の左側であり、右側は不人気であった。そのため、群れはトライアスロン形式で競い、勝者のみがその特等席を得ることができた。特にカイザーは甘えん坊であり、親のヴィットマンを超えるほどの大きさに成長してもその性質は変わらなかった。今日もまた、狼たちは静子のそばを求めて熾烈な競争を繰り広げた。
信長の河川治水計画
尾張と美濃を手中に収めた信長は、水害という新たな課題に直面していた。彼は洪水の被害を防ぐため、コンクリートを用いた治水工事を計画し、貯水池の建設や河川の護岸工事に取り組んだ。この計画は木曽三川の完全分流を視野に入れた大規模なものであり、現代の河川改修と類似した構想であった。治水事業は領民の支持を得るための建前であり、信長の本当の狙いは伊勢湾の制海権の掌握と本願寺勢力の排除にあった。
戦国時代の歯磨き
静子は現代の習慣を戦国時代に持ち込み、歯磨きを推奨した。彼女は茄子のヘタを黒焼きし、塩を混ぜた歯磨き粉を作り、馬の鬣を利用した歯ブラシで口腔ケアを行った。これにより、虫歯や歯周病を防ぐ習慣が広まり、信長やその家臣たちも静子の影響を受けた。結果として、尾張・美濃では一時的に茄子の価格が高騰した。
麦とろご飯と家康の葛藤
徳川家康は、尾張陣営で静子が自ら食事を作る姿に驚いた。静子は天然の自然薯をすり下ろし、出汁や調味料を加えたとろろを麦飯にかけて供した。家康はその香りに抗えず、最初は葛藤したものの、最終的には麦とろご飯を三杯もおかわりし、満足げに食べた。後日、家康は忠勝に静子からレシピを聞き出すよう命じた。
濃姫と間者の駆け引き
濃姫は仁比売の情報を狙う間者の存在を見抜き、偽の情報を巧みに流して撹乱した。彼女は間者の動向を冷静に見極めながら、巧妙に信長の計略を支えた。彼女の手法は、事実と虚偽を織り交ぜ、敵を混乱させる高度な情報戦であった。
麻と米を利用したバイオプラスチック
静子は、米と麻幹を混ぜたバイオプラスチックの開発に着手した。岐阜米の大増産により、ついに資源の確保が可能となった。彼女は麻を全国に栽培させ、茎の部分を織田家に提供すれば繊維を無料で加工できる仕組みを導入した。これにより、麻の実の常食化も進み、全国的な栄養改善にも寄与した。バイオプラスチックが完成すれば、戦国時代の生活レベルは飛躍的に向上すると静子は確信していた。
梅干し作りと保存食の生産
静子は大量の梅を用いて梅干し作りに取り組んだ。塩分を多く含む梅干しは、戦国時代では貴重な保存食であり、大量の塩を必要とした。彼女は選果機を活用して作業を効率化し、戦国時代には珍しい本格的な梅干し製造を進めた。これにより、軍の食糧事情の改善にも大きく貢献した。
静子の計画と実践は、戦国時代に新たな変革をもたらし、信長をはじめとする多くの者たちに影響を与えた。
同シリーズ
戦国小町苦労譚 シリーズ
小説版


















漫画







その他フィクション

Share this content:
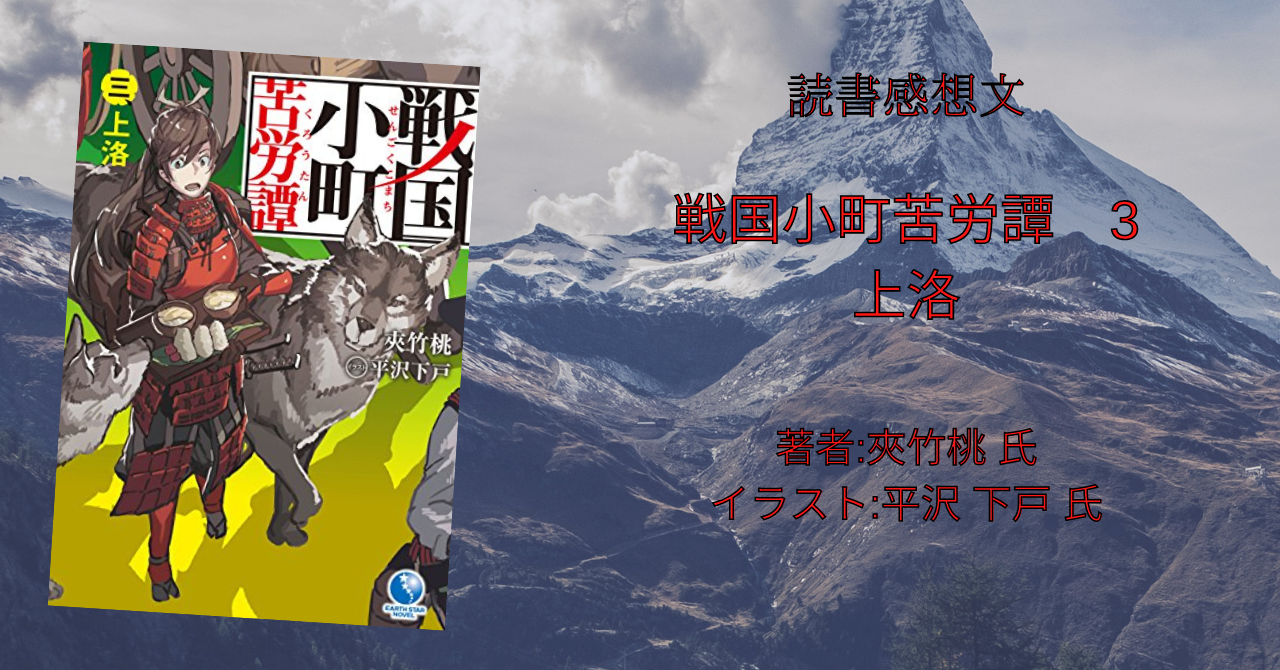

コメントを残す