どんな本?
『「若者の読書離れ」というウソ』は、飯田一史氏による新書である。本書は、近年広く信じられている「若者は本を読まない」という通説に疑問を投げかけ、中高生の読書実態をデータと具体的な事例をもとに検証している。
著者プロフィール
• 飯田 一史:著述家、ライター。出版、書店、読書に関する分野で多数の執筆活動を行っている。代表作に『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』などがある。
書籍の特徴
本書の特徴は、若者の読書傾向に関するデータ分析と、実際に中高生に人気のある書籍の具体的な紹介を組み合わせている点にある。著者は、中高生が本に求める「三大ニーズ」と、それに応える「四つの型」を提示し、現代の若者がどのような本を好むのかを明らかにしている。また、「TikTok売れ」の実情や、ライトノベルの読者層の変化、短編集の需要拡大など、Z世代のカルチャーにも深く切り込んでいる。
出版情報
• 出版社: 平凡社
• シリーズ: 平凡社新書 1030
• 出版年月: 2023年6月
• ISBN: 9784582860306
• ページ数: 264ページ
• 定価: 1,078円(本体980円+税)
読んだ本のタイトル
#「若者の読書離れ」というウソ
著者:#飯田一史 氏
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか
「最近の若者は本を読まない」のは本当なのか?「中高生に読まれている本」の綿密な調査と分析を通し、十代の読書の実態を検証する。
「若者の読書離れ」というウソ
この20年間で、小中学生の平均読書冊数はV字回復した。そんな中、なぜ「若者は本を読まない」という事実と異なる説が当たり前のように語られるのだろうか。各種データと10代が実際に読んでいる人気の本から、中高生が本に求める「三大ニーズ」とそれに応える「四つの型」を提示する。「TikTok売れ」の実情や、変わりゆくラノベの読者層、広がる短篇集の需要など、読書を通じZ世代のカルチャーにも迫る。
感想
二つのショック!
若者(ティーンズ)の読書離れ。学生読書量グラフと書店売上ランキングのデータを用いての、子どもの読書量は一定しておりスマホやPCが普及した現在においても特段の変化は見られないらしい。
“読書離れ”を若者(ティーンズ)達のせいにしているが実態は、小学生は読書習慣をつけさせるための活動が効いており現在最高の読書量を誇り。
中学生、高校生は昔とあまり変わらない。
大学生の読書量低下は絶対数が増加し社会人とほぼ変わらぬ比率になっただけ。
そうなると”読書離れ”しているのは絶対数の多い大人となる。
まずそれがショック。
別のショックは、ティーンズ向けだったラノベが大人向けになっていた、、
ティーンズ向けじゃなくなったせいでティーンズ達は行き場を無くし、一部は児童書へ向かったりしたらしい。
情動・衝動優位なティーンズ達の心に刺さるモノは、、、
「三大ニーズ」
・正負両方に感情を揺さぶる
・心春期の自意識、反抗心、本音に訴える
・読む前から得られる感情がわかり、読みやすい
「四つの型」
・自意識+どんでん返し+真情爆発
・子供が大人に勝つ
・デスゲーム、サバイバル、脱出ゲーム
・余命もの(死亡確定ロマンス)と「死者との再会・交流」暴力系、生死
これはティーンズに限らず、老若男女を問わず幅広く好まれる雛形かと・・
とにかく、そんな彼等の要求に応えられる作品は現在、ラノベには無く。
売り上げが半減したのはラノベの読者ターゲットが変わってしまったせいであるらしい。
でも、「キノの旅」「SAO」「物語シリーズ」の人気は根強く。 最近の物でも「ようこそ実力至上主義の教室へ」「RE:ゼロから始める異世界生活」「探偵はもう死んでいる」も人気になっている。
物語シリーズ以外は挫折してるは・・・ 感性が合わなかったもんな・・・
ただ、この本に載っていた「わたしの幸せな結婚」は大正時代の陰陽系と知り買って読んだら面白かった。
ラブコメのニーズはかなり減ってしまったらしい、私が大好きな下ネタ系はもっとマイナー・・・ 週刊少年ジャンプでもこのジャンルは全滅したらしい。
確かにそうだ・・
この本でも例に出されている「転生したらスライムだった件(転スラ)」は下ネタ要素がほぼ無くて読みやすい印象だった。
現在は『小説家になろう』(なろう系)のようなネットで公開され、ある程度人気になって実績のあるタイトルを書籍化するのが現在の傾向。
確かに、私が最近買ってるタイトルの8割以上が”なろう系”。。
ボカロ系は完全にチンプンカンプン・・・ そんな世界があったとは、、状態。
一般文芸だと、「氷菓」(古典部)がアニメ化を機に売り上げが上がり継続しているらしい。
あと、「天久鷹央」シリーズも人気らしい。
その後は需要にマッチしていると評判な「本屋大賞」などのランキングを参照してティーンズ達の読書傾向を当てはめると若干のズレが見受けられらしい。
結局は売る側と買う側、作る側と読む側の需要と供給はなかなかマッチングしない。
それを常に当てたら凄いけど、、
とにかく、若い子が本を読まないのは大人が読まないから。
親が読まないのに、その子供が読む訳がない。
それなのに「若者の読書離れ」と言うのは理不尽だとこの本を読んでたら余計に感じた。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
備忘録
はじめに
中高生の読書実態への関心
筆者は本書を、中高生の読書実態を解明することを目的に執筆した。タイトルが関心を引くように設計されているが、実際の内容は「どのくらい、どんな本を読んでいるのか」に焦点を当てている。教育関係者、保護者、出版関係者など、若者と関わる立場の人々にも理解を深めてもらう意図が込められていた。
断片的な印象と現実の乖離
社会では「若者は文学作品を読まない」「読書から離れている」といった言説が頻繁に語られていた。多くの大人が「アニメやドラマ原作が中心」「ライトノベルが好まれる」といった限定的な印象を抱いていたが、それらは部分的な情報に過ぎなかった。筆者は、押しつけがましい読書指導は逆効果であるとし、まずは実態把握が必要だと主張した。
読書習慣のV字回復とジャンルの変遷
データによれば、2000年代以降、小中学生の読書量はV字回復を遂げていた。一方で文庫ライトノベル市場は縮小し、かつて中高生に人気を博していたタイトルはランキング上位から姿を消した。「YA」と呼ばれるヤングアダルト向けレーベルの刊行数も減少しており、「YA棚」が存在しない書店も珍しくなかった。
誤解と施策のズレ
筆者は、若者の読書に関する施策が「イメージ」と「べき論」に基づいている点を問題視した。現状把握をせずに「こうするべきだ」と語る大人の論調は、結果として若者に対する一方的な評価や押しつけとなり、良好なコミュニケーションの妨げとなっていた。
本書の独自性と手法
本書は、中高生の読書実態そのものを主題とした希少な書籍である。既存のブックガイドとは異なり、相手を理解することに主眼が置かれていた。筆者は10代本人への直接取材は行わず、学校読書調査やカスタマーレビュー、読書感想サイトに現れた声を補助資料としながら、主に統計データと書籍内容の分析を用いて傾向を抽出した。
分析の焦点と方法論
筆者は「10代が好む本を実際に読み込む」という方法論を採用した。その目的は、実際の書籍内容を検証することで、作品に共通する傾向を浮き彫りにすることにあった。「中高生が読んでいる本の内容に即して検討した本」はこれまで存在しておらず、主観であっても分析には意義があると考えていた。
表層情報と実際の嗜好の違い
ドラマやアニメ原作作品が読まれていることは事実であるが、それはあくまで作品を知るきっかけに過ぎなかった。中高生が選ぶ本には、他世代のベストセラーとは異なる独自の傾向が見られ、それらは作品の中身を丁寧に読むことでしか把握できないと筆者は結論づけた。読書傾向の本質を理解するには、表面的なデータではなく内容の深掘りが不可欠であった。
第一章 10代の読書に関する調査
読書冊数と不読率の推移
1980年代から1990年代にかけて小中高生の読書量は減少し、不読率は上昇したが、2000年代に入りV字回復を遂げた。特に小学生は史上最高の平均冊数を記録し、中学生は微増、高校生は横ばいとなった。回復の背景には官民連携による読書推進策があった。
政策的な支援と制度の整備
1990年代には肥田美代子らが主導した議員連盟が読書環境の整備を後押しし、文部省も「調べ学習」の導入や図書館整備計画を推進した。2001年には「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行され、朝読やブックスタートなどの政策が全国で浸透した。
読書習慣の形成と学校の役割
朝読の導入により、小中学生の約8割が学校で本を読む時間を持つようになった。一方、高校生は朝読実施率が約45%に留まり、不読率が高止まりする要因の一つとなっている。学校外読書に限定すると不読率は高く、学校環境が読書習慣の形成に強く寄与していることが示された。
雑誌離れと出版市場の変化
書籍とは対照的に雑誌の不読率は上昇し、平均読書冊数は激減した。特に1980年代中盤には雑誌が月に数冊読まれていたが、2022年にはその数が大幅に減少した。出版市場全体でも雑誌の売上は激減し、需要はウェブやスマホなど他メディアに吸収された。
書籍市場の堅調と政策の偏り
出版市場では書籍の売上は減少しておらず、電子書籍を含めれば1兆円規模を維持していた。これは読書推進策が「書籍偏重」であった結果であり、雑誌は政策的な対象外とされてきた。書籍が「読むべきもの」とされ、児童書の販売も堅調に推移している。
ライトノベル市場の縮小
2000年代に成長した文庫ラノベ市場は2012年をピークに半減以下となった。中高生の読書量は維持されていたにもかかわらず、市場は縮小した。これは読者層の中心が中高生から大人へと移り、「中高生向け」というジャンル認識が薄れたためである。
なろう系の台頭と市場構造の変化
「小説家になろう」発の作品群が書籍化され、「単行本ラノベ」として新たな市場を形成した。これらは読者の人気が反映されたものであり、売上の初速や重版率が高かったため、従来の文庫ラノベよりも商業的に成功した。結果として市場は「大人向け」に再構成され、中高生の支持を失った。
文庫ラノベ市場の二極化と構造的失敗
なろう系の拡張に伴い、文庫ラノベ市場では10代読者の離脱が顕著になった。従来の中高生市場に戻ることなく、大人向けに転換したことが、全体の市場縮小を招いた。児童書市場の安定を踏まえれば、中高生向けの読者層を維持していれば衰退は避けられたと筆者は指摘した。
ケータイ小説の再興と柔軟な対応
スターツ出版は「野いちご」や「Berry’s Cafe」など投稿サイトと連動し、ケータイ小説文庫を多様なレーベルで展開した。読者の嗜好の変化に応じて作品傾向も進化し、感情描写を重視する作品が主流となった。さらにTikTokによる拡散やコミカライズ事業を成功させたことで、最高益を記録した。
読者ニーズへの対応と差別化戦略
スターツ出版は、作品のレーベル分化によって読者の混乱を防ぎ、明確なターゲティングを維持した。読者層の拡大に応じた作品提供が成功要因となり、ラノベ市場との差を明確にした。恋愛小説においても価値観の変化に対応し、共感を得る展開を重視した点が支持を得た。
高校生と大学生の読書傾向
高校生の読書状況は改善されたものの、読書冊数の伸び悩みは朝読の未導入や政策的支援の希薄さが一因であった。大学生では不読率が上昇傾向にあり、大学進学率の上昇と入試制度の多様化により、本を読まない層の進学が影響していた。
大学生の変容と不読率の背景
大学生の内実が変化し、かつてよりも多様な学力・関心を持つ学生が増加した。進学率の上昇により、読書習慣のない層の大学進学が一般化し、不読率の上昇に繋がった。全国大学生協連の調査でも、50%前後の学生が読書時間を持たないとされている。
「若者の本離れ」という言説の誤解
統計上、高校生や大学生の不読率は日本人全体とほぼ同等であり、「若者だけが本を読まない」という見方は誤りであった。現代の読書傾向は、年齢にかかわらず二極化しており、「ふたりにひとりは読書をしない」という構図は若者にも大人にも共通していた。
読めないことと読まないことの境界
筆者は、「読まない」人の存在を論じる上で、「読めない」人の存在も見落としてはならないと主張した。学習障害や発達性ディスレクシアの人々は、文字の読解に困難を伴い、紙の本を読むことが実質的に不可能である。また、視覚や触覚による情報処理が優位な人々にとって、読書は適さない学習手段となる。このような背景を持つ人々の「本を読まない」行動は意図的な選択ではなく、構造的な困難に起因していた。
発達特性と読書の意欲
筆者は自身の息子の例を挙げ、ADHDに起因する読書や学習の困難さを指摘した。意欲や能力にはグラデーションがあり、「できない」と「やらない」は明確に区別できるものではなかった。読書が困難な人々の存在を、単に「本嫌い」として切り捨てる姿勢は不適切であり、外部からの支援によって全員が読書好きになるという期待も現実的ではなかった。
読書行動における遺伝の影響
行動遺伝学の観点からは、読書を好むか否かも、半分程度は遺伝的要因によって決定されているとされた。安藤寿康氏の研究によれば、家庭環境が読書量に及ぼす影響はごくわずかであり、遺伝の影響が統計的に有意であった。読書量の個人差は先天的なものであり、後天的な環境によって大きく変えることは難しいとされた。
高校生以上における不読率の安定性
文化庁や毎日新聞社の調査によれば、日本人全体の不読率は長年にわたりほぼ一定であり、スマートフォンの普及とも関連性が見られなかった。高校生の読書冊数も、1960年代から月1冊台で安定しており、インターネットやモバイルデバイスの登場以前と以後で大きな変化はなかった。これらのデータは、読書行動の遺伝的安定性を裏付けるものであった。
読書時間の分布と遺伝的限界
読書量だけでなく、読書にかける時間もまた遺伝的影響を強く受けていた。大学生や社会人の読書時間は1日あたり約30分前後で推移しており、小中学生の読書時間とも大差がなかった。遺伝的に決まっている「セットポイント」によって、個人の読書量には限界があるとされ、それは努力だけでは大きく変化しないと説明された。
日中韓における読書事情の比較
日本、韓国、中国の読書実態を比較すると、小中学生においては日本の読書冊数が最も多かった。韓国や中国では高校生まで読書率が高かったが、冊数は日本に及ばなかった。背景には受験制度の違いや部活動の有無などがあり、日本の子どもたちは忙しいながらも比較的多くの本を読んでいた。成人の読書率は3国間で大差はなかった。
TikTokと若年層の読書傾向
2020年以降、TikTok上での本紹介動画が「TikTok売れ」として注目されたが、実際には既に若者に人気のあった作家や作品が再注目されたケースが多く、新規性は低かった。特定の作品に関心が集中する傾向は見られたが、若年層全体の読書量を押し上げる効果は限定的であり、高校生女子以外には顕著な影響は確認されなかった。
TikTokの販売促進としての限界
TikTok経由での書籍販売は一時的なものであり、動画の効果が持続するには出版社・書店・インフルエンサーの連携が必要であった。品切れ時の再販タイムラグや、投稿数の少なさ、紹介作品の偏りなどが影響し、書籍の大規模な販促手段としての限界が明らかとなった。また、TikTokユーザーの慎重な選書傾向も影響を与えていた。
「若者の読書」の実態の再確認
調査結果を総合すると、日本の若年層の読書率や冊数は過去と大きく変わっておらず、不読率は高校生以上で成人と同等に達していた。文庫ラノベ市場は中高生向けからの脱却に失敗し縮小した一方、児童書市場は堅調であった。読書推進政策が中学生以下に集中していること、高校生以降の変化が乏しいことなどが特徴として浮かび上がった。
結論:読書量と環境の限界
遺伝的な傾向により、高校生以上の読書量には明確な上限があり、外部環境をいくら整えてもその枠を大きく超えることは困難であった。出版業界の不況は雑誌需要の低下と可処分所得の減少に起因しており、書籍需要は依然として堅調であった。若年層の読書実態は、メディアが描くステレオタイプとは異なり、数字に基づく冷静な分析が必要とされていた。
第二章 読まれる本の「三大ニーズ」と「四つの型」
10代の脳と衝動性の優位性
10代の脳は大脳辺縁系が先に発達し、前頭前野の成熟が遅れる構造により、感情や衝動が理性より優位に立つ状態にあった。そのため、損得を冷静に見積もるよりも、得られる報酬を過大に評価して行動する傾向が強かった。これはヒトの進化過程において集団を維持し、生殖活動を促す上で必要な特性でもあったが、近代以降の教育制度や寿命の延伸により、この衝動的な10代の性質が社会的適応の困難さを引き起こす場面も増加した。
中高生が好むフィクションの特徴
中高生が求める物語には、感情を強く揺さぶる要素、思春期特有の自意識や本音に触れる内容、読む前から感情の予測が可能な読みやすさという三要素が求められていた。複雑な描写や社会的テーマ、仕事や大人の世界を描いたものよりも、個人の感情や関係性に焦点を当てた内容が好まれ、特に自分たちと年齢の近い登場人物による青春劇が支持を得ていた。
読まれる本の四つの型
中高生の読書傾向には、共通するプロット型が存在した。①自意識+どんでん返し+真情爆発、②子どもが大人に勝つ、③デスゲーム・サバイバル、④余命ものや死者との再会・交流である。これらの型はジャンルを超えて登場し、三大ニーズを効果的に満たす形式であった。
住野よる作品の人気の背景
住野よるは、2010年代後半以降で中高生に最も読まれた作家の一人であり、『君の膵臓をたべたい』をはじめ、複数の作品が学校読書調査で上位にランクインし続けた。作品には「自意識+どんでん返し+真情爆発」型の構造があり、主人公が他者との関係を通して感情を吐露し、成長していく様が中高生に共感をもって受け入れられていた。
本音の吐露と現実との乖離
若者は本音を語りたいという欲求を持ちつつも、実際には他者との関係に踏み込むことを避ける傾向が強かった。社会構造の変化や人間関係の流動化により、深い人間関係を築きにくくなり、現実では「エモい本音のぶつけ合い」が困難なものとなった。そのため、物語の中でのみ理想化された感情の吐露が求められ、虚構に癒やしや代償的体験を求める傾向が強まった。
『人間失格』の根強い人気
太宰治の『人間失格』は、「自意識+どんでん返し+真情爆発」型に類似する作品として、中高生の間で再評価された。人気の背景には、メディアミックス作品『文豪ストレイドッグス』や『文豪とアルケミスト』の影響があったが、それ以上に作品自体が10代の内面に強く訴えかける内容を持っていたことが要因であった。登場人物の内面にある自己否定や葛藤が、中高生の複雑な感情に共鳴したのである。
現実との距離が物語の需要を生む構造
現代社会では深い人間関係を築くことが難しくなり、感情を共有し合う関係が希薄化していた。そのような社会構造の変化が、逆に物語における友情や感情の爆発的な吐露への需要を高めていた。現実にないものを虚構で補おうとする動機が、物語の選好に強く影響していたのである。
ハイスペックな主人公への共感
『人間失格』の主人公・葉蔵は、自己卑下しつつも実際には高い能力と容姿を持つ人物として描かれていた。彼は破滅的な行動を繰り返しながらも、周囲に助けられ続けた存在である。このような人物像に対し、読者は自らを重ねて安心感を得ていた。若者が物語の主人公に共感し、陶酔するためには、「普通」よりもむしろ「特別」である必要があった。思春期における「自分は特別だ」という感覚が、『人間失格』のようなハイスペックな人物像と親和性を示していた。
思春期の自意識と反抗の構図
葉蔵の「道化」的行動や過剰な自意識は、思春期特有の繊細さや反抗心を体現していた。その筆致は住野よるの作品に通じ、若者が抱える生きづらさや本音の吐露を描いた内容が共感を呼んでいた。葉蔵の極端な反応や感傷的な語りは、10代読者の心理に響いたのである。
読みやすさとリアル系の親和性
『人間失格』は文章が平易で分量も少なく、現代の若者にとって入りやすい近代文学作品であった。太宰治の自殺との関連から、作品を「半実話」として受容しやすく、感情移入が容易であった。リアル系作品はノンフィクションだけでなく、事実に基づいているように感じられるフィクションも含まれ、若者の嗜好に合致していた。
子どもが大人に勝つ物語の構造
『名探偵コナン』や『探偵チームKZ事件ノート』など、「子どもが大人に勝つ」型の作品は、社会や大人に対する不満を物語で昇華する形式であった。大人はしばしば敵として登場し、子どもたちが知恵や勇気で打ち勝つ構図が読者に爽快感を与えた。また、主人公に味方する大人は社会の枠から外れた存在である場合が多く、子ども寄りの価値観を持つ者として描かれていた。
三大ニーズへの適合性(子どもvs大人)
この型はポジティブな感情だけでなく、敵役の大人による圧力や裏切りを通してネガティブな感情も引き出す構造であった。反抗心や自意識に訴えかけ、進路や人間関係の悩みといったテーマも自然に織り込まれた。予測しやすく感情的に入り込みやすい展開は、読者にとって親しみやすいものであった。
デスゲーム・サバイバル・脱出型の人気
『バトル・ロワイアル』に始まるデスゲームは、極限状況でのサバイバルを描いた形式として人気を集めた。命のやり取りが緊張感を生み、感情の振れ幅を増幅させる構造であった。登場人物の死が簡単に描かれることで、感情移入やドラマが強調され、読者を惹きつけた。
社会への不満とフィクションの代替行動
デスゲームの理不尽さや競争は、学校や社会の圧力に対する比喩と捉えられた。登場人物たちが極限の状況で本音を吐き出し、日常では不可能な行動を取ることで、読者はカタルシスを得た。自己の抑圧された感情をフィクションで代償的に解放する場として、強い支持を受けたのである。
簡潔な文体とゲーム実況的受容
これらの作品は情景や心理描写を最小限に抑え、会話と出来事主体で展開された。山田悠介作品や『青鬼』などは、既存の文壇的評価とは異なる枠組みで広がり、ゲーム実況や動画サービスとの連動も人気拡大に貢献した。若年読者に届くための「読みやすさ」が、評価基準の変化を象徴していた。
ジャンルの交代と退場
かつて中高生の間で圧倒的な人気を誇った『王様ゲーム』や山田悠介作品は、徐々に読まれなくなった。その背景には、児童文庫でもデスゲームが普及したことや、設定の時代遅れ感が指摘されていた。山田作品のガラケー使用やシンプルすぎる展開が、スマホ世代には古く映ったのである。
余命ものと死者との再会の定番性
「余命もの」は、主人公や恋人の死が確定した状態から始まり、感情を爆発させる展開を用意することで読者の心を揺さぶった。「死者との再会・交流」型は、一時的な再会による感情の高まりと再びの別れによる哀切さで読者を引き込んだ。いずれも三大ニーズを的確に満たす構造であった。
感情のピークと読者のカタルシス
「余命もの」は、焦燥感や後悔、本音の吐露といった要素が中高生の内面と重なり、強い共感を呼んだ。また「死者との再会」では言えなかった言葉のやり取りが物語の核となり、読者自身の願望とも一致していた。これらは読みやすく、予測しやすい展開によって感情移入が促進された。
長期的な人気の根拠
余命ものや死者との再会型は、2000年代以降の純愛ブームや難病もの、さらには戦後の伝記文学などとも連続していた。『セカチュー』や『いま、会いにゆきます』などもこの系譜に属し、現代の若者にとって新しいものではなく、常に一定の需要を持ち続けている型であった。今後もこの流れは継続すると思われる。
第三章 カテゴリー、ジャンル別に見た中高生が読む本
児童文庫の読者層の拡大
かつて小学生を対象としていた児童文庫は、近年では中学生にも読まれるようになっていた。特に中学1〜2年生の男子を中心に『名探偵コナン』や『ぼくら』、『KZ事件ノート』などが読書調査で上位に入っていた。以前は中学に進学すればラノベや一般文芸へ移行する傾向が強かったが、近年は児童文庫の読者年齢層がやや上昇しつつあった。
児童文庫が中学生に読まれる理由
読者層の変化には三つの理由があった。第一に、2013年以降児童文庫レーベルが増加し、刊行点数とシリーズが充実したことであった。第二に、マンガやアニメ、ゲームのノベライズが児童文庫から多く刊行され、中学生も自然と読み続ける環境が整ったことである。第三に、ラノベが大人向けにシフトした結果、中学生が「自分たちのための本」を見つけにくくなったことで、児童文庫に居場所を見出すようになった点が挙げられた。
マンガノベライズの定着と工夫
マンガノベライズは2000年代後半から中高生の読書調査に登場し、集英社のJUMP j BOOKSが業界常識を覆す成功例となった。特に『D.Gray-man』や『銀魂』などがヒットし、原作と同様の装丁により書店での陳列や流通面でも工夫が凝らされた。また、実写映画化された少女マンガのノベライズも人気を博し、若手俳優の表紙写真によって購買層を広げることにも成功した。
レーベル別の読者層戦略
同じ原作であっても、集英社は児童文庫の「みらい文庫」、女性向けの「オレンジ文庫」、少年向けの「JUMP j BOOKS」といった複数レーベルで異なるターゲットに合わせてノベライズを展開していた。これは読者層ごとの文体や装丁の違いを反映したものであり、読者の取りこぼしを避けるための戦略でもあった。
中学生男子に読まれる『星のカービィ』
角川つばさ文庫の『星のカービィ』シリーズは、精神的・読解的にまだ成長途上の中学生男子に好まれていた。キャラクターの動機が食欲であり、内容は極めて平易、挿絵も多いため、読書へのハードルが低く設定されていた。これは「軽い内容の本も必要だ」とする認識に基づく分析であり、「中学生にもなってこれを読むのか」という否定的評価を乗り越えるべきだと筆者は主張した。
低読解層への読書支援の提案
中学生男子の中には、読書力が十分に育っていない層が存在しており、彼らにも届く本の必要性が説かれていた。かつての花井愛子作品やあかほりさとる作品のように、軽快な文体と平易な内容が若年層の読書意欲を刺激していたように、『カービィ』にも同様の役割が期待されていた。
『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』の中学生人気
廣嶋玲子『銭天堂』シリーズは、小学生向けとして出発したが、中学生女子にも支持されるようになった。善悪の二元論に収まらないシビアな物語展開、登場人物の欲望と失敗、紅子やよどみといった強烈なキャラクターが、中学生の興味を引いた。特によどみの存在は、現実の人間関係に潜む悪意を象徴していた。
読者層の変化と装丁の工夫
『銭天堂』は児童書でありながら、大人向け文芸書と同様のソフトカバーであり、同時に総ルビと平易な文体により読みやすさを確保していた。このバランスが中学生にとって「子どもっぽくないが難しすぎない」適切な水準となり、幅広い支持を得ていた。
総ルビ書籍の必要性と提言
筆者は『カービィ』や『銭天堂』の需要の高さから、大人向けでも総ルビ書籍の導入を検討すべきだと述べた。出版業界には「漢字が読めて当然」という認識が根強くあるが、実際には常用漢字でも読めない人は多く、ルビを加えることで読書へのハードルを下げることが可能であると指摘した。読書推進の観点からも、より広い層に届く本作りが求められていた。
ライトノベル人気の変遷と市場構造
ライトノベルは2010年代初頭に中高生の間で絶大な人気を誇ったが、近年では市場規模と影響力の双方で縮小傾向にあった。その中でも長期的に読まれ続けている作品は、中高生に強く訴える要素を備えていた。市場全体が大人と10代のどちらをターゲットにするか迷走した結果、従来の中高生読者が離れていったが、一部作品は依然として若年層の支持を集めていた。
『キノの旅』の普遍性と形式の魅力
2000年より刊行された『キノの旅』は、ラノベとしては例外的に20年以上中高生に読み継がれた作品であった。短編形式で各国を巡るロードムービー的な構成が、朝読書などの短時間読書に適しており、また皮肉とビターさを含む内容が思春期特有の自意識に響いた。主人公キノの「ボク女」的な設定も、特別感を演出する一因であり、自我の揺れ動きや社会への疑問といった内面描写が中高生に刺さる要素となっていた。
ビジュアルとデザインの重要性
『キノの旅』の成功には、黒星紅白によるイラストと鎌部善彦のデザインが大きく寄与していた。ビジュアルは孤独感や抒情性を表現し、作品全体の世界観と融合していた。また、露骨な性的描写がないことから、図書館でも扱いやすく、中高生に安心して推薦できるラノベの代表格となった。
『SAO』と〈物語〉シリーズの持続的人気
『ソードアート・オンライン』はデスゲームとVR世界の要素を取り入れた作品で、特に中高生男子に高い支持を得ていた。〈物語〉シリーズは、怪異を通じて思春期の悩みを具現化し、内面の葛藤と対峙する物語で構成されていた。軽妙な会話と深刻なテーマが共存し、「軽さ」と「重さ」を両立させた点が長期的な人気の理由となった。
〈物語〉シリーズの特徴と時代的な限界
西尾維新の〈物語〉シリーズは台湾のイラストレーターVOFANを起用し、流行に左右されないデザインを維持していた。箱入り書籍という特殊仕様も図書館での扱いやすさに寄与した。ただし、性的描写が多く、2000年代的なサブカル文化に影響された表現が、現代では違和感を覚えさせる可能性があり、今後の継続的な人気には疑問も残った。
『ようこそ実力至上主義の教室へ』の教育観と構造
『よう実』は学校という閉鎖空間を舞台に、卓越性と公正という教育の二大原理を対立構造として描いた作品である。主人公綾小路は冷徹で超人的な頭脳を持ち、大人の策略にも打ち勝つ存在として描かれた。集団戦形式の競争や個人の感情の暴露などが、読者の関心を惹きつけた。教育の理念や格差、適応と反発という構図も物語に深みを加えた。
『Re:ゼロ』のループ構造と感情の振れ幅
『Re:ゼロから始める異世界生活』は、異世界転移と死に戻りをテーマにしたループものとして、読者に強い感情の揺さぶりを与えた。恋愛と死の両方が描かれ、「余命もの」「死者との再会・交流」の要素も併せ持っていた。主人公スバルの試行錯誤と挫折、感情の爆発が中高生の内面に響き、持続的な人気を保っていた。
他の人気作品と四つの型の共通点
『探偵はもう、死んでいる。』は死亡確定ロマンスと死者との再会を描き、『86―エイティシックス―』は差別と戦争を題材にしながらも、「子どもが大人に勝つ」型を内包していた。『薬屋のひとりごと』や『わたしの幸せな結婚』も若者が知恵と意志で困難に立ち向かう展開を持ち、中高生に訴求力のある構造であった。
ラブコメの立ち位置と性への関心の変化
『このラノ』ではラブコメが10代に人気だが、学校読書調査では上位に来ることは少なかった。これはラブコメの読者がラノベファンに限られるためであり、中高生全体で見るとマイナーなジャンルであった。また、性行動調査により、若者の性への関心が低下していることが明らかになり、性的要素を含む作品は受け入れにくくなっていた。
性的要素の希薄な作品の成功例と傾向の変化
『転生したらスライムだった件』のように、性的要素がほとんどない異世界転生作品が広く人気を集めていた。これはラノベに限らず、エンタメ全体においても「エロを入れないほうが好まれる」傾向が強まっていることを示していた。性描写や過度なラブコメ展開を排した作品が、より多くの読者を獲得しやすい構造に変化していたのである。
まとめとしての傾向分析
ラノベファン特有の需要がある一方で、中高生全体に訴求するには「自意識+どんでん返し+真情爆発」や「子どもが大人に勝つ」といった構造を持ち、性的要素を控えた作品が有利であった。読者の嗜好や社会背景を反映し、現在の人気作品には共通する型が存在していた。
ボカロ小説の誕生と展開
ボカロ小説は、ボーカロイド楽曲の世界観をもとにした物語として誕生し、楽曲・歌詞・MVを基に小説化されるジャンルであった。初音ミクなどのキャラクター性が強調され、ユーザーによる二次創作が活発化する中で、小説もその流れに乗った。『悪ノ娘』をはじめ、物語性を持つ楽曲から派生した作品が登場し、主に若い女性層に受け入れられていった。
『カゲロウデイズ』の社会的反響と区分けの曖昧さ
『カゲロウデイズ』はキャラクター性とループ構造、過激なモチーフを特徴とし、社会現象を巻き起こした。しかしこの作品にはボーカロイドは登場せず、ボカロ楽曲を原作としながらもキャラクターはすべてオリジナルであった。この構造の違いは、商業展開における権利関係にも影響を与え、ボーカロイドキャラクターを使うか否かでビジネス上の利便性が異なっていた。
HoneyWorksと少女マンガ的恋愛構造
HoneyWorksが手掛けた『告白予行練習』シリーズは、MVと小説を連動させ、中高生の青春恋愛を描く構成で人気を博した。男女混声ボーカロイドによる曲と、それを小説化した青春群像劇は、少女マンガ的世界観を音楽と物語の双方で展開し、ティーン層から強い支持を得た。部活動や進路、友情など、恋愛以外の要素も盛り込まれ、思春期の複雑な心情を描き出した。
ボカロ第二次ブームと新たな文芸表現
2020年代には、n-bunaによる『盗作』、YOASOBIの『夜に駆ける』、カンザキイオリの『あの夏が飽和する。』といった作品が注目された。これらはボカロ曲出身でありながら、キャラクター性を排した一般文芸的スタイルを取り、過激なモチーフや心理描写に重点を置いた。さわやかさを排し、家庭内不和や死、世界の終末といった重い題材が扱われ、第一次ブームとの共通項が存在していた。
キャラクター小説の再興と中学生男子層
再びMF文庫Jから『グッバイ宣言』『ベノム』といったボカロ小説が刊行され、中学生男子に人気を得た。これらは主人公が周囲と折り合えずに孤立する中で、人間関係の中で変化していく姿を描いており、曲の背景に物語性を与えたことで読者の共感を集めた。『ベノム』では「求愛性少女症候群」という異常現象の設定が加えられ、『青春ブタ野郎』シリーズとの共通性も見られた。
ジャンルを越える10代の共通ニーズ
ボカロ小説とラノベは読者層が異なるとされるが、「思春期の自意識、反抗心、本音に訴える」物語構造は共通していた。10代が求める感情の型は、作品のジャンルやメディアを超えて似通っており、それゆえに似たモチーフや構造が繰り返し用いられていた。
一般文芸とミステリー作品の台頭
2020年代からは、学校読書調査の方式変更により、シリーズ作品の合算集計が導入された結果、ミステリーや探偵小説が目立つようになった。中高生に人気の作品には、湊かなえや東野圭吾、西尾維新、知念実希人らの作品が含まれており、ジャンルの広がりとともに、一般文芸への関心も高まった。
『古典部』シリーズの男子高校生支持
米澤穂信の『古典部』シリーズは、思春期の自意識、どんでん返し、真情爆発を描いた学園ミステリーでありながら、人が死なない日常の謎を中心に据えていた。折木奉太郎という斜に構えた主人公は、読書傾向のある高校生男子にとって自己投影しやすい存在であった。恋愛要素や感情描写は控えめだが、終盤に明かされる真実や苦い青春描写が共感を呼んだ。
『古典部』の位置付けと読者層の限定性
同作はラノベ的要素も持つが、出版形態や語り口により一般文芸として認識される場合も多かった。タイトルや設定のとっつきにくさから中学生には届きにくく、高校生男子に限定的に支持される作品となった。ラノベを「よく読む」層が少数派であることを考慮すると、『古典部』のようにラノベ読者以外にも届く内容が、読書調査で上位に入る条件であった。
知念実希人作品とミステリーの三大ニーズ適合性
知念実希人の作品は、「デスゲーム」「余命もの」「子どもが大人に勝つ」「自意識+どんでん返し+真情爆発」などの型に沿った構成で、10代のニーズに適していた。『仮面病棟』は脱出劇として、『崩れる脳を抱きしめて』は悲恋ものとして、『天久鷹央』シリーズは若い主人公が大人を凌駕する展開としてそれぞれ成立していた。
『天久鷹央』シリーズの継続的支持
とりわけ『天久鷹央』は、装丁や文体の工夫により、高校生にも受け入れられる「子どもが大人に勝つ」物語として機能していた。エピソードごとに切なさや信頼が描かれ、どんでん返しや真情爆発の構造も備えていたため、長期的に支持される要因となった。児童文庫から離れていく中学生が次に読む作品として、自然な受け皿となったのである。
読書率低下という“常識”の揺らぎ
文部科学省が発表したデータに基づき、メディアは若者の活字離れを報じてきた。しかし著者は、その根拠となる調査設計や質問形式に疑義を呈し、調査結果そのものが読書実態を正確に反映していないと指摘した。特に、「1か月に1冊も本を読まない」設問が読書の全体像を捉えていないことを強調し、選択肢の偏りが回答を誘導していたと論じた。
「不読率」という統計の意味づけ
不読率という単一指標だけで読書離れを断定する傾向に対し、著者はその危険性を訴えた。統計の読み取りには多様な視点が必要であり、特に若者に関する調査結果は世代や生活背景に即した複眼的な解釈が必要であった。実際には、読書をしている層が一定数存在しており、単なる冊数だけで判断することは不適切であると論じられた。
読書行動の多様化と背景事情
若者が本を読まなくなったという単純な議論ではなく、読書行動が多様化しているという事実が示された。電子書籍やスマートフォンの普及、SNSとの接触などにより、活字との関わり方が変化していた。また、学校や家庭での読書指導、学習環境も読書率に大きな影響を与えていた。読書行動は生活の中に自然に組み込まれるものであり、単なる統計だけで語れるものではなかった。
調査設計とメディア報道の責任
読書離れを煽る報道の背景には、調査方法の問題があった。読書という行動の定義や、質問の文言の微細な違いが結果に大きな影響を与えていた。特に読書の「定義」が曖昧なまま報道されることで、実態から乖離した「読まない若者」というステレオタイプが強化された。著者はメディアの報道姿勢と調査の設計責任の双方を問うていた。
若者像の固定化と“上から目線”の問題
社会における「若者」像が一様に語られ、しばしば非主体的であると決めつけられる傾向に対し、著者は警鐘を鳴らした。読書率の低下は若者自身の問題というよりも、社会の側が作り出したイメージの産物であり、教育者や大人が若者に対して上から目線で語る構造そのものが問題であった。若者自身の言葉や行動を丁寧に拾う姿勢が求められていた。
終章:読書の価値と社会のまなざし
著者は最後に、読書が単なる知識の習得ではなく、自己との対話であると語った。読書率の数字だけに注目するのではなく、読書を通じた個人の成長や社会との関わりを考える必要があった。若者の読書行動を批判的に見るのではなく、彼らがどう読書と関わっているかに注目する視点こそが、今後の社会に必要な態度であると結ばれていた。
第四章 10代の読書はこれからどうなるのか
読書推進施策の意義と限界
若者の読書量は最終的に平均して月2冊未満に収束する傾向があったが、それでも幼少期からの読書経験は語彙力や調べ物のリテラシーに寄与していた。1990年代後半以降に行われた読書推進活動には一定の成果があり、本を読む環境整備は教育的意義を持っていた。ただし、もともとの気質により本に興味を持たない人には効果が限定的であり、成長とともに環境よりも個人の選択の影響が強まる傾向があるとされた。
高校生への読書支援と図書館の課題
高校生への読書推進策として、公共図書館や学校図書館による企画が行われていたが、多くは中高生のニーズを十分に捉えておらず、成果が限定的であった。ライトノベルの蔵書拡充も効果が薄れつつあり、読ませたい本と読みたい本の乖離が見られた。ニーズを把握せずに一方的に本を提供する姿勢に対し、著者は中高生当事者の声を取り入れたレコメンドや企画を提案した。
大学生への読書支援とアクティブラーニング
大学ではアクティブラーニングの一環として図書館のラーニング・コモンズ化が進んだが、それだけでは読書習慣を定着させるには至らなかった。大学1年生向けにレポートの書き方や図書館の使い方を教える初年次教育が導入され、中等教育とも連携して探究的な学びが推進されたが、大学生の読書量や不読率は改善していなかった。
大学生向けの楽しみの読書支援策
学術的読書支援に加え、趣味としての読書支援にも余地があった。大学生協による「読書マラソン」や「ビブリオバトル」などの活動が展開されたが、既に読書習慣がある者向けであり、読んでいない学生に向けた施策は手薄であった。大学進学を機に一度読書をやめた者への再アプローチや、大学4年生に向けた再読の誘導が効果的であると示された。
雑誌読書の推進余地と効果
書籍に比べて読書量の変動幅が大きい雑誌は、高校生・大学生への読書推進における可能性を秘めていた。ビジュアル要素や短文構成により、読書に苦手意識を持つ層にもアプローチできる点が魅力であった。雑誌は構成や正確性でも書籍に次ぐ信頼性を持ち、読解リテラシーや表現力向上にも寄与する教材となり得るため、推進活動の焦点とすべきであるとされた。
「本離れ」という誤解と読書実態の再認識
小中学生の読書量は過去最高水準であり、高校生の読書率も改善傾向にあった。大学生の不読率は高いが、それは大学進学率の上昇による層の多様化と読書志向の変化によるものであり、必ずしも読書離れとは言えないとされた。ネットやスマホの影響も読書時間に大きな変化を与えていないことが指摘された。
中高生の読書ニーズと四つの型
中高生の読書には三大ニーズが存在し、①感情を揺さぶる、②自意識や本音への訴求、③予測可能な読後感であった。それを満たす代表的な構造として「①自意識+どんでん返し+真情爆発」「②子どもが大人に勝つ」「③デスゲーム・サバイバル型」「④余命・死者再会型」の四つが挙げられ、ジャンルを超えて支持を得ていた。
小説以外の人気ジャンルと共通要素
中高生に読まれる小説以外の書籍には、「勉強・知識にエンタメ要素を加えたもの」「思春期の不安に寄り添う生き方指南」「恋愛や人生のポエム的表現」といった特徴があった。こうした傾向は、「身近」「現実的」「わかりやすい」を重視する読者の嗜好を反映していた。
「子どもの本離れ」神話の形成背景
1980年代〜1990年代の雑誌市場の縮小や出版不況の記憶が、「本離れ」への誤解を生んだ。たまたま不読率が上昇した年に話題化されやすく、改善された年には注目されない傾向がメディアにあった。また、書籍好きの大人が自分の嗜好を基準に読書の水準を定めていることも、読書状況の誤解に繋がっていた。
読書に対する現実的視座の必要性
若者の読書状況を論じる際、「大人が読ませたい本」と「子どもが読みたい本」の違いを認識すべきである。中高生は大人の平均よりも多く読んでおり、それ以上を望むことは過剰である。若者の嗜好や特性を「あるがまま」に受け入れ、その現実を基に読書支援を考えることが、効果的かつ持続可能な施策に繋がると結ばれていた。
あとがき
ライトノベル研究から始まった執筆動機
筆者の初単著は2012年に刊行されたライトノベルに関するものであり、当時は文庫ラノベ市場がピークを迎えていた。ラノベが「中高生向け」として認識されていた時代に、それを当事者の視点から論じた経験が、筆者の執筆姿勢の原点となった。
若年読者と批評の乖離への違和感
2000年代初頭、西尾維新が若くしてミステリー界に登場し、年長世代からの批判にさらされる様子を目の当たりにしたことが、筆者の文筆活動の動機の一つであった。受け手と送り手の認識の差、当事者による語りの重要性を実感し、それを言語化する欲求が芽生えた。
法社会学的視点と価値観の多様性
大学時代に学んだ法社会学の影響により、筆者は制度的な価値観と民間の価値観が異なることを理解し、純文学や主流文学的な枠組みに収まらないジャンル作品の価値を見出す視点を持つようになった。読書推進活動の中で排除されがちな軽文学や娯楽作品の意味を掘り下げようとする姿勢が根底にあった。
若者の読む本に対する社会の偏見
絵本や児童文学を除いた多くの「若者向けの本」は、文壇や新聞において取るに足らない消費物として扱われてきた。SFやミステリーのファンですら、自分たちが読まないラノベやケータイ小説を「評価に値しない」とみなす傾向があり、教育現場でもそうした偏見が根強く存在していた。
教師や司書による「良書」信仰の影響
学校教育においても、生徒が好きな作品を積極的に肯定せず、「良質な本」をどう届けるかに注力する構造があった。中高生の読書V字回復や不読率の改善は、そうした教育現場の努力の賜物であったが、その過程で「読む喜び」の多様性が十分に尊重されていたとは言い難かった。
現実の読書行動と評価の乖離
実際に多くの若者が読んでいる作品が存在していても、それを正しく理解しようとする姿勢が社会に欠けていた。中高生によるラノベやノベライズの読書行動が、ステレオタイプに基づいた誤解により過小評価され、誤った「本離れ」像が再生産され続けていた。
書籍偏重と「良書」主義の限界
書籍中心、良書中心の読書観が、実際の読書状況との乖離を招いていた。このギャップは出版産業や教育政策、文化史の観点からも望ましい状態ではなく、若者理解の障壁ともなっていた。筆者はこの乖離を埋めるために本書を執筆したと述べている。
執筆の経緯と謝意
本書は、筆者が2020年に刊行した『いま、子どもの本が売れる理由』の続編的位置づけにあり、前著で扱えなかった「中高生編」に該当する。原稿の初出媒体の編集者たちや協力者への感謝の言葉が綴られ、またミハイル・バフチンの著作を刊行してきた平凡社から出版できた喜びも語られていた。
歴史的視点の未収録と将来への展望
本書では歴史的変遷を十分に扱えなかったことに対する残念さが述べられたが、今後改めてまとめる機会を設けたいという意欲が記された。また10年後に再び「10代の読書」について書くことへの意欲も表明されていた。
個人的な献辞と締めくくり
本書の執筆中に旅立った愛猫「ちぃ」への献辞で結ばれ、筆者の個人的な思いが静かに添えられていた。読者への最後のメッセージとして、自身の立場の限界を認めつつ、下の世代からの批判と感想を受け止める姿勢が示されていた。
同著作品
読者ハ読ムナ(笑)

類似作品


それ、なんで流行ってるの?

ノンフィクション

Share this content:
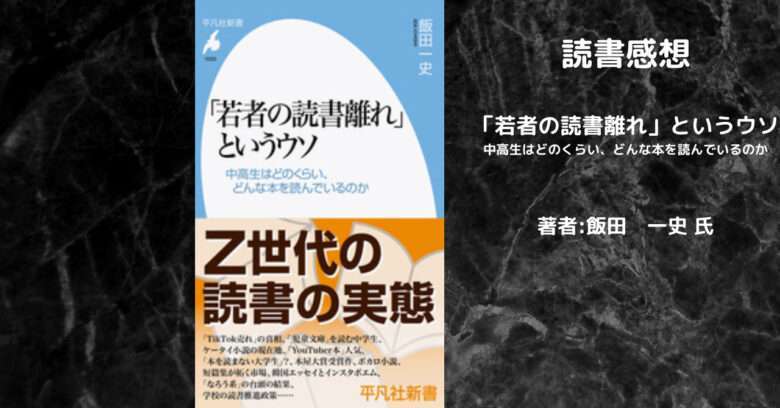

コメントを残す